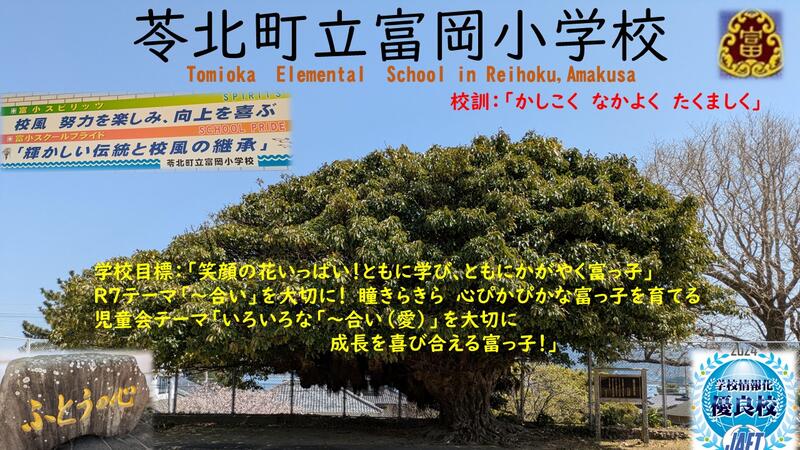
最終更新日 2026.02.18

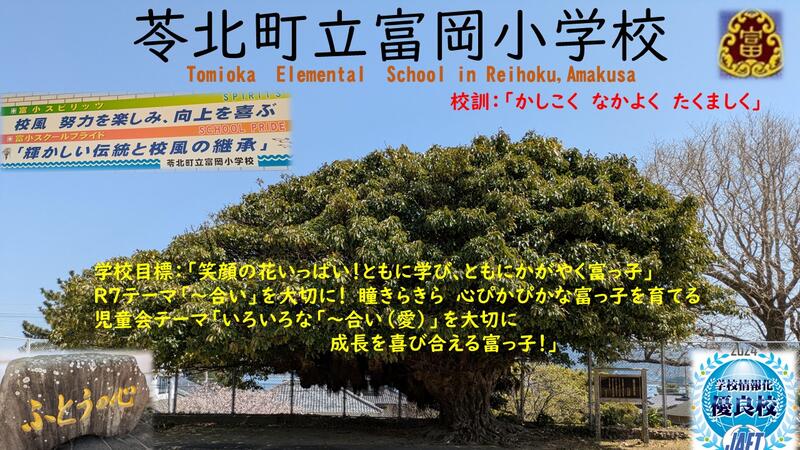
最終更新日 2026.02.18
今日の給食は、ふるさとくまさんデーでした。
太平燕。おいしく頂きました。
ちなみに昨日は八珍汁。貴重な八種類の具材が入っている汁物。
どれが8種類か数えながら楽しく頂きました。
高学年は、ハードルの練習中です。
4年生は昨日の授業の様子から。立方体づくりです。
「ああ、一面足りませんでした・・・」「1cmの立方体つくりました」など算数的活動を楽しみながら行っていました。
2年生も昨日の様子です。コップが飛び出す工作です。どんなびっくり工作になるのかなあ・・・楽しみですね。
熊日学童スケッチ展の作品を一つ紹介していませんでした。
明日から三連休です。ニュースなどを見ていますと感染症の拡大も心配ですね。まずは免疫力です。しっかり食べて、しっかり運動して、しっかり寝て、心のリラックスを図ってくださいね。
いい三連休になりますように♡
苓北町役場ホールでは、県子ども芸術祭オール天草に出品された子どもたちの作品が展示してあります。
お時間や用事がある方は、ぜひご覧ください。
今日は児童総会がありました。第2回目の児童総会は、「富岡小をさらによくしていくために」という共通認識のもとに、児童がそれぞれ分かれて児童会活動を行い、1年間の活動をまとめ、次年度の準備の場です。これまで委員長として、また委員長を支える立場として活躍してきた6年生。まさにリーダーでした。
その様子です。
企画委員会
給食委員会
環境委員会
放送委員会
体育委員会
保健委員会
図書委員会
児童からもたくさんの感謝の言葉がありました。
最後に私の挨拶です。
「2月も半ばになり、今の学年で過ごす時間も、あと少しとなりましたね。今日は、6年生がこれまでリードしてくれ、「学校を更によくしようと」取り組んできた児童会活動の1年間のまとめです。さて、皆さんが今年度、大切にしてきた児童会のテーマを覚えていますか? 「いろいろな『合い(愛)』を大切に、成長を喜び合える富っ子」でしたね。この「あい」という言葉には、たくさんの素敵な意味がこもっています。
〇友達と助け「合い」、支え「合い」〇元気に挨拶し「合い」 〇友だちを大切にした聴き「合い」・学び「合い」〇認め「合い」 〇周りの人を大切にする感謝の「愛」
皆さんの周りには、この1年間でたくさんの「合い(愛)」があふれていました。 困っている1年生に優しく教える上級生の姿、転んでしまった子に「大丈夫?」と声をかける姿。その一つひとつが、富っ子の大切な「宝物」です。
3学期は「まとめ」の学期であり、「準備」の学期でもあります。 今日の児童総会での話し合いは、6年生がリードしてきた1年間のまとめでもあり、これから5年生がリーダーとして引っ張っていく準備のスタートでもあります。今の富岡小の仲間と、最後までたくさん「合い(愛)」を届け合ってください。
そして、委員会、クラブ活動、登校班、そして普段の生活で6年生は皆さんを親身に思って、見えるところ、見えないところで様々な取組をしてくれていました。あと20数日で卒業する6年生への感謝、そして新しく入ってくる1年生への優しさを準備して、もっともっと富岡小を良くしていくための時間としていきたいですね。」
今日の給食は、ソフトフランス、白身魚そしてポトフでした。おいしくいただきました。
日曜日には学級懇談会のあとに子ども育成会餅つき大会を行いました。
餅米を提供してくださった倉田様、お手伝いをしてくださった富岡女性の会の皆様、そして育成会の皆さんありがとうございました。
私が以前本校に勤務していた頃は3月に行なっていたのかなあ。コロナ禍で中断して、一昨年実施して、本年度たくさんの皆さんのご協力もあって実施となりました。
事前に使用する道具を確かめ綿密に計画を立てられ、金曜日にはたくさんの保護者の方が手伝いに来てくださりセッテイングと6年生と餅米の準備。そして日曜日は朝8時から火を起こして準備。
子どもたちのためにと保護者の皆さん、そしてそれを手助けしてくださる地域の皆さん、すてきなこれぞ富岡パワーを改めて実感しました。ありがとうございました。
6年生が餅つき、4年生と5年生が餅丸めをしました。子どもたちも美味しそうに食べていました。「校長先生、18個食べました。」「私は14個」など笑顔で話してくれました。
途中で記念撮影。すてきな富岡らしい時間でした。
今日の給食は元気の出るレバー。元気になりました。
本日の授業参観、PTA総会、学級懇談会、子ども育成会餅つき大会はありがとうございました。
今日は、授業参観の様子から写真を中心にお知らせします。
子ども育成会餅つき大会は火曜日にお知らせしますね。
たんぽぽ学級の様子です。
1年生の様子です。
2年生の様子です。
3年生の様子です。
4年生の様子です。
6年生の様子です。
5年生の様子です。
お世話になりました。
最後にPTA総会でお話した校長挨拶の一部です。
「 令和7年度も、残すところ卒業証書授与式を含めてあと24日となりました 。 本日は、これからの学校運営に関わる3つの重要な点、①複式学級の設置、②学力調査の結果、③教育評価についてお話しさせていただきます 。
本校でも児童数の減少に伴い、令和8年度から複式学級を設置することとなりました 。この表は、苓北町の学齢簿をもとにした児童数の推移です。今後も統合までの4年間で複式学級が増加していきます。 複式学級設置にともない「チーム富小」として複式学級を支えていく体制づくりを現在構想しているところです。授業のスタイルも様々な形態になってきます。二つの学年が一つの教室で学ぶ複式の授業、一つの学年だけで学ぶ単式の授業、隣接学年と一緒に学ぶ共同の授業、担任外の教職員が指導する授業など現在どのような学びが可能かを構想しています。少人数での学習となるため、一人ひとりに目が届きやすくなるメリットがある一方、指導の工夫が求められます。学校としては、これまで以上に丁寧な指導体制を整えてまいります。
保護者の皆様にご協力いただいた学校評価アンケートについてです。今回は50家庭のうち50回答をいただき、皆様の教育に対する熱意を強く感じております 。
「心:なかよしの花」についてです。本年度は、「心の教育の充実」を最重要テーマとして学校経営、学校の教育活動を展開していきました。その中で、「いじめ・不登校対策の充実」「人権意識の向上、人権感覚の醸成」において評価が向上しました 。しかし、考察にも記していますが、「いじめはいけないことだと思いますか」という問いに一定数の児童が「理由があればいじめはいけないことだとは思わない」と回答していました。このことは、本年度の取組を一考しないといけないことと捉え、3学期の心の教育の更なる充実を現在はかっているところです。また、「児童と担任の関係の希薄さを感じる」という声をいただきました。この声を真摯に受け止め、児童一人一人との対話を重視した取組を今後も進めていきます。
「学び:がんばりの花」についてです。特別支援教育への肯定率が98%と非常に高く、個に応じた指導が評価されていました。。一方で「家庭学習の習慣化」や「読書活動」に若干の低下が見られました 。
「健康:元気の花」についてです。防災教育などの安全教育は向上しましたが、私たちも「体力向上」には課題が在ると考えています。体力テストで課題であった跳躍力や走力などの向上を体育の授業や集会活動などで今後も取り組んでいきます。
「感謝の花」についてです。全体的に高い評価を頂いていますが、早期対応・情報交換については、今後も重視して学校総体として取り組んでいきます。
保護者の 皆様からいただいた記述回答や口頭等でのご意見の中には、「先生方が一人ひとりに寄り添ってくれている」という温かい励ましの一方で、学校の働き方改革についてについてなど貴重なご指摘もいただきました 。
児童数の減少に伴う教職員数の減少を考慮した、学校の働き方改革は、「子どもとの向き合う時間の確保」という意味からも進めていきますが、それには保護者の皆様のご協力に頼る部分も多くなってくると思います。皆様からの声を真摯に受け止め、残りの24日間、そして令和8年度に向けて、子供たちが「自分らしく楽しい学校生活」を送れるよう、教職員一同取り組んでまいります 。 引き続き、本校の教育へのご支援をよろしくお願いいたします。
2月の保健目標は「心の健康を考えよう」です。
メインの掲示を、定期的に子どもたちが興味をもち、生活な中でちょっと考るきっかけとなるようにチェンジしながら掲示してくれています。ありがとうございます。
「こころがもやもやしたときどうする?」
もやもやは年齢、男女問わずありますよね。子どもたちもそうだと思います。自分のこころをいろんなきっかけで一歩前へ半歩前へでいいと思います。掲示を眺めながら思ったところでした。ちなみに私は2.10.20の方法かなあ。
さて、本校の教員業務支援員の先生が、熊日学童スケッチ展の入賞作品を「富小美術館」として掲示してくださいました。いつもありがとうございます。
日曜日の授業参観の時にぜひ見ていただければと思います。ホール、東側階段踊り場、東側2階階段、放送室前に分散して掲示しています。
他にも「版画」でもたくさんの賞をいただきました。また、描画では「熊本県子ども美術展」にも出品、入選していますので、今後その作品も展示していただけると思っています。
先日、「文化」についてお話しする機会がありました。その際に、ある方が『「文化」はなかったり、気にしなくても生活の上ではそんなに困ることは少ないと思います。しかし、絵画、工芸、音楽・・・いろいろな「文化」に囲まれていると人生を豊かにしてくれます。その豊かさが人生をいい意味で変えたり、厚みを持たせたりしてくれます」というお話をされました。まさにその通りと思います。校舎内が子どもたちの作品がたくさんあふれるステキな空間になっています。
さて、昨日の短縄跳びグランプリの様子です。躍動感あふれる、リズムある一瞬をご覧ください。
さて、今日の給食は、これ。おいしくいただきました。何とバレンタイン給食です。ありがとうございます。
画像が上下逆になってしまっています。すみません。ハヤシライスとってもおいしかったです。
さて、正門の水仙がきれいに咲いています。冬だなあと感じました。
さて、火曜日の4年生の授業の様子を少し紹介します。
算数の「変わり方」の学習です。「テーブルの数と座れる人数の関係のきまりを表に書いて調べよう」が今日の課題です。
しっかり、集中して考え、グループで聴き合って、そして学び合って学習が進みます。
下の写真いいですよね!学びをとても感じます。
4年生の皆さんも、もう1ヶ月半で、高学年です。期待していますよ。高学年としてのリーダーシップの準備をよろしくお願いします。
さて、本稿の部活動ではないのですが、5年生6人、6年生6人からなる富岡小器楽合奏クラブが熊本県立劇場でプロピアニスト金子三勇士さんのコンサートに共演しました。これは、11月に行われた熊本県器楽合奏コンクールの出場校で小学校1校、中学校1校に与えられたMIUJI賞です。
会場は、ほぼ満員でした。その中で、堂々とそして「心を磨いて 音を磨いて」きた音楽♪モーツアルトの「ディベルティメント」を金子さんのピアノとしっかりハーモニーしながら、会場を素晴らしい音で包んでくれました。
物怖じせずに、あの会場で、あの観客の前で演奏している富っ子に感動しました。
下は、リハーサルの時の様子です。
ありがとうございました。
私が地域で出会った方々にも、よく「器楽!応援しているけんね!」と話しかけてくださいます。
子どもたちの努力、外部指導者の方の熱意、保護者の皆さんのご協力、地域の皆さんの思いがあっての地域クラブとしての活動だなと思います。ありがとうございました。
今日は、苓北の魅力を知ることを目的とした地域学習です。
東京から学生が苓北町に来てくれています。それもミカンをこよなく愛する学生さんたちです。
地域おこし協力隊の方々、苓北町観光協会の方々、苓北町役場の方々、苓北町教育委員会の方々というバックアップがあっての実施です。
学生の皆さんも早めに来て事前の最終調整です。ありがとうございました。さあ、活動の時間の様子です。
子どもたちの感想を紹介しますね。
「みかん愛好会の皆さんへ
今日は東京から私たちのために来てくださってありがとうございました。私は、みかんが大好きなので、あまいみかんの見分け方がわかったのでスーパーで見てみたいと思います!!あまいみかんがたべれますように!!」
「みかん愛好会のみなさんへ
お忙しい中、東京から苓北まで来てくださってありがとうございます。私は、みかんがとても好きで今回はみかんのことについて知れてとても嬉しかったです。みかんを食べるときは教わったことを使いたいと思います。」
「みかん愛好会のみなさんへ
東京から富岡まできていただき、みかんのことについて教えていただいきありがとうございます。私はみかんが大好きなので、私が知っていることよりもみかんについて知れたのでよかったです。本当にありがとうございました。愛好会の皆さんの愛が伝わりました」
みかんの選び方などみかんに興味がある方は、5・6年生の子どもたちに聞いてみてくださいね。
今朝は冷え込みましたね。でも朝日がとてもきれいでした。
そんな寒空ですが、運動場からは歓声が!何しているのかなとのぞいてみると1年生が生活科「ふゆとなかよし」の学習中です。今日は、自分でつくった風の力で動くおもちゃで遊んでいるところでした。

5年生は、算数。円柱と角柱の学習です。私の隣で教頭先生が学習シートをつくったり、授業の進め方を確認したり、押さえるポイントを確認したりして、いざ授業へ。
3年生も算数。小数の加減法。
間違えやすい問題を集中して解いていました。
2年生は、自作の詩を交流中です。
たんぽぽ学級は、算数にとても集中して取り組んでいました。
今日の給食は、鰯の生姜煮です。おいしく頂きました。
土曜日には、天P連主催の親睦ふらぼーるバレーボール大会が開催され、富岡小チームも参加してきました。
参加してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。筋肉痛はだいじょうかなあ♡
まずは、昨夜の「複式学級設立に伴う保護者説明会」にたくさんの保護者の皆様にご参加いただき、またたくさんのご意見をいただきました。まだ、いろんな可能性のもとにシュミレーションしている段階ですので未確定なところはありますが、少しでもご心配やご疑問が少なくなったら幸いです。何かありましたら、学校の方へご連絡ください。わたしも保護者の皆様と直接お話ができて、とても心強いお話などもいただき、嬉しく思いました。ありがとうございました。
さて、今日は、よかナビでもお知らせがあっていましたが、午前中から学校も断水でした。保護者の皆様もご心配があったのではないでしょうか?
ご相談したら、すぐに、教育委員会の皆さんが水を用意してくださいました。ありがとうございました。
タンクに生活用の水。
飲料水にも使える水の入ったポリタンク
そして備蓄用の飲料水用のペットボトルの水などとても配慮いただきありがとうございました。
用途に合わせて、子どもたちが苦労しないようなご配慮をとても感じました。
教職員で手分けして、手洗い場やトイレに運んだり、トイレの排水などは一部プールの水も使用しながら今日1日を過ごしました。ポリタンクから適量水を出すのを手分けして行ったり、タンクから水を分配したりしていたら、子どもたちもたくさん手伝ってくれました。子どもたちの成長も感じたところでした。そして作業している私たち職員へ「ありがとうございます」といえる富っ子、いい週末を迎えられそうです・・・。子どもたちも水が止まるという体験はないので、いろんなことを制約されたり、いつもは自由に行っていることがルールに則って行うなど多少の不便は感じたと思います。
また、6年生の子どもたちと話をしていると、「校長先生、水がないってとっても大変ですね」「災害の時って、こんな状況が何日も続くんですよね」「水の大切さを感じた一日でした」などと感想を話してくれました。さすが6年生だなあと感じたところでした。他の学年もたくさん感じたことがあると思います。
今日は、教育委員会の皆さん、そして役場の皆さんの学校を大切にしてくださる思いをとても感じました。いつもありがとうございました。いつも感謝しています。
あこうタイムの様子です。
昨日はまるつけ先生が来てくださり、1・2年生にたくさんの◎と満点シールをくださいました。
子どもたちもモチベーション高く、いつもとても意欲的に取り組んでくれます。ありがとうございます。
子どもたちとってもニコニコでした!丸つけ(赤ペン)先生の皆さんの温かい言葉掛けのおかげです。
いろんな皆さんに富岡小そして富っ子は支えられているなと強く感じた今週でした。
さて授業の様子は、3年生の図工の様子です。
金槌を使ってトンカントンカン♪釘を打って工作です。
ワニ、恐竜、ロボット、寿司屋さん、たこ焼き屋さん・・・イマジネーションすごいです。
ステキな工作を一緒にできて楽しかったです。
明日は天P連親睦ふらバールバレーボール大会です。出場される保護者の皆さん頑張ってください。
お互いけがには気を付けましょう♡
今日は長縄グランプリでした。
その様子を写真いっぱいでご紹介します。
昼休みも長縄で学年を越えて遊ぶ様子がとってもステキな富岡小の一日でした。
今日は立春ですね。温かい午後でした。
今日は終日不在でしたので、昨日の授業の様子です。
2年生は、タブレットを使って大きな数の学習です。10個集まったら....というふうに大きな位の数を考えていきます。
5年生は創作昔話作成中です。かぐや姫、北風と太陽、わらしべ長者などを自分なりにアレンジします。
4年生は社会科。地域の伝統工業について学びます。担任の先生方内田皿山焼に行って取材したインタビュー動画を見て、小代焼と比べながら考えていきます。担任の先生の準備が素晴らしいです。
3年生理科はものの重さの秘密を探ります。アルミニュウム箔の広げたままだったり、ちぎったり、丸めたりして重さがどう変わるか?
立春。出張に向かう道すがら、花も椿から梅に変わってきたなあ♡と思ったところでした。桃、菜の花、桜と季節は変わっていくんですね。
今日は節分ですね。字の通り節分とは「季節を分ける」ことも意味しているそうです。江戸時代以降は特に立春の前日を指す場合が多いそうです。今日の給食は節分メニュー。恵方巻き、節分豆でした。
職員室では、「いつの間にか日本の伝統的な行事になったなあ」「子どもの頃は豆まきだけしよった」など声が上がっていました。
そんな節分の日。1年生と6年生が交流です。心の鬼を紹介し、その鬼を追い出そう♡という趣旨です。
今日は体験入学です。新1年生を5年生が中心となってお出迎えします。よく考えれば、今の1年生をお迎えしたのが6年生。1年間の成長もとても感じました。
私の心の中の鬼は?
んん~悩み鬼かなあ。ずーっとああすればよかったかな?でもこんな方法もあったかなあ?と考えすぎてしまうこと。
皆さんは今日の節分、どんな心の鬼を追い出しますか?
2月に入りました。3年生教室では、先日書いていた書き初めの条幅が早速掲示してありました。「友だち」です。
先週末は、人権集会でしたが、「言葉」ってとても大切ですね。そう思いながら改めて保健室の掲示をみながら、学校全体としての更なる「心の教育の充実」が大切と感じたところでした。
早いものです。いよいよ師走ですね。1年教室、6年教室には節分に関する掲示がありました。
季節を感じる掲示、その中で自分も生活を改めよう!と振り返る機会となっていますね。ありがとうございます。
さて、金曜日の午前中に、木曜日に引き続き4名の方々に来ていただき、琴・尺八演奏感想と琴演奏体験です。
3年生は、私が会場の音楽室に行ったときに丁度、3年生の子どもたちが練習しているリコーダーの♬メリーさんの羊♬を琴・尺八と一緒に共演中でした。すばらしい!
もう一度最初から聞かせていただきました。すてきだなあ♪ 次年度もこの活動ができれば、こんな活動も!あんな活動も!・・・とワクワクしてきます。この機会を提供してくださった4名の講師の先生方のおかげです。ありがとうございます。
その後は体験活動です。「チューリップ」を体験です。
1・2年生も鑑賞の後は琴演奏体験です。「さいた♪さいた♪のところできた♡」など初めての体験も楽しんでいました。
5年生の体験の際は、すみません来客対応で授業に行けなかったので、写真が無くてすみません。
ちなみに、金曜日の給食はカツカレーでした。中学校は受験シーズンに突入しますね。その祈願もあるのかなと思います。
今日の給食は、これ。おいしくいただきました。
本年度の学校経営の大きなテーマは、「『~合い(愛)』を大切に!瞳キラキラ 心ぴかぴか な富っ子を育てる」です、児童会目標も「いろいろな『合い(愛)』を大切に!成長を喜び合える富っ子」とし、教職員・子どもたち、そして保護者・地域の皆さんの「チーム富小」で、「心の教育の充実」、特に「相手意識:思いやりの心」を大切に取り組んできた1年間です。
各学級でも、下のような学級の人権目標を設定して取り組んできています。3学期の人権集会は、その振り返りを発表しました。
全学年、しっかり取り組めて良くなってきたところ、課題として残っているところなどを学年の実態に合わせて発表してくれました。
6年生は、今学校全体で取り組んでいる学級力向上プロジェクトの結果とリンクさせて発表してくれました。
私は聞いていて、しっかり自分たちのことを分析しながら、できたところ、課題として残っているところを考えているなととても思いました。すべてがうまくいくわけではありません。そこで大切なのが振り返りながら、自分ごととして考えることだと思います。
学校全体でも1年間成果が上がったこともあれば、まだまだ課題として残ったこともあります。課題を洗い出し、悲しい思いをする富っ子が一人もいない富岡小をみんなで協力して作っていければと思います。
最後に、私の講話『ことばは「心」のまど』からです。
「皆さん、おはようございます。 今週は3学期の人権週間でした。人権週間は「人権」について考える大切な期間ですね。「人権」とは、一言で言うと「誰もが自分らしく、楽しく生きる権利」のことです。
今日の校長先生の話は、「人権」を大切にしていくために、とても大切な、皆さんが毎日使っている「言葉」についてお話しします。
皆さんは、友達に言葉をかけるとき、その言葉が相手の心にどう届くか想像していますか? これを「相手意識」と言います。
例えば、自分が言われて嬉しい言葉を、大切な人にプレゼントするような気持ちで届けてみてください。
反対に、自分が言われてチクチク痛い言葉は、相手の心も傷つけてしまいます。言葉は、投げたら戻ってこない矢のようなものです。口に出す前に一瞬だけ、「今の言葉、相手はどう思うかな?」と立ち止まって考えてみてほしいのです。
「丁寧な言葉遣いをしましょう」とよく言われることがあると思います。それは単に「正しい日本語」を使うためだけではありません。丁寧な言葉を使うことは、「目の前の相手を大切に思っていますよ」というサインを送ることだからです。「うざい」「きもい」といった乱暴な言葉は、せっかくの皆さんの素敵な心を、雲がかかったように隠してしまいます。丁寧な言葉を使うことで、皆さんの心の優しさが、相手にまっすぐ伝わるようになると校長先生は思います。
最後に一番大切なことを伝えます。 それは、「言葉はわたし自身である」ということです。皆さんが話す言葉は、誰が一番近くで聞いているでしょうか? それは、自分自身です。 優しい言葉を使っている人は、自分の心も優しく育てることができます。反対に、人を傷つける言葉ばかり使っていると、自分の心もトゲトゲして、悲しい気持ちになってしまいます。皆さんが使う言葉は、皆さんという人間を作っていく材料です。 「ありがとう」「すごいね」「大丈夫だよ」 そんな温かい言葉で、自分自身をそして富岡小いっぱいにしてほしいと思います。
「ことばは心のまど」です。友達に、そして自分自身に、温かい言葉のプレゼントを届けてみませんか? 一人一人の言葉が優しくなれば、この学校はもっともっと、みんなが自分らしく笑える場所になるはずです。
今日の午後と明日の午前中に全学年を対象に「和楽器の魅力 琴鑑賞&演奏体験」を実施します(した)。
富岡出身の琴奏者の蓑田様からお話をいただき、実現しました。今日は同じく琴を演奏される松下様、尺八奏者の緒方様、そして楽器をお貸しいただいた森様のお力もお借りし実現しました。
今日は4年生と6年生の体験です。
♪さくら♪を3つのバージョンで聴き比べ。そして季節の歌。子どもたちがよく知っているジブリメドレー。琴と十七弦琴そして尺八すてきな調べです。
子どもたちの待ちに待った♪さくら♪を親指に爪をつけて演奏体験。
担任の先生も一緒に体験。私も隣で体験させていただきました。楽しい〜〜♡
子どもたちも「初めてだったけど楽しかった」「もっと弾きたかった。来年が楽しみです」と感想を話してくれました。
6年生は「春の海」。お正月にお店に買い物に行った時にゆく流れていますね。今日解説を聴かせていただき、櫓を漕ぐ、大きい波、小さい波...イマジネーションは大切ですね。
6年生も楽しみながら演奏体験をしていました。
明日は1.2年生、3年生、5年生が体験します。
明日もよろしくお願いします。音楽を含めて文化に触れる素晴らしい機会、ありがとうございます。
今日の給食は、コッペパン、いちごジャム、シチュー、そしてクジラ竜田揚げです。昭和27年の給食だそうです。おいしくいただきました。
今は「鯨」って、特に天草ではなかなか食卓に上がらないですよね。硬いイメージがあったのですが、柔らかく、独特のニオイも抑えられとても美味でした。いろんな工夫をしてくださっているんだなあ。ありがとうございます。
さて、今日は6年生の理科の様子を紹介します。
小学校では、プログラミング教育が2020年度から導入されています。 現代社会では、コンピュータは魔法の箱ではなく、人が与える「プログラム」によって動く身近な道具となっています。子供たちが将来どのような職業に就くとしても、コンピュータ等の情報機器を主体的に活用して問題を解決していく力は不可欠です。
今日の理科では、スクラッチというアプリを使って、信号機の仕組みをプログラミングして動かせるように考える学習です。併せて、電気が生活の中でどう使われるかを学んでいきます。
6年生の授業の様子です。
今日もさすが6年生、難しい課題でもしっかり話し合いながら考えていました。
プログラミング教育には、3つのねらいがあります。
①「プログラミング的思考」を育むこと
②プログラムの働きやよさに気付くこと
③ 各教科等での学びをより確実なものにすること
しっかり学んだ1時間でした。次の理科でもプログラミング的思考を駆使して考えるそうです。
今日の給食は「はじまりの給食」です。塩鮭、栄養すいとん汁、漬物和えでした。
80年ぐらい前山形県で始まった給食。当時のメニューは、おにぎり、焼き魚(塩鮭)、漬物(菜の漬物)という質素な内容だったそうです。
今日は4年生の理科から。理科専科の先生からこんな授業しますと朝から教えていただいていたので、取材へGO!
今日は「もののあたたまり方」水がどんなふうに温まっていくのかを実験します。まずは柔軟剤を温めて「モヤモヤ」の動きを観察。そしてサーモインクといって温まると色が変わる特殊な液体で調べます。
みんな保護メガネをして、まるで科学者。しっかり科学していました。
今日は外国語活動の話題も少し。3年生は「What's this?」ひまわり、とんぼ、ちょう、コアラ.......いろんな名前をたくさん発話していました。
もう一つ4年生です。「Go Straight Turnleft.....」道案内の仕方をたくさん発話していました。私も一緒にしましたが、私だけ間違ってしまい......。
明日は6年生の理科の様子を紹介できたらと思います。
人権週間がスタートしました。キーワードは「相手意識」「ことばはわたし」です。
早速、保健室横の掲示板に保健室の先生が下の「いろいろな気持ち」と言う掲示とあわせて、子どもたちに啓発してくれています。
いつもありがとうございます。
さて、今日は寒かったですね。出勤の時マイナス2度。富岡小も着いた時には4度でした。子どもたちは元気です。
子どもたちの様子です。国語の学習です。「どうぶつのあかちゃん」についてしらべて文にまとめています。すてきな掲示も!!
2年生は生活について振り返って、学級での生活をさらに良くしていこうと話し合っていました。
5年生は、「聴き合う学び合う」学びについて「探究」の質を上げていくためにはと言う視点でよりよい学び方について思考していました。探究のプロセスは、文部科学省によれば「①課題の設定」「②情報の収集」「③整理・分析」「④まとめ・表現」の4つのステップで構成され、これらを反復・循環させることで問いの質を高める手法です。
3年生は算数。
問題を解くときのこの頭の近さ。一緒に思考しているってオーラがどんどん伝わってきます。
唐揚げです。苓北町児童生徒人気給食ランキング5位です。さすが5位、美味しい〜。あっ、いつも美味しいんですよ♡
お待たせしました。子どもたちからも保護者の皆さんからもリクエストがあったサッカーゴールの設置。昼休みはたくさんの子どもたちがサッカーや他の遊びで体を動かしていました。寒い1日ですが、あっぱれですね~。
24日から30日が全国的に給食記念集会です。苓北役場では子どもたちの作品が展示されています。是非観覧ください。
1年生が凧揚げをしていました。とっても楽しそう。みんなで運動場をいっぱい使って走っていくうちに凧がたかーくあがっていきます。
今日の給食はタンドリーチキン。職員室出は、「ところでタンドリーって何?」という会話が....。タンドールという窯で焼いたという意味だそうです。勉強になりました。
最後に、作業や掃除していると子どもたちが遠くから「校長先生ありがとございま〜す」といっぱい声をかけてくれます。とってもすてきな子どもたちだなーと手前味噌ながらいつも心がぽかぽかとなります。そういう子どもたちに育ててくださっている保護者の皆さんや先生方が更にすてきだなーといつも感謝しています。
1年生の皆さんが大きな数を探しに校長室に来てくれました。
カレンダーの数字、児童数の変化の数字・・・いっぱい大きな数字が学校にあります。
校長室の歴代の校長先生方の写真を見て、「46,47・・・・校長先生は48番目だ!」
「でもどうして写真がないの・・・?」「それは、・・・」
楽しい時間でした。
2年生は音楽の時間です。自分の名前に音符と音階を当てはめて作曲です。
「お」を二分音符にしたら・・・ まさに作曲家でした。
今日の給食は、かみかみゴボウ、もずくスープです。おいしく頂きました。
今日は、午前午後とも校外に出ていましたので、ショートバージョンです。
今日は寒かったですね。明日はすこしやわらぐ予定ですが、終末また寒気が入るようですね。
インフルエンザ等が流行している地域もあるようです。互いに気を付けていきましょう。
これが何だか分かりますか?
こっぱもちです。先日3年生と6年生が総合的な学習の時間の一環として「こっぱもち」の「こっぱ」づくりをマリン校舎の皆さんの指導で行いました。
そのこっぱを使って「こっぱもち」を作成されたということで、3年生教室と6年生教室に贈呈に来ていただきました。3年生教室での様子です。小高連携の最先端と言われています。ありがとうございます。今日、3年生・6年生は持って帰ると思います。おいしくお召し上がりください。
今日の給食は、「今日は世界の料理 スペイン編」です。もう気分はバルセロナです。
オムレツ、シーザーサラダ、スープはソポ・デ・アホ(カスティーリャ地方の伝統的なスープだそうです.
職員室では、かき玉汁と思ってました・・・という人も・・・)です。スペイン語で「おいしい」は「rico(リコ)」「bueno(ブエノ)」ですね。今日の給食もブエノいただきました。
さて今日は給食集会です。
給食委員会の皆さんが、「バランスよく給食を食べることの大切さ」について寸劇で発表してくれました。
食品の三要素ですね。緑・赤・黄色(献立表を見ると分かりやすいです)
好き嫌いしてバランスよく食べないといろんな困ることが・・・
緑・赤・黄色の食品のよさを説明してくれました。
とっても分かりやすく、そして興味を引きつける発表ありがとうございました。
給食調理場から栄養教諭にも来ていただき、お話をしていただきました。
①和食の大切さ ②ミートスパゲッティができるまで ③調理場の皆さんの思いについて、動画も交えながらお話しくださいました。
子どもたちの感謝のお手紙をお渡ししました。
最後に私からです。「感謝の気持ちをもって生活しましょう」
富岡小では、1月19日から1月23日が、給食記念週間でした。給食記念週間は、今から70年ぐらい前に学校での給食が始まったことを記念して設けられている週間です。今では当たり前のようにいろいろな食べ物を誰もが食べることができていますが、そのころの日本は戦争が終了したばかりでなかなか食べる物が手に入らない時代でした。育ち盛りの子どもたちに少しでも栄養のあるものも提供したいと考えられたのが現在の給食です。
昨年、香港から来た富小にインターンの一環として大学生も6年生と会食をしながら、給食の素晴らしさを感想で話されていました。
さて、皆さんは、好きな給食は何ですか?校長先生はカレーライス、フルーツポンチ、牛乳、メンチカツの組み合わせが今までの給食で最高に好きでした。好きな物も嫌いな物もありますよね。でも、バランスが取れたいろんな種類の食べ物を食べられるということが給食のいいところだと思います。ちなみに校長先生はきゅうりが嫌いです。きゅうりって給食によく出ますよね。でも毎日残さずニコニコ笑顔で食べています。
その給食はいろんな人たちの思いや努力の上に作られています。食べる物を生産してくれていたり、食べ物を運んでくれたり、調理をしてくれていたりする人たちがいます。その人たちに感謝をして給食をいただくにしましょう。校長先生は、苓北の給食はレタスやオクラなど苓北や天草のものをたくさん使ってあります。皆さんが給食で食べている米も地域の方が子どもたちのためにと一生懸命つくられた苓北産の米を使っているそうです。調理場のみなさんは、おいしくてバランスの取れた、給食を提供するために、相談をしながら、1つ1つの食品を安全かどうか確かめながら給食を作ってくださっています。
富岡小学校の周りには、農業をしていらっしゃる方、魚をとっている方や育てている方々など食糧を作っている方々がたくさんいます。気持ちを込めて作ったり、とったりしたものを新鮮なうちに給食としていただける恵まれた環境にあります。大きな感謝の気持ちをもって給食をこれからも食べていってほしいと思います。
今日の給食は、中華三昧。麻婆豆腐、餃子、棒々鶏です。おいしくいただきました。
今日は、4年生の道徳を参観させていただきました。
テーマは「ともだちのために」で友情・信頼について考えました。
まずは、「友だちとはどんな人?」というアンケートから「やさしい」「頼れる」「助ける」「大切」などがあがっていました。
では「友情とは?」
「助け合う」「わかり合う」「なかよし」「協力し合える」「支え合う」・・・・いい言葉ですね。
「~合う」ってことがキーワードですね。
さて、内容に入っていきます。今日考える話のストーリーは「なかよしの転校していった友だちから絵はがきが届いた。絵はがきが大きくて貼ってある切手では不足して若干の支払いが・・・」という内容です。
仲のよい友だちにこのことを「伝える」「伝えない」ということを考えながら、友情と信頼について考えていきます。
まずは、自分の考えのポジションニング
「どうしてそう考えたかが大切なんですよね」そして、それを交流しながらいろんな考えに触れ、自分の考えを深めていくことが大切ですね。
グループで意見交流です。
そしてみんなで交流して、更に考えを深めます。
「自分が登場人物のシュツエーションだったらどうしただろう?」と考えてしましました。
「言わないかなあ・・・」「でも友だちのためなら気分を害しない程度にうまくはなすかな・・・」
そういう心の葛藤が大切なんですよね。
よく学んでいた4年生でした。
4年生の皆さん、3学期は高学年5年生になるための0学期です。
どんどん個性を表出させ、どんどん伸びていきましょう。応援しています。
今日の給食はふるさとくまさんデー苓北町の味です。
麦ごはん、照り焼きチキン、レタススープ、いんげんの胡麻和え、ポンカンです。お米、レタス、ポンカン....苓北町の食材いっぱいです。美味しく頂きました。
18日は富岡地区どんどやでした。17日にはその準備です。以前は子ども育成会を中心に行なっていた地域の行事なのですが、コロナ禍で中断し、地域の有志の皆さんが実行委員会を立ち上げ今年から開催されました。地域のためにと微力ながら子ども育成会と学校も後援させていただいています。準備には教育長先生も手伝いに来てくださいました。
事前の協議で風など十分に配慮して実行するという共通理解をしての開催です。朝、少し早めに来るとたくさんのしめ縄などの正月飾りがすでに入れてありました。風も早朝は少し強くて心配していたのですが、予報通り微風に。
開式の前にいらっしゃった地域の皆さん、参加した子どもたちと写真撮影です。トータル300人弱の方が参加されました。
6年生の代表が点火。
高く燃え上がりました。「鬼火焼き」は、正月飾りに宿った「鬼(悪霊)」を追い払い、火にあたって餅を焼いて食べ、新年の「無病息災・家内安全・五穀豊穣」などを祈願する意味があります。炎と煙、そして竹の破裂音で厄を払い清める、厄払いの意味もあるそうです。特に天草では、1年間しめ縄を飾る歴史的な慣習があり、そのしめ縄を燃やして厄払いする風習がとても残っていますね。
老人会の皆さんが餅焼き網の作成を子どもたちに教えてくださいました。
子ども育成会の皆さんは餅をアルミ箔で包んで準備してくださいました。
女性の会の皆さんは豚汁を200人分用意してくださり美味で美味しく頂きました。
消防団の方々も火の見守りをずっとしてくださっていました。とても安心しました。
地域おこし協力隊員の皆さんも片付けまで協力してくださいました。
火がおきになったら餅焼きタイム。焼き上がった餅も美味しく頂きました。
みんな笑顔です。
何世代にわたる皆さんが一堂に集まるすてきな機会だなあと感じたところでした。
私自身も以前勤務した時にお世話になった皆さんにたくさんお会いでき、またこの機会にたくさんの皆さんと知り合いになれ、保護者の皆さん、子どもたちとも話ができ楽しませていただきました。
ご協力ご支援いただいた皆様ありがとうございました。
昨日の雨で空気も澄んで朝の正門もきれいでした。
今日もぽかぽか、作業日和です。作業しているとたくさんの子どもたちが「校長先生 ありがとうございます、さようなら」と大きい声で言って子どもたちが帰っていきました。
その気持ちだけでも心もぽかぽかになりました。校舎も富岡城もきれいな1日でした。
さて、企画委員会から書き損じはがきを集めるというお知らせです。
このように委員会からのお知らせや取組が期間にあわせて掲示してあります。
図書委員からは往復はがきキャンペーンのお知らせです。
図書室には「本が好きになる」ような掲示がいっぱいです。
ちょうど1年生が本を選んで、読書だいすき往復はがきを書いているところでした。
たくさん本を読んでほしいなあ。取組に感謝です。
6年生の教室横には冬休みの宿題「家族のために作った料理」の掲示がありました。おいしそうな多国籍な料理がいっぱいです。おいしそうな写真も感想もすてきでした。
たんぽぽ学級ではとっても集中して算数に取り組んでいました。
3年生は道徳の授業、個性のよさを認め合う内容でした。いい個性をもっている3年生の皆さんですね。
今日の給食はひじきご飯に豚汁。ひじきご飯美味でした。美味しく頂きました。
今日の給食は、ハヤシナゲットライスです。
フルーツポンチでした。おいしくいただきました。
1年生は、体育で縄跳びの練習中です。
まずは単縄跳びです。
長縄チャレンジ。タイミングをまわす先生たちに教えてもらいながら、少しずつ慣れてきていたようです。
5年生の図工の「美しく立つ針金」の作品です。明日も図工があるので、明日完成に向けて取り組んでいくみたいです。
何をイメージして作成されたのかは、想像してみてください。
鑑賞側もイメージネーションが大切ですね。
午前は、春一番かなと思うほどの温かい風、午後は一転して風雨となりましたね。びっくりする天気でした。
椿の季節ですね。
今日の給食は「揚げパン」でした。給食調理場の方々が、丁寧に1つ1つコッペパンを揚げ、きな粉砂糖をまぶしてくださったんだと思うとより一層おいしく感じます。とても愛情を感じます。子どもたちも楽しみにしているようでした。
大人になって思うんですが、給食の「揚げパン」ってどんな食べ方が正解なんだろう?
箸でつかんでかぶりつく?ティッシュなどに包んで手でちぎりながら?フォークとナイフで?・・・・・子どもの頃をそんなの考えずにおいしく食べてたなあ?今もおいしくいただいていますけど。
さて、5年生の図工の様子です。「美しく立つ針金」という題材です。アルミニウムの針金をラジオペンチなどを使って曲げたり、丸めたり、絡めたりしながら想像力を広げ、自分らしいおもしろさや美しさを見つけながら立体をつくっていく時間です。5年生の皆さん、悪戦苦闘しながらも楽しんで作成していました。
1年生の廊下には「冬休みの思い出」の絵日記が掲示してあります。
それぞれ思い思いの冬休みの思い出!充実した冬休みだったようですね。
4年生は、算数の学習。表を使って分類していく学習です。
今日は、午後からぽかぽかしたいい天気にありましたね。今週は、晴れが続くようです。
作業日和です・・・・・。
学校のホールの掲示板には、教務の先生が3学期にチーム富岡小で取り組むことが掲示してあります。
この3学期を充実した令和8年度の0学期にしていくために「心を一つ」取り組んでいきます。
さて、各学年の授業も平常運転です。
1年生は算数の時間。「26」の表記の仕方と数字の概念について学習中です。
ペアで考えながら、しっかり学びを深めていました。
2年生は、国語の時間。
回文などの日本語の面白さを学習中です。
3年生も国語の時間。昨日某N〇Kの番組で家族の歴史を深掘りする番組があっていました。
その番組でも紹介された和田誠さんの詩を読んでいました。
和田誠さんの絵本は私も何冊か持っています。「ともだち」という絵本は人権集会などでも引用させていただいています。
4年生も国語の時間。冬の感じたことをカルタにしてカルタ対戦中で盛り上がっていました。
5年生は算数の時間です。後方では振り返り。中程では友だちと一緒に、前方では先生と一緒に問題に挑戦中でした。
6年生は、外国語の学習です。ペアで楽しそうに活動していました。
今日の給食は、これです。焼きししゃも、肉じゃが、キャベツとちくわの和え物です。おいしくいただきました。
最後に学校通信です。詳しくご覧になりたい方は、下をクリックください。
「地域とともにある学校」という言葉がよく使われます。
地域の皆様の教育力は大事な財産でもあると思っています。本校では、地域学校協働活動推進員の方にコーディネートしていただいて、地域の皆さんにいろんな場面で支援していただいています。これは、子どもたちにも「体験」という面でも「富岡を見て、富岡を愛す」という面からも大切なことです。
1月18日に富岡地区では区長会を中心とした有志の皆さんが中心となって「富岡地区どんどや(鬼火焼き)」を計画していらっしゃいます。子ども育成会も学校も「地域のために」という視点で微力ながら協力をさせていただいています。その一環として、たき付け用の松葉拾いをクリーンタイムを使って行いました。
大きな袋 20袋分みんなで集めました。こんなにきれいになりました。
17日の準備は希望した子どもたちと婦人会の皆さんが豚汁の野菜きりなどを計画されています。
18日はもち焼きの道具を老連会の皆さんが参加した子どもたちに指導してくださるそうです。
よき交流の場となればと願っています。
さて、昨日・今日の子どもたちの様子です。
1年生は冬休みの思い出にそれぞれコメントを書いて感想交流をしていました。
2年生は、始業式の3学期に頑張ることを使って、2年生で頑張ることを話し合っていました。
5年生は、自己紹介タイムでした。
さて、昨日の始業式で3学期頑張ることを先生方と子どもたちで共有する時間を取りました。簡潔に説明します。
「なかよしの花:心(Heart)プロジェクト」です。
〇テーマは『「気付き合い・思い合い」~ことばはわたし~』です。
①自分の名前も 相手の名前も大切にしよう。
『さん、くん』をつけて名前を呼ぼう!
②言葉を大切にしよう。 考えてから言おう!その言葉言われて嬉しい言葉かな?
③「返事」と「反応」は『あなたのことを大切に思っているよ』のメッセージ
【がんばりの花 学(Head)プロジェクト】です。
〇テーマは『「高め合い」~自分も友だちも学びの主人公~』です。
①「わからない」は学びの種 レベルアップのチャンス
②「違い」を大切にして、いろいろな考えに出会おう。
【元気の花 健(Health)プロジェクト】
〇テーマは『心も体も「きたえ合い」』です。
①運動する意味!それは・・・
集中力アップ! 免疫力アップ! 筋力アップ! 心も体も元気に!
②毎日合計60分以上運動しよう
③縄跳び、鬼ごっこ、ボール遊び・・・徒歩での登校も大事な運動
チーム富岡小で3学期を充実したものとなるよう取り組んでいきます。
最後に、本校にとっての2026年初めての給食は
紅白なます、いわし?さんま?の梅煮、白玉雑煮という縁起のいい給食でした。
季節を感じます。給食調理場の皆様2026年もおいしい給食よろしくお願いします。
おいしくいただきました。
今日も長めのUPになってしまいました。長いと「いいね」が伸びないんですよね。
「いいね」もちょーーーと励みになりますので、ボタンのプッシュをお願いします。
あけましておめでとうございます。令和8年もよろしくお願いします。
今日から3学期のスタートです。学校では始業式を行い、3学期のスタートを切りました。
転入も2人あり、令和7年度3学期は児童数71人でのスタートです。
学級では、担任の先生方の温かいメッセージが子どもたちをお迎えです。
手前味噌ですが、先生たちの子どもたちを温かく見つめる視線を感じるようで、朝早い寒ーい教室ですが、心が温かくなりました。先生方!いつもありがとうごございます。
保健室横廊下の掲示板もリニューアルです。「けんこうおみくじ」子どもたちが興味関心を、そして季節や行事を感じるようにいつも工夫されています。ありがとうございます。ちなみに私は「大吉」でした。
音楽室の後方では、卒業式に向けたサイネリアがすくすく育っています。学校主事の先生を中心に細心の注意を図りながら育成してくださっています。ありがとうございます。
さて、今日は始業式でした。
私からは、こんな話を始業式で行いました。
「新しい年を迎えました。それぞれ新しい1年間を迎え、2026年はこんなことをがんばろうという抱負を皆さん持っていることと思います。その抱負を大切にしてほしいと思います。3学期は、50日間と1番短い学期ですが、これまでの1・2学期の学びや体験をまとめる大事な学期であり、同時に、みなさん一人一人の心に残る思い出をたくさんつくる学期でもあります。
今年は干支でいうと「うま年」ですね。「うま」という漢字は、「馬」という漢字ともう一つ「午」という漢字があります。「午前・午後」を使うとき使いますよね。昔の時刻の呼び方に「午(うま)の刻」という言葉があります。午の刻は、ちょうど一日の真ん中。今でいうとお昼の12時にあたります。午の刻は、昔は「物事を見直し、整え、次へ向かう大切な時間」を表していると言われていました。今のみなさんも、まさに「午の刻」です。
この3学期、これまでの自分を見直し、整え、振り返りながら伸ばす大事な時間です。
「自分がすべきことをしっかりできたかな」「しっかり聴き合い、学び合えたかな」「自分は周りの友達にとって,どんな友だちだったかな」「困っている人に声をかけられたかな」「自分の挨拶や言葉遣いはどうだったかな」
そんなことを考える、大切な時期です。学校は、みんなでつくる場所です。
2学期の終業式でも話しましたが、いじめは、絶対に許されません。いじめをしないだけでなく、見て見ぬふりをしない。これは、皆さんもう分かっていますよね。
それができる仲間が集まった学校は、とても強い学級であり、とても強い学校です。
この3学期、皆さんに2つのことを意識して過ごしてほしいと思っています。
1つ目は、思いやりです。あいさつ、声かけもそうですが、校長先生は「言葉を選び、友だちを大切にすること」をみんながもっと考えてほしいと思っています。そうするともっともっとみんなが過ごしやすい学校になると思っています。
2つ目は、学びの充実です。先日、お客さんがいらっしゃって「努力を楽しみ、向上を喜ぶ」という富小スピリットをご覧になり、ステキな言葉ですねと言ってくださいました。聴き合い、学び合いながら、しっかり自分で一つ一つ成し遂げていくことが大切ですね。
そのためにも、今年は、午年だけに「うまくいく」一年になるように・・・・自分で頑張りながらも、自分だけが走るのではなく、友だちと歩調を合わせて進む。そうすれば、それぞれのステキなゴールは必ず見えてきます。そう思える毎日を、みんなでつくっていきましょう。」
3学期の私たち教職員、子どもたち双方で頑張っていく取組の共有の時間を行いました。
その内容は、明日のHPでご紹介しますね。
今日は、寒くなるかと思いきや少しぽかぽかした晴れ日。いい3学期のスタートになったようです。
2学期も今日で終わりとなりました。感染症が流行するのではないかと心配もありましたが、2学期の終業式を迎えられました。
これも、いつも学校教育にとてもご理解とご支援をいただいている、保護者の皆さんそして地域の皆様のおかげです。
子どもたちもとても成長した2学期であったと思います。また、その陰にある先生方の真摯な取組の成果と思っています(手前味噌ですが・・・)。
各学級の代表の子どもたちの振り返りも自分を振り返ってすばらしい発表をしてくれました。
漢字計算大会を頑張ったこと、持久走大会を自分の目標目指して練習から頑張ったこと、持久走大会でたくさん保護者や地域の皆さんの声援で頑張れたこと、学び合いの中で考えの違いに気を付けて考えられたこと、JFA夢の教室の講師の方の話を聞いて、自分も頑張りたいと思ったこと、学習発表会に協力して、いい発表ができたこと、図工の版画を集中して頑張ったこと、陸上記録会で自己新記録を出せたこと、修学旅行で平和の尊さをしっかり考えたこと、苓北支援学校との交流を相手意識を大切にして取り組んだこと・・・・・・たくさんの学びが子どもたちの成長につながったと思いました。
生活担当の先生から次のような話がありました。
〇トイレのスリッパがよく並ぶようになって、細かいことにも気づける富っ子になってきたんだなとステキに思ったこと
〇言葉の遣い方は自分を表している・・・意識していきましょう。
〇冬休みの生活について「夕方5時には家に帰り着いておくようにしましょう」「交通量も多くなってくる季節、交通安全には十分気を付けましょう」「あいさつは、学校で出来ていることを地域にも広げられたらステキですね」
次に、保健の先生からは「ふ」「ゆ」「や」「す」「み」を「あいうえお作文」にして次のような話がありました。
「ふ」・・・・ふとりすぎ 食べ過ぎ注意 運動しよう
「ゆ」・・・油断しないで 続けよう 感染症対策
「や」・・・やりすぎに 注意してね テレビ・ゲーム
「す」・・・すいみんは しっかりとって 早寝早起き
「み」・・・磨こうよ 食べたらすぐに 自分の歯
少し、昨日の学習の様子を紹介しますね。昨日紹介できませんでしたので・・・・・♪
1年生はタブレットを使ってe-ライブラリーに挑戦中です。

2年生は、収穫祭で大根の味噌汁を作成中です。
5年生は、体育でベースボール型ゲームをエンジョイ中です。
6年生は、版画で集中して彫り♪彫り♪中です。
最後に、終業式で私が話した内容です。
「おはようございます。今日は12月24日、クリスマスイブですね。2学期は、78日間ありました。暑かった8月29日の2学期のスタートから78日間いろんな学びや体験ができた2学期だったと思います。1番2学期の暑い日で37.3度ありました。季節が変わって今日はもう冬ですね。
少し2学期を振り返ってみましょう。10月には6年生修学旅行、敬老ふれあい会、JFA夢の教室、5・6年生の陸上記録会、5年生の水俣に学ぶ肥後っ子教室たくさんの行事がありましたね。11月には、5,6年生が出場した音楽会もありましたね。また、皆さんが堂々と発表した学習成果発表会、12月には皆さんがんばった校内持久走大会がありました。2学期の学びや、体験を通して、「自分 のよさ」「友だちのよさ」「学校のよさ」「富岡のよさ」をたくさん感じたと思います。
さて、校長室の前の廊下に「日々是進(にちにちこれすすむ)」という額があります。昔の文部大臣の中村梅吉さんという方が書いた直筆の書です。私もそうですが、毎日の生活の中で目に見えていいこと、成長したと感じることばかりではありませんよね。「ああ~やってしまった」「失敗したなあ」と感じることも多いですね。その時「次は、こうしよう」「こうすればよかったなあ」と自分を省みたり、次の行動につなげられれば前に進んだことと一緒ですよね。「失敗することも前に進むこと」と思います。
2学期の始業式で、3つの大切にしてほしいことという内容で話をしました。少し振り返ってみたいと思います。その3つは、 1つ目は「言葉の使い方」、2つ目は、「あいさつ」、3つ目は、「字を丁寧に」でした。
1つ目の「言葉の使い方」2つ目の「あいさつ」はどちらも「相手意識」 に関わります。2学期も「~合う」「~合い」を大切にして、活動を充実させてきましたね。「相手意識」って、人権に関することと思っています。人権とは、「一人一人が大切にされること」です。
「~合い」「~合う」ということを大切にするということは、「ことば」を大切にすることです。「友だちと話すときの言葉」「何かに書いて伝える言葉」ひょっとしたらスマートフォンやタブレットで見たり使ったりする「言葉」・・・・皆さんmも分かっていると思いますが、言葉は、相手の心を励ましたり、 相手の心を温かくする不思議な力を持っています。逆に、言葉は相手の気持ちを冷たくしたりする力も持っています。だから、言葉って大切に使っていかなくてはいけないんですよね。
みなさん、「相田みつを」さんという書家で詩人の方を知っていますか。
相田みつをさんの詩に「自分の番 いのちのバトン」という詩があります。
自分が生まれるまでに父と母で2人、父と母の両親で4人、そのまた両親で8人・・・数えていくと10代前では1024人、20代前では100万人を超すそうです。こんなふうに命のバトンを受け継いで今、自分の番を生きています。
そんな大切な皆さんですから、自分もそして友だちも、家族も地域の人も同じように大切にしてほしいと思っています。だからこそ、皆さんも分かっていると思いますが、「いじめはどんな理由があってもゆるされない」んですよね。
14日間の冬休みに入ります。そして、1月1日には令和8年となりますね。これまでの自分の成長や友だちやまわりの支えてくれた人に感謝の気持ちを大切にこの14日を過ごしてほしいと思います。「ありがとう」の気持ちを大切にしながら、冬休みを楽しんで、そして健康に過ごしてください。」
2学期、保護者の皆さん、地域の皆様には大変お世話になりました。
年の暮 いい年をお迎えください。
2026年 午年もよろしくお願いします。
今日の給食は、チキンライス、フィレオチキン、レタスのコンソメスープ、カラフルサラダ、クリスマスケーキです。
気分はもうクリスマスですね。子どもたちもクリスマスのプレゼントを楽しみにしていますね。
「校長先生、サンタさんに〇〇もらいます」など話かけてくれます。
今日のクリスマスケーキも楽しみにしているようです。セレクトなんですよ。チョコか、イチゴか。
私は、ずっーと自分はチーズと思っていて、そう家族に話したのですが、選択にありませんでした。とんだ記憶違いでした・・・トホホ・・・
さて、昨日はたんぽぽ学級の皆さんからおでんパーティでつくったおでんをいただきました。
自立活動の時間や生活科・総合的な学習の時間などの時間を使って、たんぽぽ農園に大根やほうれん草を植えて、収穫です。
その収穫した大根を使っておでんづくりです。
計画表に沿って、子どもたちと先生方で仕事を分担しながらつくったそうです。
このおでんがちょー美味でした。
大根もほろほろにとけるぐらいやわらかく、味がよく染み渡っていました。
天草弁で言う「よー、しょんどる」状態です。
いつも二人とも気軽に話しかえてくれるので、私もいつも心が温かくなります。昨日はおでんで更に暖かくなりました。おいしく頂きました。
昨日の午後の様子です。風が冷たくて強い中、3・4年生が分かれて体育中です。
3年生元気いっぱいにキックベース中でした。とーっても楽しそうです。
12月19日(金)学校通信海の声R7年度12号を配付しました。掲載させていただきます。
すみません。地区の配付棚の締め切りの関係で早めに配付させていただいています。
詳しくご覧頂きたい方は、こちらをご覧ください。
今日は冬至です。今日の給食は冬至にちなんだメニューです。
さけの塩焼き、ほうれん草の柚子あえ、かぼちゃのそぼろにです。冬至にかぼちゃを食べて、ゆず湯に入る日本の伝統的な風習があります。冬至は、1年で最も昼が短いので、これから日が延びていくことを運気が上昇することととらえて、無病息災を願って、かぼちゃを食べて栄養補給を行い、ゆず湯に入って血行促進やリラックス効果で元気いっぱい冬を乗り切ろうということだそうです。給食はとっても季節を感じます。ありがとうございます。
さて、今日は先週の様子からお知らせします。
5年生は学級力向上プロジェクトの二学期の取り組みの反省中でした。自分たちで自分たちの生活を振り返り、自分たちで向上する道筋まで考えようという取り組みです。ネクストリーダーの5年生の皆さん期待しています。
先週は3〜6年で毛筆指導が行われました。
また、各学年で版画の指導も佳境です。版画の先生にお手伝いいただきながら、集中して彫り進めます。写真は木曜日の4年生の様子です。
1年生は図工で思い思いに箱をデコって作品づくりです。
文化展の表彰のあとに職員室でアドバイスをいただいた先生にお礼を言いに来てくれた4年生。すてきです。
昨夜はオリオン座と冬の大三角がとても綺麗でした。是非夜空も見上げてみてください。冬の大三角は、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオン、オリオン座のベテルギウスの3つの1等星をつないでできる三角形のことです。
今日は、2年生の皆さんが、1年生と保育園の皆さんを招いての一緒に生活科の学習につくった手作りゲームで遊びます。
1年生の皆さんと保育園の皆さんが楽しんでくれるように、一生懸命準備を頑張っていました。
最後の準備の様子です。私も少し先に体験させていただきましたが、よく考えて作ってありました。
相手意識をとても大切にした準備が整っていました。
黒板は、ウェルカムボードに変身です。お迎えの準備はばっちりです。
さあ、ゲームタイムです。迷路、クレーンゲーム、魚釣りゲーム、
風の力を使ったゲーム、射的・・・・
風・磁石・ゴムなど3年生の理科で学ぶことをゲームと言う形で先取りしながらよく考えられたゲームです。
1年生の皆さんも保育園の皆さんもとっても楽しい歓声と笑顔いっぱいでした。
2年生の皆さんありがとうございました。
今日の給食はこれです。おひめさまだごじる。美味しく頂きました。
そうそう、給食の牛乳の消費期限が2026年1月1日となっていました。年の瀬が近づいてきたなあと感慨にふけってしまいました♡
今朝は、表彰集会でした。
天草郡市文化展・特別支援学級作品展、漢字・計算・タイピング大会、全国国土緑化・育樹ポスターコンクール、天草郡市音楽会の表彰です。
まずは、天草郡市文化展・特別支援学級作品展の表彰です。
描画の部、科学発明の部、特別支援学級作品展の部それぞれ、天草教育会館にも展示されていましたが、とても素晴らしい作品でした。おめでとうございます。
次は、全国国土緑化・育樹ポスターコンクールです。
とてもたくさんの作品が優賞・良賞をいただきました。自分が書いた絵が印刷された賞状で、とっても記念になりますね。おめでとうございます。
2学期の漢字計算タイピング大会です。満点賞、努力賞、躍進賞、合格で賞とありますが、それぞれの子どもたちがとても頑張っていました。「努力を楽しみ、向上を喜ぶ」富岡小スピリットそのままです。素晴らしいです。天草郡市音楽会も5・6年生がむずかしい曲でしたが、しっかり歌いきり、ステキなハーモニーを会場に響かせてくれました。
さて、4年生では総合的な学習の時間に郷土学習を取り入れています。
先日は、地域学校協働活動推進員の方にじゃっと祭やペーロン大会について、地域の歴史に詳しい方にも来ていただき、富岡城の秘密というテーマで話をしていただきました。
いつもご協力ありがとうございます。富岡のことを知ることは、富岡の人を好きになる、富岡のことを好きになるにつながると思っています。
さて、今日に給食は鰯にみかん。健康的な給食、おいしく頂きました。
今日は、火災避難訓練でした。
天草広域連合苓北分署から3名の方に来ていただき、避難訓練です。
避難のその直前に、雨雲が・・・。急遽、体育館での実施としました。
苓北分署の方のお話や教頭先生・防災担当の先生からの話の中にもありましたが、以下のことが大切ですね。
訓練でやったことが、万が一の時に皆さんの命を守ります。そのために、今日の訓練を単なる練習で終わらせず、常に心に留めておいてほしい4つの原則があります。
キーワードは「おはしも」です。
お・・・おさない
は・・・はしらない
し・・・しゃべらない
も・・・もどらない
この「おはしも」は、避難時に皆さんが安全かつ迅速に行動するための、最も大切なルールです。
災害はいつ起こるかわかりません。しかし、もし起こっても、今日学んだことを思い出して、慌てずに「おはしも」をしっかり守って行動すれば、必ず命を守ることができます。
自分の命は自分で守る。そして、周りの人の安全にも気を配る。その意識を、今日の訓練で改めて強く持ちましょう。
火災避難訓練の様子です。
水消火器を使って、消火の練習も行いました。
今日の給食は、これです。おいしくいただきました。
今日は、3年生、6年生が天草拓心高校マリン校舎のみなさんと「こっぱづくり」体験です。
マリン校舎の魅力化発信ということで、年間通して、そして長年、小高連携をしている富岡小に「一緒にどうですか?」とお声かけいただきました。
目的は、「天草伝統食品、こっぱもちを試作し、地元食文化・歴史を考える機会とする」です。
朝の登校の時から、3年生の児童が「校長先生、今日はこっぱもちづくりです」と話してくれ、とても楽しみにしているようでした。
まずは、いきなり団子作りからスタートです。熊本で団子と言えば「いきなり団子」ですね。
蒸す間に、こっぱの作成からスタート。
子どもの頃こっぱづくりよくされていましたね。〇十年前になりますね・・・。
そのころ、登校の時も軒先によく干してあったのを思い出しました。
皮をむいて
切って、
穴を開けて
テレビ局や役場広報の方々の取材も来ていました。
高校生の皆さん、マリン校舎の先生方が優しく教えてくださいました。
わらに通します。
次は蒸します。
いきなり団子もできあがり、
おいしくいただきました。
昔懐かしい、こっぱづくり、教えてもらいながらも楽しくできました。
干す作業が残っています。学校でも、いくつかつるさせてもらおうと思っています。
今日の給食は、ゴボウサラダ、おでん、なっとう。おいしくいただきました。
おでんに、うずらのたまごが・・・・・って、教室はなるんでしょうね。と思いながら食べたところでした。
朝日がとても綺麗な朝でした。子どもたちを裏門でお迎えするちょっとした間に大手門でパチリ。富岡ってすてきです。
今日の給食はこれ。サラダに入っているシラスがいいアクセントです。あとは野菜コロッケです。美味しく頂きました。
昨日は苓北町教育委員会主催の教育講演会がありました。
これからの教育の在り方、苓北町のすてき、小規模校での学びのヒントなどたくさんの学びをいただきました。
講師は苓北町出身で、文部科学小教科調査官、東京学芸大学の登本洋子先生でした。富岡小にもちょっとよっていただき、富岡の地域素材をどう教育の中に活用したらよいのか、体験学習のよさなどヒントをいただきました。
今日はたくさんの応援ありがとうございました。天気を心配していましたが、無事開催できました。子どもたちの様子です。
開会式
開会式で、こんな話をしました。
「今日は、楽しみにしていた持久走大会です。
今朝、6年生のある人と話していたんですが、とてもうれしくなりました。ちょっと紹介しますね。
「校長先生、おはようございます。今日は頑張ります。一番じゃなく、自分の目的を達成できるように頑張るのが今日の目標です。歩かないで最後まで頑張ります。」
持久走は、速さだけでなく、あきらめずに走りきる気持ちが何より大切です。苦しくなる場面もあると思いますが、そんな時こそ、応援してくれる友達や先生、おうちの人の声が力になります。周りへの“感謝”の気持ちを胸に、一歩一歩前へ進んでください。
走り終えたあと、みなさんの「やりきった!」という顔を見るのが楽しみです。
今日は安全に気をつけて、自分のベストを尽くしましょう。応援しています。
最後に、今日も皆さんのために春の迫地区の皆さんが、道路の清掃をしてくださいました。そのことも感謝の気持ちを大切にしながら頑張ってください。」
低学年の走りの様子です。
中学年の様子です。
高学年の様子です。
PTA役員の皆様、運営のお手伝いありがとうございました。
皆様の協力があって今日の大会ができました。
応援にたくさん来ていただいた地域の皆様、保護者の皆様、たくさんの応援が子どもたちの力になりました。ありがとうございました。
閉会式
最後に冒頭の校長の話でも触れましたが、本日もそして子どもが試走で走る日には毎回春の迫の有志の方々が子どもたちが走りやすいように道路環境を整えてくださいました。ありがとうございました。
今日の給食はカレーライス。美味しく頂きました。
今日の朝日ちょっと神秘的でした。朝の交通指導の時にパチリ♪
下の2枚の写真から連想される物語は何でしょう?
今、1年生は国語で「たぬきの糸車」の学習です。保護者の皆さんには音読で大変お世話になっています。
3年生は、「3年峠」です。韓国の昔話です。
一人のおじいさんが 三年とうげで 転んでしまいました。
「三年しか生きられぬのじゃあ。」となくおじいさんは、ごはんも食べずにふとんにもぐりこみ、病気になりました。
ある日、水車屋のトルトリが 三年とうげで もう一度転ぶことを ていあんしました。
「一度転ぶと三年生きる。二度転べば六年、三度転べば九年。何度も転べばううんと長生きできるはずだよ。」と言うのです。というストーリー展開です。韓国版一休さんみたいな感じ?ですね~。
6年生は版画の時間です。集中して彫り彫り。
今日は出張でしたので昨日の授業の様子でした。
今日の午後は、56年生対象の薬物乱用防止教室です。毎年学校薬剤師の先生に依頼しテーマを変えて教室の講話をしていただいています。
今年度は「薬物」についてです。最初はキャリア教育の視点も入れてくださり、薬剤師の仕事や業務をしていくにあたっての留意していることを紹介してくださいました。
お話された内容を少し紹介します。まず、薬とは、①病気やケガを早く治す働き、②健康な状態に戻すのを助ける働きがあります。この②が大切なんですよね。
薬を服用するには、どうやって飲む、いつ飲む、1日何回飲む、どのくらいの量飲むなど細かく決まりがあります。この「決まり」が大切ですね。
危険薬物についても説明がありました。そして、タバコやアルコールなどのきっかけとなるゲートウェイドラッグは大人も句を付けなければなりません。
薬物を乱用すると脳に異変が起こり、心身に大きな影響を与えます。薬物を乱用するともとの状態には戻れなくなります。
まとめてみました。
①薬物は1回使うだけでも乱用です。
②薬物乱用は心も体もボロボロにしてします。
③薬物乱用は犯罪です。
④甘い誘いには注意。「ちょっとだけなら....もダメ」
⑤SNSの誘いにも注意
⑥きっぱり断ろう、ダメ、ゼッタイ
今日の給食は、スタミナ元気になるレバー。そして人気ランキング7位のほうれん草ムースでした。美味しく頂きました。
今日の午後は2年生が玉ねぎ植えです。地域学校協働活動推進委員の方がゲストティーチャーで植え方を教えてくださいました。
「♡美味しく育て♡」という思いをこめて優しく、教えていただいたように植えていきます。
3月末から4月始めに収穫かなあ~。お世話も頑張ります。
1年生はタブレットで作品づくりです。
金曜日は今年最後の満月でした。コールドムーンでした。思わずパチリ♪
今日の給食はひじきサラダ、いわしの梅煮、すいとん汁でした。美味しく頂きました。
今日は今年最後の満月。コールドムーンです。夜空を眺めるのも一興かもしれませんね。
さて、今日は2回目の試走です。出発前に子どもたちに声をかけると、元気いっぱいの声が。ステキです。
今日は沿道にたくさんの方々が応援に来ていただきました。応援のパワーをいただいて子どもたちさらに加速したり、力を振り絞ったり、頑張っていました。
地域の皆さんが昨日も沿道の清掃をしてくださいました。今日も草が道に出てきている箇所を刈ってくださっていました。ありがとうございました。
子どもたちの頑張りの様子です。
低学年試走の様子です。
中学年試走の様子です。
高学年試走の様子です。
前回に引き続き、保育園の皆さんの声援もいただきました。
今日の給食は豚キムチご飯と大豆と豆腐のフライです。うちの試走に合わせてスタミナつけてください。疲れた筋肉にたん白質ということなんでしょうね。美味しく頂きました。
「いいね」ボタンをつけてみました。押していただけると励みになります。
来週もよろしくお願いします。
今日は所用で外にいますので、子どもたちの様子の紹介はありません。すみません。
富岡小学校は、創立150年も過ぎる伝統ある学校です。学校には文部大臣(現文部科学大臣)直筆の書が2つ飾ってあります。
一つが坂田道太氏の「人を先に私を後に」という額です。この言葉は私も大好きで、学校に指導に来ていただく習字の先生に色紙に書いていただきました。
もう一つが校長室前の廊下に掲示してある中村梅吉氏の下の額です。
「日々是進」です。(草書ですので「進」がたぶんです。)
先日ある本を読んでいましたら、「失敗することも前に進むこと」ということが書かれていました。毎日の生活の中で目に見えていいこと、成長したと感じることばかりではありませんよね。「ああ~やってしまった」「失敗したなあ」と感じることも多いですね。その時「次は、こうしよう」「こうすればよかったなあ」と自分を省みたり、次の行動につなげられれば前に進んだことと一緒ですよね。
子どもたちも一緒ですよね。
校長室を出て、「廊下、寒」と思って目に入ったこの額を見て改めてそう思ったところでした。
さて、今持久走の試走コースでも石蕗の黄色い花がたくさん咲いています。
花言葉は、きびしい環境でも育ち花を咲かせることから「困難に負けない」だそうです。
明日は2回目の持久走試走です。応援しています。
地域の皆さんのご支援にいつも感謝しております。
ICT支援の方に、HPに新機能を付けていただきました。最後に「いいね」ボタンが付きました。
ご覧になられたら、「いいね」ボタンをクリックしていただけると励みになります。
まずは、昨夜の苓P協、ふらーばるバレーボールレクレーション大会はありがとうございました。本校PTAから2チームが出場しました。出場された皆様、運営してくださった皆様、他のチームで参加された皆様、お疲れ様でした。私もとても楽しく参加させていただきました。3ポイントミスしたのが心残りですが・・・。
今日の朝は、大潮の満潮で強風。車に波のしぶきがじゃぶーーーん♪じゃぶーーーん♪冬だなあと思っていたら、午後からしんしんと冷えてきました。今日は低学年は標準学力テスト、中学年以上は県学力テスト2日目でした。子どもたち集中して頑張っていました。
今日は、昨日配付した学校通信「海の声11号」を掲載させていただきます。
今日の給食は、これです。給食アンケート第8位のスパゲッティでした。他にはミルクパン、シーザーサラダ、ウィンナーです。イタリアン的な給食でした。おいしくいただきました。
明日は、所用で不在としますのでHPの更新はお休みとさせていただきます。すみません。
たんぽぽ学級農園の大根が大きくなってきました。すくすく育っています。
さて、今日は1・2年生は標準学力テスト、3~6年生は県学力調査が実施しされていました。
よく頑張って、問題にチャレンジしていました。
さて、12月になり保健室の掲示板も模様替え。
12月の保健目標は「寒さに負けない暮らしをしよう」です。その他にも子どもたちがぜひ触ってみたくなるような仕掛けが・・・。元気に過ごすための『アドベントカレンダー』です。ちなみにアドベントとは、準備期間ということで、クリスマスまで気持ちを高めて行く準備、待ち望む準備なども含まれるそうです。
子どもたちにとって、クリスマスって一大イベントですよね。それまで毎日健康に過ごしたいですよね。
1年生は、生活科の学習です。タブレット端末を使って、学校にある花や植物をパチリ♪。
なかなかピントが合わなくて、悪戦苦闘していましたが、「とれたー」「これこうすればよかっばい」「ほうきぐさはみどりからあかにいろがかわる」など会話しながらパチリ。ステキな午後でした。
今日もまた、小春日和でしたね。それと関連してか、給食は春雨スープと春巻きでした。おいしくいただきました。
3年生が社会科の学習でお世話になったレタス農家の方が3年生にレタスを持って来てくださいました。ありがとうございました。
おいしいレタスの食べ方も教えていただきました。最後はみんなで記念写真です。「ハイ、レタス!」
朝の雨はびっくりしましたね。「え!今日雨なの?」
いい、持久走の試走日和と思ったのですが.......。日和と言ったら昨日、そして今日の午後は小春日和でしたね。先日ラジオで「小春日和って11月から12月初旬の季節とあわず温かい日のことで、2月、3月の温かい日にはつかえない」そうです。
そんな今日は試走の時間も雨で中止になりました。体育は体育館で持久走の練習です。次の試走は金曜日です。
今日の給食は豚汁と紅白なます、卵焼きでした。紅白なます縁起がいいですね。ん~~今日は祭事でしたっけ?美味しく頂きました。
今、子どもたちが登校するときに、ちょうど朝日が校舎を赤く染めているんですよね。
セピア色の校舎もステキです。
さて、今日から12月11日に開催される持久走大会の試走が始まりました。
春の迫地区のお孫さんが本校に通っている方々を中心に持久走のコースの草刈りをしていただきました。
また、今日は落ちているどんぐり等があぶないかもしれないとどんぐりなどを走路から掃いていただきました。
ありがとうございます。「子どもたちのためだけん、地区で声をかけ合って今年もしたと」とお話をしてくださいました。ありがとうございます。いつも感じているのですが、富岡地区の子どもたちをとても大切にしてくださる土地柄がとてもありがたいです
子どもたちも初めての試走でしたが、一生懸命走っていました。
中学年の様子です。
高学年の様子です。(低学年は、応援に一生懸命になってしまい写真を撮るのを忘れていました)
来週月曜日も晴れたら試走を行います。お時間がある方は応援をお願いします。
今日の給食は、これ。おいしくいただきました。
11月27日 苓北町教育委員会指定 学力向上推進校授業公開を行いました。
本年度は「主体的に学び、深め合う富っ子の育成~「聴き合い、学び合う」学びの充実を通して~」というテーマで研究を深めているところです。
苓北町内外から70名を超える先生方や教育関係者の皆さんに来校いただきました。ありがとうございました。
写真でその様子を紹介します。
6年生 社会「平和で豊かな暮らしを目指して」
5年生 国語「伝記を読んで「みんなde名著」を書こう
4年生 算数「見方・考え方を深めよう わすれてもだいじょうぶ」
3年生 理科「電気の通り道」
2年生 「かけ算」
1年生 算数「ひき算」
たんぽぽ学級 国語 2年生「お手紙」 6年「やまなし/イーハトーヴの夢」
終わって、子どもたちも「ああしっかり、じっくり考えたなあ」先生たちも「ほっとした。子どもたちがしっかり考え、頑張ってくれました。」などみんなが笑顔の公開授業となりました。
その後本校の授業をもとに授業研究会を行いました。また、3名の講師の方々に来ていただき、ご助言もいただきました。
低学年・特別支援教育部会の様子です。
中学年部会の様子です。
高学年部会の様子です。
ご助言いただいた3名の先生方、ありがとうございました。
参観者の皆様ありがとうございました。
苓北町教育委員会及び天草教育事務所の皆様、ありがとうございました。
本日いただいたご示唆、ご助言をいかして、さらに富岡小学校の教育の充実を図っていきたいと思います。
今日の給食は揚げパン。S小学校がマラソン大会だったからお疲れ様というこでしょうか?明日は本校が町教育委員会指定の公開授業です。チキンナゲットカレーライスです。愛情感じます。
さて、今日は6年生が九州電力グループ出前授業でした。サイエンスセミナーと言ってもいい出前授業です。
3人の講師の方がいらっしゃってスタートです。
発光ダイオード、プロペラ、オルゴールなど手回し発電機を回して、自分で作った電気で光らせたり、回したり、鳴らしたりします。
苓北火力発電所を卓上でミニチュア化した模型で発電機を分かりやすく説明もあり、分かりやすくクイズもあり、楽しい1時間でした。
ありがとうございました。
1時間目に教室を回っていると、3年生教室から話し合いの声。
「今日5時間目に1年生に読み聞かせをします。その練習を・・・・」
1年生が楽しんで聞いて本に興味を持ってくれるという意識で本も選んだんでしょう。
瞳がキラキラ!目的意識がハッキリしているので、心もぴかぴかですね。どのグループも一生懸命練習に励んでいました。
さあ、5時間目の本番です。1年生もニコニコです。いろんな工夫が見られます。抑揚、セリフの言い回し、間の開け方・・・すてきです。
最後は、全員で記念撮影です。
笑顔あふれる1年生と3年生でした。ステキな時間ありがとうございます。
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 木場
運用担当者 教頭 川端
教務主任 亀子