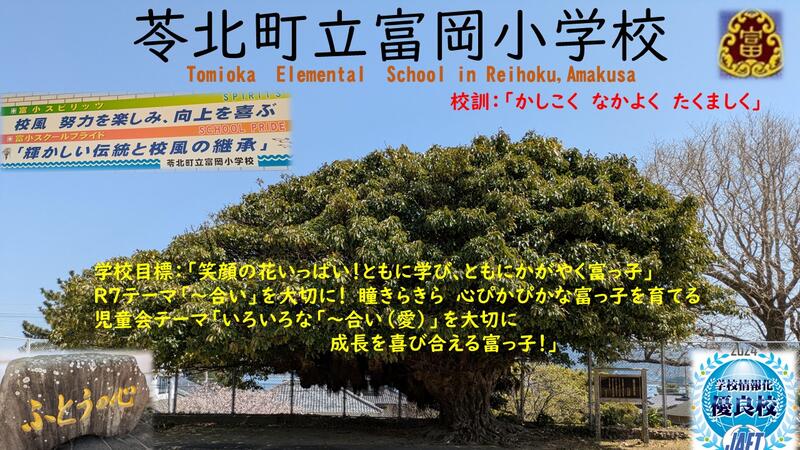
最終更新日 2026.02.18

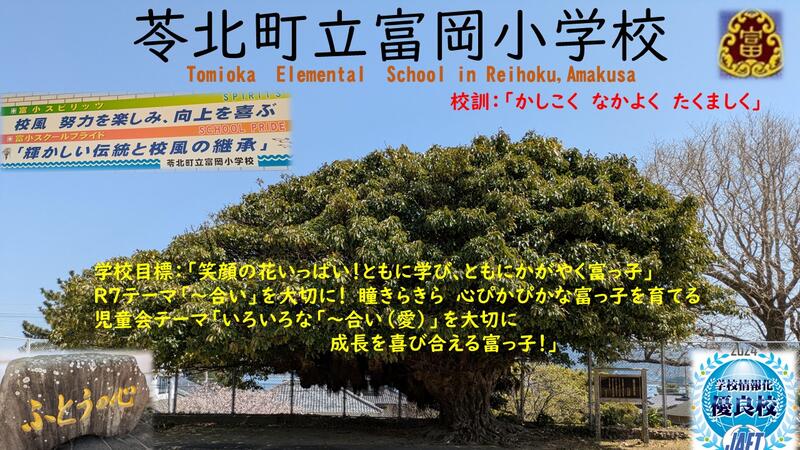
最終更新日 2026.02.18
今日の給食は、ふるさとくまさんデーでした。
太平燕。おいしく頂きました。
ちなみに昨日は八珍汁。貴重な八種類の具材が入っている汁物。
どれが8種類か数えながら楽しく頂きました。
高学年は、ハードルの練習中です。
4年生は昨日の授業の様子から。立方体づくりです。
「ああ、一面足りませんでした・・・」「1cmの立方体つくりました」など算数的活動を楽しみながら行っていました。
2年生も昨日の様子です。コップが飛び出す工作です。どんなびっくり工作になるのかなあ・・・楽しみですね。
熊日学童スケッチ展の作品を一つ紹介していませんでした。
明日から三連休です。ニュースなどを見ていますと感染症の拡大も心配ですね。まずは免疫力です。しっかり食べて、しっかり運動して、しっかり寝て、心のリラックスを図ってくださいね。
いい三連休になりますように♡
苓北町役場ホールでは、県子ども芸術祭オール天草に出品された子どもたちの作品が展示してあります。
お時間や用事がある方は、ぜひご覧ください。
今日は児童総会がありました。第2回目の児童総会は、「富岡小をさらによくしていくために」という共通認識のもとに、児童がそれぞれ分かれて児童会活動を行い、1年間の活動をまとめ、次年度の準備の場です。これまで委員長として、また委員長を支える立場として活躍してきた6年生。まさにリーダーでした。
その様子です。
企画委員会
給食委員会
環境委員会
放送委員会
体育委員会
保健委員会
図書委員会
児童からもたくさんの感謝の言葉がありました。
最後に私の挨拶です。
「2月も半ばになり、今の学年で過ごす時間も、あと少しとなりましたね。今日は、6年生がこれまでリードしてくれ、「学校を更によくしようと」取り組んできた児童会活動の1年間のまとめです。さて、皆さんが今年度、大切にしてきた児童会のテーマを覚えていますか? 「いろいろな『合い(愛)』を大切に、成長を喜び合える富っ子」でしたね。この「あい」という言葉には、たくさんの素敵な意味がこもっています。
〇友達と助け「合い」、支え「合い」〇元気に挨拶し「合い」 〇友だちを大切にした聴き「合い」・学び「合い」〇認め「合い」 〇周りの人を大切にする感謝の「愛」
皆さんの周りには、この1年間でたくさんの「合い(愛)」があふれていました。 困っている1年生に優しく教える上級生の姿、転んでしまった子に「大丈夫?」と声をかける姿。その一つひとつが、富っ子の大切な「宝物」です。
3学期は「まとめ」の学期であり、「準備」の学期でもあります。 今日の児童総会での話し合いは、6年生がリードしてきた1年間のまとめでもあり、これから5年生がリーダーとして引っ張っていく準備のスタートでもあります。今の富岡小の仲間と、最後までたくさん「合い(愛)」を届け合ってください。
そして、委員会、クラブ活動、登校班、そして普段の生活で6年生は皆さんを親身に思って、見えるところ、見えないところで様々な取組をしてくれていました。あと20数日で卒業する6年生への感謝、そして新しく入ってくる1年生への優しさを準備して、もっともっと富岡小を良くしていくための時間としていきたいですね。」
今日の給食は、ソフトフランス、白身魚そしてポトフでした。おいしくいただきました。
日曜日には学級懇談会のあとに子ども育成会餅つき大会を行いました。
餅米を提供してくださった倉田様、お手伝いをしてくださった富岡女性の会の皆様、そして育成会の皆さんありがとうございました。
私が以前本校に勤務していた頃は3月に行なっていたのかなあ。コロナ禍で中断して、一昨年実施して、本年度たくさんの皆さんのご協力もあって実施となりました。
事前に使用する道具を確かめ綿密に計画を立てられ、金曜日にはたくさんの保護者の方が手伝いに来てくださりセッテイングと6年生と餅米の準備。そして日曜日は朝8時から火を起こして準備。
子どもたちのためにと保護者の皆さん、そしてそれを手助けしてくださる地域の皆さん、すてきなこれぞ富岡パワーを改めて実感しました。ありがとうございました。
6年生が餅つき、4年生と5年生が餅丸めをしました。子どもたちも美味しそうに食べていました。「校長先生、18個食べました。」「私は14個」など笑顔で話してくれました。
途中で記念撮影。すてきな富岡らしい時間でした。
今日の給食は元気の出るレバー。元気になりました。
本日の授業参観、PTA総会、学級懇談会、子ども育成会餅つき大会はありがとうございました。
今日は、授業参観の様子から写真を中心にお知らせします。
子ども育成会餅つき大会は火曜日にお知らせしますね。
たんぽぽ学級の様子です。
1年生の様子です。
2年生の様子です。
3年生の様子です。
4年生の様子です。
6年生の様子です。
5年生の様子です。
お世話になりました。
最後にPTA総会でお話した校長挨拶の一部です。
「 令和7年度も、残すところ卒業証書授与式を含めてあと24日となりました 。 本日は、これからの学校運営に関わる3つの重要な点、①複式学級の設置、②学力調査の結果、③教育評価についてお話しさせていただきます 。
本校でも児童数の減少に伴い、令和8年度から複式学級を設置することとなりました 。この表は、苓北町の学齢簿をもとにした児童数の推移です。今後も統合までの4年間で複式学級が増加していきます。 複式学級設置にともない「チーム富小」として複式学級を支えていく体制づくりを現在構想しているところです。授業のスタイルも様々な形態になってきます。二つの学年が一つの教室で学ぶ複式の授業、一つの学年だけで学ぶ単式の授業、隣接学年と一緒に学ぶ共同の授業、担任外の教職員が指導する授業など現在どのような学びが可能かを構想しています。少人数での学習となるため、一人ひとりに目が届きやすくなるメリットがある一方、指導の工夫が求められます。学校としては、これまで以上に丁寧な指導体制を整えてまいります。
保護者の皆様にご協力いただいた学校評価アンケートについてです。今回は50家庭のうち50回答をいただき、皆様の教育に対する熱意を強く感じております 。
「心:なかよしの花」についてです。本年度は、「心の教育の充実」を最重要テーマとして学校経営、学校の教育活動を展開していきました。その中で、「いじめ・不登校対策の充実」「人権意識の向上、人権感覚の醸成」において評価が向上しました 。しかし、考察にも記していますが、「いじめはいけないことだと思いますか」という問いに一定数の児童が「理由があればいじめはいけないことだとは思わない」と回答していました。このことは、本年度の取組を一考しないといけないことと捉え、3学期の心の教育の更なる充実を現在はかっているところです。また、「児童と担任の関係の希薄さを感じる」という声をいただきました。この声を真摯に受け止め、児童一人一人との対話を重視した取組を今後も進めていきます。
「学び:がんばりの花」についてです。特別支援教育への肯定率が98%と非常に高く、個に応じた指導が評価されていました。。一方で「家庭学習の習慣化」や「読書活動」に若干の低下が見られました 。
「健康:元気の花」についてです。防災教育などの安全教育は向上しましたが、私たちも「体力向上」には課題が在ると考えています。体力テストで課題であった跳躍力や走力などの向上を体育の授業や集会活動などで今後も取り組んでいきます。
「感謝の花」についてです。全体的に高い評価を頂いていますが、早期対応・情報交換については、今後も重視して学校総体として取り組んでいきます。
保護者の 皆様からいただいた記述回答や口頭等でのご意見の中には、「先生方が一人ひとりに寄り添ってくれている」という温かい励ましの一方で、学校の働き方改革についてについてなど貴重なご指摘もいただきました 。
児童数の減少に伴う教職員数の減少を考慮した、学校の働き方改革は、「子どもとの向き合う時間の確保」という意味からも進めていきますが、それには保護者の皆様のご協力に頼る部分も多くなってくると思います。皆様からの声を真摯に受け止め、残りの24日間、そして令和8年度に向けて、子供たちが「自分らしく楽しい学校生活」を送れるよう、教職員一同取り組んでまいります 。 引き続き、本校の教育へのご支援をよろしくお願いいたします。
2月の保健目標は「心の健康を考えよう」です。
メインの掲示を、定期的に子どもたちが興味をもち、生活な中でちょっと考るきっかけとなるようにチェンジしながら掲示してくれています。ありがとうございます。
「こころがもやもやしたときどうする?」
もやもやは年齢、男女問わずありますよね。子どもたちもそうだと思います。自分のこころをいろんなきっかけで一歩前へ半歩前へでいいと思います。掲示を眺めながら思ったところでした。ちなみに私は2.10.20の方法かなあ。
さて、本校の教員業務支援員の先生が、熊日学童スケッチ展の入賞作品を「富小美術館」として掲示してくださいました。いつもありがとうございます。
日曜日の授業参観の時にぜひ見ていただければと思います。ホール、東側階段踊り場、東側2階階段、放送室前に分散して掲示しています。
他にも「版画」でもたくさんの賞をいただきました。また、描画では「熊本県子ども美術展」にも出品、入選していますので、今後その作品も展示していただけると思っています。
先日、「文化」についてお話しする機会がありました。その際に、ある方が『「文化」はなかったり、気にしなくても生活の上ではそんなに困ることは少ないと思います。しかし、絵画、工芸、音楽・・・いろいろな「文化」に囲まれていると人生を豊かにしてくれます。その豊かさが人生をいい意味で変えたり、厚みを持たせたりしてくれます」というお話をされました。まさにその通りと思います。校舎内が子どもたちの作品がたくさんあふれるステキな空間になっています。
さて、昨日の短縄跳びグランプリの様子です。躍動感あふれる、リズムある一瞬をご覧ください。
さて、今日の給食は、これ。おいしくいただきました。何とバレンタイン給食です。ありがとうございます。
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 木場
運用担当者 教頭 川端
教務主任 亀子