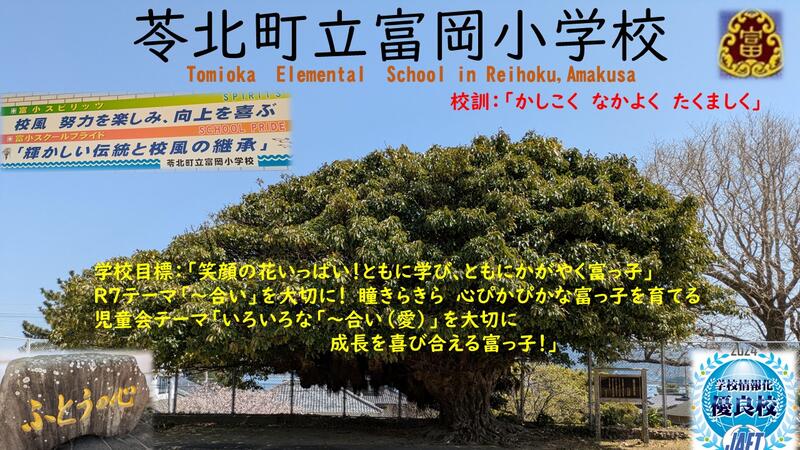
最終更新日 2026.02.12

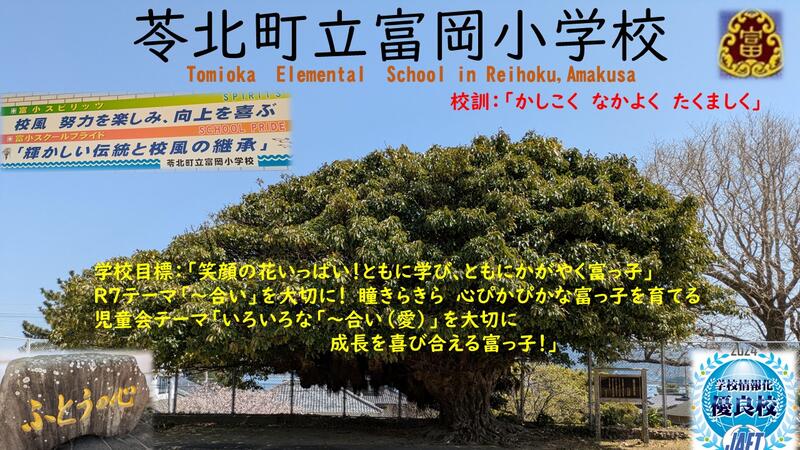
最終更新日 2026.02.12
6月19日(水)
今年度、富岡小学校は「人権の花」運動に取り組みます。花の栽培を通して、人権意識を高めていくことをねらいとした取組で、この日は法務局天草支局長様、天草人権擁護委員協議会、苓北町教育委員会の皆様をお迎えして、花の種子の伝達式が、3時間目ホールにて行われました。
進行は、環境委員会の子どもたちが行います。「人権の花」運動の立て看板や昨年度取り組んだ姫戸小、本渡東小からの花の種子を代表の子どもたちが受け取りました。1年生はひまわり、2年生はあさがお、3年生は千日紅・百日草、4年生はマリーゴールド、5年生はサルビア・ケイトウ、6年生はパンジーの種です。いろいろな種類の花がこれから富岡小学校を彩っていくと思うと、とても楽しみです。
花の種を渡し終わったところで、サプライズゲストの登場です。マスコットキャラクターのまもるくんとあゆみちゃんがホールにやってくると、子どもたちは大喜びでした。
まもるくんとあゆみちゃんが見守るなか、全員で「種をまこう」という詩を音読。最後に、各学年の「人権宣言」を発表しました。
伝達式が終わると、子どもたちは握手をしたり話しかけたり・・・と大人気のまもるくんとあゆみちゃんでした。かわいいマスコットキャラクターと全校児童で撮った記念写真はとてもいい思い出になったようです。
詩「種をまこう」のように、「人権」という名の種をまき、「思いやり」という名の水と「愛」という名の栄養をたっぷり注ぎ、みんなの「笑顔」という名の陽をあびて、芽が出て、花が咲き、大きな幸せの実が実るといいですね。美しい人権の花、なかよしの花、笑顔の花が咲き誇ることを願っています。
6月18日(火)
今週は、プール開き週間。まずは、先頭を切って高学年のプール開きが行われました。6月6日(木)に全校児童で掃除を行ったプールは、その後床面の補修を行い、きれいな水をたたえ太陽の陽を浴びてキラキラ輝いていました。準備運動を行い、シャワーを浴びてプールに入ります。
始めに、自由に水慣れをした後、子どもたちが大好きな「人間洗濯機?(プールの縁に沿ってぐるぐる何周も歩いて水の流れを作るもの)」を行いました。流れができた後、反対向きに歩こうとすると水の抵抗でなかなか前に進まず、歓声が上がっていました。
宝探しゲームも、学年対抗で楽しみました。この日は、高学年もたくさんのゲームや自由時間で初のプールを楽しみましたが、これからは7月23日(火)の苓北部会水泳記録会に向けて練習も頑張っていく予定です。高学年に引き続き、中学年は6月19日(水)にプール開きが行われ、低学年は6月21日(金)からプールでの学習が始まります。今年も、事故がなく、楽しい学習が進められていくことを願っています。
6月14日(金)
毎年行われている「苓北町小・中学校ごみゼロ実践運動」。本来ならば、5月30日前後に実施されるのですが、富岡小は運動会等で他の学校より遅い実施となりました。環境委員会の子どもたちが中心となって、ゴミ袋の準備や開始式の進行を務めます。
開始式が終わると、学年ごとに分かれて富岡の町のごみ拾いに出かけていきます。1年生は、富岡海水浴場駐車場、2年生は松林から山陽公園にかけてのごみを、燃えるゴミ・燃えないゴミに分別しながら拾ってビニル袋に入れていきます。
3年生は、フェリー乗り場から富岡神社に向かって、4年生は、フェリー乗り場周辺のごみを拾います。海岸には、洗面器やざるなどいろいろなプラスチックのごみが落ちていました。
5年生は、富岡海水浴場、6年生は、白岩崎キャンプ場に向かってゴミを拾っていきました。
最後は、各学年から集められたごみを環境委員会の子どもたちが、分別確認をしながらまとめていました。
6月9日(日)に、苓北町では各地区で清掃活動が行われていたので、例年よりゴミの量は少なかったようですが、それでも子どもたちは、いろいろなごみが捨てられていることに驚き、自分たちが住む富岡をきれいにしていかなくてはという意識をもつことができた時間となりました。
6月14日(金)
今年度のかなた班(縦割り班)の初顔合わせが朝の時間に行われました。
6つの班に6年生がリーダーとして入り、これから掃除や全校遊びなど様々な異学年との交流活動に取り組んでいきます。まずは、自己紹介から・・・
この日から早速かなた班掃除も始まりました。6年生のリーダーが掃除場所を分担して、下級生に指示を出していました。低学年の子供たちも、新しい掃除場所で上級生の掃除を見ながら黙々と掃除に取り組んでいました。最後は、班ごとに反省会。お互いに協力し合いがら学校をきれいにしていってくださいね。
6月13日(木)
最近天気のよい日が続いていますが、雨が多くなるこの時期、風水害に備えての避難訓練と災害時等保護者に安全に子どもたちを引き渡すための訓練を実施しました。訓練前の5校時、たんぽぽ学級では雨風が強くなったらどうしたらよいのか担任の先生としっかり考えていました。
午後3時10分、大雨洪水警報が発令されたという設定で放送があり、子どもたちは帰りの用意をして一度ホールに集合します。担当から風水害の危険やどんな行動をとるとよいのか話があり、その後お迎えを待つ場所に移動します。1・6年、たんぽぽ学級はあこうルーム前の廊下、2・3年は中央階段、4・5年は更衣室前の廊下に並んで名前を呼ばれるのを静かに待っていました。
午後3時40分、最初のグループの地区の保護者の方の車がどんどん運動場に入ってきました。2年生教室前でいったん停車いただき、担当が名前を確認しトランシーバーで児童の待機場所に伝えます。呼ばれた子どもたちは靴を履き、児童玄関前の職員が名簿で確認し、保護者の車に乗せていきます。
午後3時55分からは、第2グループの保護者の方が迎えに来られ、午後4時15分過ぎには、予定していた全保護者の方に子どもたちを引き渡すことができました。この日は、晴れていたため車への乗り降りや、運動場の走行もスムーズにできましたが、雨風が強いときはうまくいかないことも出てくることと思います。いろいろなことを想定し、今回の訓練の反省をもとに、より安全に子どもたちをご家庭に帰すことができるようにしていきたいと思います。平日のご多用の折、お迎え等大変お世話になりました。
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 木場
運用担当者 教頭 川端
教務主任 亀子