御船小学校 こどもたちの活動の様子
今日もどこかで
必要なものは残し、不要なものは無くす。誰もがよりよく生きるために不可欠な行動だと思います。1951年に、第3世代として今の形になり、今日まで続けられていることがあります。それは、ラジオ体操です。
御船小学校の管内でも、夏休みの朝を使って取り組んでいる地域がいくつもあります。「生活リズムを整える」「体の代謝を高める」など、メリットは言うまでもありません。数多あるメリットの中でも、現代だからこそ大事にしてほしいことがあります。それは「人と人とのつながり」です。友達や地域の大人と顔を合わせるこの時間は、つながりの希薄化が指摘される現代だからこそ、非常に貴重です。都合によっては、地域で集まってラジオ体操をすることができない場合もあるでしょう。そんな時は、家族でやってみてはいかがでしょうか。家族みんなで行うラジオ体操によって生み出されるのは、「心が通い合う時間」かもしれません。
なぜラジオ体操が、形も変えずに続けられているか。それは、やっぱり「必要」だからです。
最後に笑うのはキミだ!
多かれ少なかれ、生きていれば誰にでもアクシデントは起こります。そんな時に必要な力こそが、課題解決能力です。課題解決能力とは、例えば目の前に課題があるとして、その原因や今後起こりうることを的確に分析し、どうやって解決させるかを建設的に考え、整理し、そして行動する力のことと言えます。以前から日本人は、この課題解決能力を重要視しており、その育成に向けて1947年から5年間は「自由研究」という1つの教科を設けていました。
現代では夏休みの宿題の代名詞でもある自由研究。なにも、苦手な分野や内容をテーマにする必要はありません。「興味のあることや不思議に思っていることをテーマに選んで研究する方が、面白みがある。」という考え方も尊重されるべきです。一見他人から「馬鹿馬鹿しい」と笑われそうなことでも、本気で取り組めば大発見につながるかもしれません。既成概念にとらわれない「子どもの着眼点」を生かし、この夏、課題解決能力を伸ばしてほしいと思います。

偉人の言葉から得るヒント
「学べば学ぶ程、自分が何も知らなかったことに気付く。気付けば気付く程、また学びたくなる。」
これはアルバート・アインシュタインの言葉だそうです。この言葉が意味することは「勉強には、当事者にのみわかる面白さがある。」ということだと思います。「苦手だから」と拒絶していては、いつまでもその楽しさがわからず、ただただ時間だけが過ぎてしまいます。夏休みの今こそ「当事者」になってみませんか。
御船小学校が掲げている家庭学習の目安時間は、1・2年生:20分以上、3・4年生:30分~40分以上、5・6年生:50~60分以上となっています。勉強は、目標をもって取り組むことが理想です。目標の立て方がわからない場合は、上記の目安時間をはじめ、覚える知識の数、問題数、ページ数など、数値目標等にしてみると取り組みやすいと思います。
「楽しみながら学ぶのがベストだ。」トーマス・エジソンの言葉です。いきなり机上の学習が難しい場合は、体験活動や得意教科、工作等、興味のあることから取り組んでも良いかもしれません。
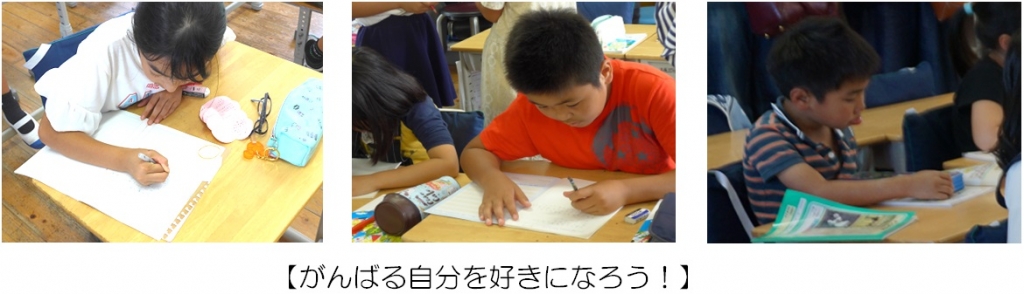
好機逸すべからず
今から2年前の2016年、「Benesse(ベネッセ)」があるデータを発表しました。それは、「小学生が家庭で行うお手伝い」をテーマとしたものです。本来お手伝いは、子どもの成長に欠かせない要素をたくさん持っています。例えば「家族の一員としての自覚」「将来の自立に向けた訓練」「計画的に一日を過ごそうとする態度の育成」「手先の器用さの向上」「忍耐力の上進」など、この他にも多くを挙げることができます。
さて、ベネッセの発表によると「お子さまは家でお手伝いをしますか」という質問に対する回答は以下の通りでした。
「必ず実行する」…16%
「ほとんど実行する」…24%
「実行する方が多い」…52%
「しない」…8%
御船小学校の児童の皆さんはいかがでしょうか。今は貴重な夏休み。できることを1つでも2つでも増やし、家族や自分のためのお手伝いに力を注いでも良いかもしれません。ちなみに、子どもが行っているお手伝いには、多いものから、1位 食器の準備や片付け、2位 洗濯物たたみ・収納、 3位 部屋の掃除、となっているそうです。
《引用》 ベネッセ 教育情報サイトhttp://benesse.jp/kosodate/201606/20160616-1.html

技と心と本気度と
先日行われた校内童話発表会についてご紹介します。発表会は二部に分かれており、第一部は1~3年生、第二部は4~6年生が参加しました。あらかじめ、各学級からそれぞれ1名ずつ代表を選出し、選ばれた児童は大勢の人が見守る中でマイクの前に立ち、覚えた童話を披露します。
一般的に、覚えた童話を暗唱することだけでも精一杯であるように思われます。しかしさすがは児童達。物語の展開によって、表情を変えたり抑揚をつけたりと、多くの工夫をしながら臨む様子に、発表を聞いていた誰もが驚かされました。
今回身につけた力は、学校だけでの学習によるものではありません。各家庭内で、自分で時間をつくって練習したり、お家の方と二人三脚で取り組んだりと、発表会までの日々こそが、貴重なものであったように思います。来年も多くの児童の挑戦があることでしょう。校内童話発表会の良さが生かされることを期待しています。

田植えにチャレンジ!
先日、JAかみましき青壮年部の皆様のご協力のもと、5年生が田植え体験を行いました。中には「家族のお手伝いで、田植えを経験したことがある」という児童もいますが、大部分が初体験。歩く度に泥の中に足が埋まり、伝わってくる感触に悲鳴をあげる児童やカエルに驚いて尻もちをつく児童等、様々でしたが、どの児童もとても楽しそうでした。稲の苗植えも、回数を重ねると、徐々に苗同士の間隔や植え方のコツがわかってきたようでした。
実際にやってみることは、何ものにも代え難い価値があると思います。「見た目はきれいな田んぼだけど、そこにはこんな過程があったのか。」「こんなに楽しいとは思わなかった。他の農業についても知りたいな。」今後児童同士で感想やわかったことを共有することで、更に学習を深めていきます。

引き渡し訓練
6月22日「災害発生時における児童の引き渡し訓練」を行いました。地震や大雨・台風接近時などの緊急時に、児童が保護者の基へ安全かつ確実に下校できるようにすることがねらいです。当日は多くの保護者の方々に参加して頂き、実際に災害が発生したときの動きを想定しました。どの児童も「移動中は必要でない限りおしゃべりをしない」「担任や放送の指示をよく聞いて行動する」など、緊張感を持ちながら参加する様子がありました。
今回都合がつかず、参加することができなかったご家庭もありました。いつ訪れるかわからない災害だからこそ、何気ない時間の中で、避難の仕方や約束の確認等について話題にする時間を大切にしてほしいと思います。学校、家庭、地域が一体となって、子どもたちの防災意識を高め「自分で自分の命を守る子ども」を育てていきましょう。

「10個知っている」よりも「5個やっている」
気持ちが落ち着いているから、行動も落ち着くのか。それとも、行動が落ち着いていると、自然と気持ちも落ち着いてくるのか。あるいはその両方か。
御船小学校の今月の生活目標は「落ち着いた学校生活を送ろう」です。本校では「落ち着いた学校生活」という言葉について、具体的に「校内では静かに過ごす」「整理整頓の徹底」「時間前準備・着席」「靴はかかとを並べて置く」等を指しています。低・中・高学年それぞれの発達段階に応じて目標の達成に向けた取組を行っています。
大切なことは、身につけたことが、相手や場面が変わっても生かされるということだと思います。学校内外で落ち着いた生活ができているか。相手や時期が変わっても、自発的に気をつけようとしているか。これらの態度を養うために、6月は児童と教師が一体となって取り組んでいるところです。
まずはやってみよう!
6月12日の業間を利用し、児童集会が行われました。この日は大きく「生活安全委員会による発表」と「各児童委員会の委員長からお知らせ」の2本立てです。生活安全委員会による発表では、廊下の安全な過ごし方について、児童らが劇を通して啓発を行いました。「急いでいるのであれば、走っても良いのでしょうか。」「他の人が走っていれば、自分も走って良いのでしょうか。」と問い掛ける内容になっており、一人一人が考える場となりました。2つ目の各児童委員会の委員長によるお知らせでは、今月の取組や全校児童へのお願いについて話がありました。特に健康委員会からは「歯ブラシチェックをすること」について報告がありました。「交換時期が近づいている歯ブラシには、シールを貼ってお知らせします。」とのことです。
発表した児童らは、すべての学年の子ども達にわかるように、言葉を選んだり、ゆっくりハキハキと話したりする工夫を行っていました。一つでも多く、自分なりの目標を持ちながら発表に臨んだことで、より大きな成長につながったように思います。

9日の就任式
4月9日に行われた就任式の様子についてご紹介します。今年度は、学校長を含む15名の職員の転任がありました。就任式が始まり、体育館に入場する先生たちを、前のめりになって見つめる児童たち。その姿からも、関心の高さがうかがえました。実は4月当初、御船小に赴任し、新学期の準備を進めていた教師たちからも「早く御船小の子どもたちに会いたい」という声がたくさん聞かれていました。児童と教師双方の思いが叶った日とも言えます。
就任式の中で行われた教師のあいさつは「御船町の至る所にある恐竜のモニュメントの数に驚きました。これから皆さんと過ごす中で、恐竜についてもたくさん知りたいです。」「私は休み時間には外にいることが多いと思います。是非たくさん声をかけてください。そして、一緒に遊びましょう。」「目標は『1日でも早く全員の名前を覚えること』『みんなに名前を覚えてもらうこと』『運動会ではみんなより早くダンスを覚えること』の3つです。」等、それぞれにユーモアがあり、賑やかな就任式に彩りました。
これからともに歩む1年間、「御船小が大好き!」と誰もが思える学校を目指して、充実した日々を過ごしていきたいと思います。
春を迎えて
平成30年度1学期がスタートしました。4月9日、久しぶりに登校した児童たちは、友達との再会を喜び、春休みの思い出を話したり、運動場で楽しく遊んだりする姿がありました。また、児童一人一人の表情から垣間見えたのは、学年が1つずつ上がったことによる喜びと緊張です。「今年こそ得意な教科を増やしたいな」「今まで自分が見てきた先輩たちのように、委員会や地区児童会で、上級生として活躍できるかな」等、様々な思いがあるようでした。それらも全てプラスに変えて、各々の自己実現に向けて1歩前進する、そんな1年になることを願っています。
最後になりますが、今年度も充実したホームページを目指して、御船小学校の情報を数多く発信していけるように努めて参ります。宜しくお願い致します。

春を前に
「御船小の子ども達の良いところは、内側に秘めたエネルギーだと思います。これからもどんどん伸ばして下さい。」
「担任をして一緒に過ごした日々、部活で一緒に汗を流した日々こそが一番の思い出です。」
「児童の皆さんよりも、教師である私の方が、多くのことを学ばせてもらいました。出会えたことが、本当に幸せでした。」
「『なぜだろう』というい気持ちを大事にしてください。『なぜ空は青いのだろう』『なぜあの子は悲しんでいるのだろう』。色々な『なぜ』を大事にすれば、やがて人を大事にする人になれると思います。」
「皆さんに好きなことはありますか。夢はありますか。それらを持ち、願い続ければ、必ず花開きます。」
子どもたちの顔を目に焼き付けるように、笑顔で言葉を伝える先生。感極まり、涙ながらに言葉をかける先生。個性が表れた、とても温かい時間となりました。先生との思い出を振り返り、感謝するとともに、先生たちの前途を祝う気持ちが育った貴重な機会となりました。

心温まる贈り物
心温まる贈り物が届きました。贈り主は兵庫県姫路市立白鷺小学校・姫路市立手柄小学校の皆さんです。白鷺小学校の先生とは、熊本地震の際からのつながりがあります。地震があった2016年夏、EARTH員(震災・学校支援チーム)として、多くのことで御船小学校の復興に向けたお手伝いをして頂きました。今回送って頂いた物は、お手紙と段ボールいっぱいのポケットティッシュです。ポケットティッシュと言っても、普通のポケットティッシュではありません。何と一つ一つにメッセージカードが付いており、目に入る度に、心がとても温かくなります。素敵なアイデアに感動しているとともに、地震発生から2年が経とうとしている今でも、遠い場所から気にかけてくださっていることに、大変感謝しています。ずっと大切にしたいつながりの一つであると、教師、児童共々感じました。
以下は、いただいたお手紙から一部抜粋してご紹介致します。
「今年は阪神・淡路大震災から23年になりました。毎年1月17日は、訓練と防災教育月間として、クラスで災害の話を聞きます。その時に、御船小学校の皆さんのお話をし、熊本地震のことや地震後の生活のことを、そして震災後に皆さんが先生方と一緒にがんばっていたことを伝えました。
兵庫県では、『南海トラフ地震』が起こると予想されていて、熊本地震の事は他人事ではありませんので、真剣に聞いていました。
4月の進級・進学に向けて、小さい学年の児童は『僕たちが頑張っていることを伝えると笑顔になってくれるかな。』など様々な思いを持ち、皆様にメッセージを書きました。
ポケットティッシュを使うときに、メッセージを見てください。少しでも、心がほっこりとして頂けたら幸いです。」
白鷺小学校ホームページ:http://www.himeji-hyg.ed.jp/hakuro-e/
手柄小学校ホームページ:http://www.himeji-hyg.ed.jp/tegara-e/
大人気!ドッヂビー!
1年生の体育ではドッヂビーをしました。ドッヂビーという名前に聞き覚えのない方は多いと思います。ドッヂビーとは「ウレタンとナイロンを使用したディスクを使う、高い安全性を持ち、手軽に楽しめる遊びであり、スポーツのこと」(日本ドッヂビー協会ホームページより)とされています。ドッジボールと同じルールですが、ドッジボールに比べると、ボール代わりのフリスビー(以下、ドッヂビー」)は動きがなめらかで、しかも当たっても痛くありません。運動が苦手な児童も、少ない恐怖感で参加することができます。
この日の1年生は、コートを横切るドッヂビーの動きを見ながら素早く逃げたり、何とかキャッチしようと構えたりする姿がありました。一方で、ドッヂビーの取り合いや、試合に負けて落ち込む児童もいました。しかし、これからの小学校生活の中で、たくさんの遊びやルールのあるボール運動の経験を重ねていきます。その中で、スポーツマンシップの精神や集団生活の送り方など、心も成長していくことと期待しているところです。

隠し味は「経験」
5年生は調理活動でみそ汁を作りました。事前に学習したことを思い出しながら、試行錯誤をする子どもたち。野菜によって切り方を変えたり、決められた水の量になるように計ったりしていました。一番苦労していたのは、いりこのはらわたを取る作業かもしれません。「どうすればうまく取れるのですか。」「隣の班が上手だな。教えてもらおう。」等、やりとりをしながらコツを掴む様子がありました。
調理活動は、日頃家で調理の手伝いをしているか、そうでないかがとてもよく表れます。この日も、慣れた手つきで次々と調理の過程をこなす児童と、包丁の握り方から一つ一つ尋ねている児童に分かれました。調理は将来自立する上で、必ず必要になる力です。ご家庭の中で親子で楽しみながら、調理経験を積み重ねることも策の一つだと思います。

いよいよ4月から
4年生の総合的な学習の時間では「外国語を楽しもう」をしました。主に「How are you?」と「I’m~」を使って友達とやりとりを行う、という内容です。やりとりを繰り返す中で、「ジェスチャーがあれば、より伝わりやすいよね。」「相手に聞こえる声の大きさで話した方がいいな」「表情に気をつけてみると、もっと気持ちが伝わる。」等、よりよいコミュニケーションの要点に気付く子どもたち。学習を重ねるにつれ、当初に比べて、どんどん良いものになりました。
自分の気持ちを伝える手段は、決して言葉だけではありません。むしろ、言葉だけでは思いが伝わらないことの方が多いです。そのことに気付くことができた貴重な時間となりました。
平成30年度から、御船小3年生4年生も、外国語活動が始まります。
たった一つの命
3月6日、地震の避難訓練を行いました。東日本大震災の記憶、そして熊本地震の経験等から、児童はいつも以上に真剣な眼差しで参加していました。安全担当の教師は「たった一つしかない命を守るのは自分である」と何度も発することで強調し、そのことで子どもたちの安全意識、防災意識は大きく高まったのではないかと思います。
「地震発生時に『落ちてこない、倒れてこない、移動してこない』場所に避難する行動は、児童生徒等に対しての事前指導が不可欠です。様々な場所や時間帯で発生することを想定し、どのような場所が安全なのかを指導しておくことが必要です。」これは、文部科学省がホームページで発信している「学校防災マニュアルについて(www.mext.go.jp/a_menu/kenko/.../07/.../1323513_02.pdf)」からの抜粋です。このことは、学校でもそうですが、家庭や地域においても十分に言えることだと思います。学校、家庭、地域で一体となり、防災教育に取り組むことができればと思います。

6年生を祝う会
3月7日、本校体育館にて「6年生を祝う会」を行いました。6年生はステージの前から体育館全体を見渡す形で座り、それを1~5年生が囲むように位置取りをしました。会では1年生から順に中央に立ち、6年生に向けた出し物を披露しました。歌のプレゼントや6年生を誘ってフォークダンスを行うなど、全ての出し物が、気持ちの込められた素晴らしいものでした。
そしてクライマックス、6年生と教職員によるドッジボール対決によって、会場の盛り上がりは最高潮に達しました。先生たちは「卒業後も応援しています」という気持ちを込めて、そして6年生は「思い出を胸に頑張ります」という気持ちを込めて、お互いに全力投球。1~5年生も会場を揺らすかのような大声援を送り、誰にとっても、温かく楽しい時間となりました。
学習や生活の随所で6年生が見せてくれた「スクラムパワー」。この日も多くの児童の心を惹き付けました。祝われる側で参加した活動でさえも、後輩たちの憧れで有り続けた6年生です。
お祝い会をしました
御船町特別支援学級合同授業「お祝い会」について紹介します。お祝い会は、「御船町の小中学校特別支援学級に在籍する児童生徒の親睦と集団行動の向上を図ること」、「卒業生を励ますとともに、今年度のまとめの会をすること」、「保護者同士で情報を交換し合い、親睦を図ること」の3つを目的として行われる、毎年の恒例行事です。
今年度は2月27日に行われ、主な活動として「御船小3年生との交流及び協同学習」「調理活動」「卒業生を祝う会」「保護者向けの研修会」等がありました。交流及び共同学習ではペアをつくり、自己紹介や風船運びゲームをしました。活動の中で、互いの好きなことや学校の紹介をし合う等、両者とも交流を楽しむ様子が見られました。卒業生を送る会では、卒業生が全体の前に出て、一人ずつ友達や家族への感謝の気持ちを伝えるとともに、今後の抱負を述べました。
これから卒業生たちは、自分の将来に向けてそれぞれの進路先へと進みます。在校生にとって、仲間とのお別れは寂しいですが、今後も活躍していく先輩の姿を見ることで「自分もがんばろう」という気持ちが高まるのではないかと期待しているところです。
空き箱→宝箱
5年生の図工では「伝えたい気持ちを箱に込めて」をしました。空き箱にビーズやスパンコールを使って装飾を施し、世界に一つだけの箱に仕上げるという工作です。この作品の魅力は、箱に何らかの形でメッセージを添えて、誰かに贈るという点にあります。例えば、ある児童は家族に対して「ここまで自分を育ててくれてありがとう」、別の児童は祖父母に「いつまでも元気でいてね」、兄弟に「大好きだよ」等々、楽しそうに箱のふたの裏に書いたり、箱の中に手紙を入れたりしていました。日頃はなかなか照れてしまって言えない気持ちも、作品という形であれば、表現できるものなのかもしれません。この箱が、受け取った人にとって「宝物」になること、間違いありません。










