「やさしく・しっかり考え・たくましい南関三小っ子」が育つように学校と保護者、地域、南関町の教育行政のみなさんでウェルビーイングが循環する「地域とともにある学校」を目指しています。

「やさしく・しっかり考え・たくましい南関三小っ子」が育つように学校と保護者、地域、南関町の教育行政のみなさんでウェルビーイングが循環する「地域とともにある学校」を目指しています。
たんぽぽ学級では、自立活動で「合同お別れ会」に向けたハンドベル練習を行いました。
ハンドベルの扱い方や鳴らし方を確認した後に、学習リーダーを中心に担当の音を決めて練習をしました。
心を込めて協力し合いながら練習をすることができました。
2月1日に「人権フェスティバル」、2月13日に「学習発表会」があります。
学級会の議題1では、人権フェスティバルではセリフだけにするか、歌を歌うか。議題2では人権フェスティバルと学習発表会のリハーサル、歌を練習する日程を考えました。
子供たちは「歌を入れると時間がぎりぎりになってしまう。」「歌を歌うことで小さい子でも仲間の大切さが伝わる」など様々な意見を出していました。
また日程決めでは、「土日は休みだから、金曜日と月曜日に入れるといいのでは」「毎日練習は委員会の仕事もあるからできない人もいる。あまり仕事のない水曜日はどうか」など詳しい理由を含めたくさん議論していました。最後は全員が納得した意見でまとまり、現在猛練習中です!ご期待ください♪
1月21日に持久走大会がありました。今回のテーマは「自分に勝つ」。順位ではなく、タイムをいかに縮め、目標タイムに届くかを大切にするということを子供たちに話し練習をスタートしました。寒い中でも、タイムを縮めるために一生懸命練習に取組む姿は、とても素晴らしかったです。
本番ではほとんどの子がタイムを縮めることができていました。きつくても諦めなければ、結果はついてくることを実感し、学ぶことができたのではないでしょうか。保護者の皆様、平日にもかかわらず沿道での見守りや応援、本当にありがとうございました。
先週の⾦曜⽇に「お結びの会」を⾏いました。朝学校に来て早速お⽶を洗い、炊飯器のスイッチを押しました。3時間⽬には炊き上がっていて、炊飯器を開けると、「わあ!」と⼦供たちの歓声が上がりました。そこから、どんどん握り、60個以上のおむすびが完成しました。4時間⽬は飾りや地域の⽅々に送るプレゼントなどを準備し、最終確認を⾏いました。そして本番、⼦供たち⾃⾝で会を進めました。堂々とした姿で、いろんなところに気を配る姿が⾒られ感動しました。⼦供はこんなにも成⻑するんだと実感することができました。 この経験を⽣かして、さらに成⻑し、⽴派な6年⽣になってほしいと思います。保護者の皆様、懇談会にも⾜を運んでいただき、ありがとうございました。
11月11日にAーlifeなんかんさんが来校され、パラスポーツ「ボッチャ」の体験をさせていただきました。ボッチャは古代ギリシャの「石投げ」がルーツとされていて、1988年のソウルパラリンピックで正式種目になったスポーツです。道具をみたりルールの説明を聞たりして子供たちは興味深々。2チームに分かれて対戦しました。最初はかなりてこずっていた子供たちでしたが、だんだんコツをつかむ子が現れ「うおー!」「あーおしい!」と盛り上がりを見せていました。私も挑戦しましたが、なかなかうまくいきませんでした。子供たちにとっても私にとってもよい経験になりました。
12月12日(金)
地域の皆様のご協力をいただき、今年も南関あげまきずし作りを体験することができました。「巻きす」を体験す
るのが初めての児童が多かったのですが、分かりやすく作り方を教えていただき、とても上手に作ることができま
した。婦人会の方から、「地元のスーパーに売りに出せるね。」と、うれしい声をいただきました。ふるさとの味、
南関あげのおいしさを十分に味わうことができました。
脱穀と同じ日に芋ほりを行いました。
春にうえた芋の苗がぐんぐん育ち、大きな芋がたくさん埋まっていました。子供たちは土を掘っては手で抜き、掘っては抜き、大きい芋が取れたら「でか~!!」喜びの声を上げていました。私も芋ほりは幼稚園以来。約20年ぶりに芋を掘りました。とても楽しい時間でした。
30日(木)の5・6時間目に「脱穀」を行いました。
お米作りの最終工程でした。かけ干しされた稲をコンバインに運び、もみとわらに分け、わらは束ねてトラックに積みました。わらやもみくずが舞い上がり、マスクをしての作業で大変でしたが、子供たちは最後まで一生懸命取り組みました。来週あたりにお米が届くそうです。楽しみです!
先週の金曜日に家庭科の調理実習で「ご飯」「味噌汁」を作りました。これまで家庭科の授業で食材には「五大栄養素」や「3つの働き」があることを学習し、ご飯と味噌汁だけでもたくさんの栄養がとれることに気づきました。そんな和食の代表ともいえるご飯と味噌汁を作れるようになろうということで班で計画を立て、役割分担を行い、当日を迎えました。
当日は婦人会の方々、教育委員会の方、保護者の上野さん、堀田さん、大倉さんに来ていただき、万全の態勢で調理を行うことができました。
各班で声を掛け合って協力し、見事おいしいご飯と味噌汁を作ることができました。私も食べましたがとってもおいしかったです。婦人会の皆様、教育委員会の方、保護者の皆様、ありがとうございました!
6年生は、17(金)、18(土)に長崎へ修学旅行に行きました。これまで、平和について学んできた6年生にとって、語り部の方の講話、原爆資料館、平和公園、爆心地公園、浦上天主堂、如己堂、山里小学校を歩いた現地学習は、とても深い学びとなりました。夜は、ホテルからの100万ドルの夜景を楽しみ、「焼け野原から、これだけのきれいな夜景になるまでには、きっと日本中の人ががんばったんだろうな。」というつぶやきが、子供たちの間から聞こえてきました。二日目は、ハウステンボスを満喫し、たくさんの思い出を抱えて帰路につきました。
修学旅行は目の前です。先日、千羽鶴ができあがりました。ハウステンボスのパンフレットをじっくり見ながら、ワクワクが止まらない様子の6年生です。「昼食は佐世保バーガー?やっぱりちゃんぽん?」「アトラクションはどれから始める?」計画通りに進み、修学旅行を満喫できますように。当日の天気が気になります。
この日は、トッパ丸君の誕生日。南関町交流拠点施設<ukara>にて、町制70周年記念イベント「子どもたちの未来への提案」が行われ、三小を代表して6年生が発表をしてきました。町長をはじめ、役場の方々、地域の方々など大勢の観衆の前で、堂々と落ち着いた態度で発表をすることができました。 「もしも、自分たちが町長になったら」をテーマに、「病院、映画館などみんなの願いが叶うビルを建てます!」「酷暑の夏でも快適に過ごせる学校作りを目指します!」「外国の人と交流を深めるイベントを実施します!」と、熱弁をふるう姿に、会場が盛り上がりました。未来の町長が、この中にもしかしたら・・・・。
6年生は、修学旅行の平和集会に向けて千羽鶴を作る活動に入りました。「1つ1つに平和への願いを込めて」の心の
声が聞こえてくるような温かい雰囲気の教室となりました。寺川先生に丁寧に教えてもらいながら、次々に鶴を重ねていました。完成が楽しみです。
いよいよ、17,18日は修学旅行です!
国語の「新聞を読もう」の学習では、新聞のしくみや読み方などを学習しました。新聞には「見出し」「リード文」「本文」などがあり、それぞれ読書が読みやすいように工夫され書かれていることや、地方紙と全国紙では、同じ記事でも、内容が違うことにも気づきました。最後に「熊本日日新聞」の今年の新聞から、自分の気になった記事を選び、内容の要約と感想をまとめていきました。
今現在、総合の学習で「米づくり新聞」を作成中なので、今回の学びを生かし、分かりやすく読みやすい新聞をつくってほしいと思います。
6年生は、単元「思いを形にして生活を豊かに」にて、トートバックを作成しています。子供たちは、久しぶりのミシンの扱いに少し緊張気味の様子でしたが、それ以上に出来上がりを楽しみにしていました。応援団の先生方からミシンの使い方、縫い方などをていねいに教えていただいたおかげで完成に近づきました。授業の最後の「ありがとうございました。」のお礼の言葉には、達成感と感謝の気持ちがたくさん込められていました。
夏休み前7月と夏休み中の8月の2回に分けて、子供たちと保護者の方々で協力し作り上げたかかしを5年生の田んぼへ立てに行きました。
ちゃんと立つか不安でいっぱいでしたが、3体ともしっかり立ち、とても田んぼに「映えて」いました!この3体のかかしが、鳥を追っ払ってくれるといいねと子供たちと話しました。さらにたくさん実をつけ成長してほしいと思います。保護者の皆様2回にわたってたくさんのご協力をいただきありがとうございました。
9月9日(火)スマホ・ネット安全教室が開かれました。
SNSを上手に楽しむために、知っておかなければならないルールやモラルについて自分の考えをワークシートに書いて、友達と交流しました。情報発信する際に気を付けることをしっかりと学ぶ機会となりました。そのあと、人権擁護委員の山下様から人権についての話を聞き、悩み事や不安は、一人で抱え込まずにだれかに相談して解決していくことが大切だと教えていただきました。
8月24日に親子レクレーションとして「かかしづくり」を行いました。たくさんの方に参加していただき、無事に完成することができました!とてもクオリティーの高い3体のかかしができ、私も感動しました。
かかしは9月上旬に5年生の田んぼに設置したいと思っています。保護者の皆様、2回にわたり協力していただき本当にありがとうございました。
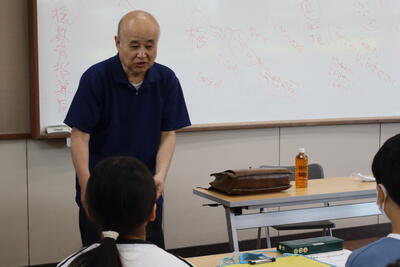
6年生は、南関町教育委員会主催の「通学学習」を受けました。人権学習では、「失敗は成功のもと」「覆水盆に返らず」という言葉に込められた意味を納得しながら聞いていました。他にも、人権感覚の大切さを教えていただき、日頃の友達との付き合い方を考えていました。この時間をきっかけに、6年生がステップアップするのを予感しました。総合的な学習「大好き!南関町」にて、南関町の文化財「南関城跡」「御茶屋跡」「旧石井家住宅」を見学しました。講師の先生から詳しい説明を聞きながら、自分たちのふるさとの魅力を肌で感じていました。
6月24日に調理実習を行いました。地域の方々のご協力をいただき、2時間でスムーズに調理することができました。今回は「ゆでる」がテーマで小松菜のおひたし・ゆでいも・ブロッコリーと人参とキャベツのいろどりサラダをつくりました。ボールいっぱいあった野菜たちはゆでることでかさが減り、たくさん食べることができました。ゆであがり、小さくなった小松菜を見て「すごい!」「こんな小さくなるんだ!」と驚きの声を上げていました。とても楽しく、勉強になった調理実習でした。
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 村岡 英治
運用担当者
教諭 田川 昭太
〒861-0812
南関町立 南関第三小学校
TEL 0968-53-0101
FAX 0968-53-0140
E-mail nankan3-es@tsubaki.higo.ed.jp
URL https://es.higo.ed.jp/nankan3e/
※住所をクリックすると別ページで地図が開きます。