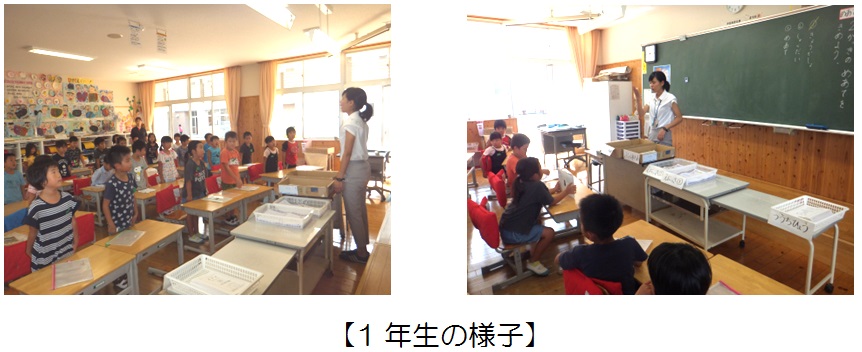カテゴリ:1年生
がんばっています!1年生!
1年生の道徳の授業の様子を紹介します。御船小学校は道徳教育の研究校に指定されており、今年度はその3年目に当たります。毎回児童の実態をもとに、育てたい児童の心や姿を具体的に設定し、様々な手立てを工夫しながら授業を組み立てています。
この日の授業では「ダメ」(出典「あたらしい道徳」東京書籍)という教材を使って学習しました。目指した姿・心は「嫌だった気持ちを、勇気をもって伝える子ども」です。教材の中には「自分よりも強そうな相手に対し、思い切って自分の気持ちを伝える場面」があり、「実際に伝えた後の自分の気持ち」に着目することで、勇気をもって行動することの大切さについて考えました。
1年生からは「気持ちを伝えたから相手がわかってくれた。頑張って伝えて良かったと思う。」という意見が多く出ました。道徳教育は、日常生活の中で生かされてこそ意味があります。本時で学んだことが、今後の児童の姿として表れることを期待しています。

大人気!ドッヂビー!
1年生の体育ではドッヂビーをしました。ドッヂビーという名前に聞き覚えのない方は多いと思います。ドッヂビーとは「ウレタンとナイロンを使用したディスクを使う、高い安全性を持ち、手軽に楽しめる遊びであり、スポーツのこと」(日本ドッヂビー協会ホームページより)とされています。ドッジボールと同じルールですが、ドッジボールに比べると、ボール代わりのフリスビー(以下、ドッヂビー」)は動きがなめらかで、しかも当たっても痛くありません。運動が苦手な児童も、少ない恐怖感で参加することができます。
この日の1年生は、コートを横切るドッヂビーの動きを見ながら素早く逃げたり、何とかキャッチしようと構えたりする姿がありました。一方で、ドッヂビーの取り合いや、試合に負けて落ち込む児童もいました。しかし、これからの小学校生活の中で、たくさんの遊びやルールのあるボール運動の経験を重ねていきます。その中で、スポーツマンシップの精神や集団生活の送り方など、心も成長していくことと期待しているところです。

100%の理解を目指して
「重要な文を見つけたら、このように文の横に線を引いてみましょう。」「問題を出す人が、何を尋ねているかは、文の中のこの部分を見たらわかりますね。」教師が指示する内容が、画面に大きく映し出され「このように」や「この部分」が何を指しているのかがすぐにわかります。
もしもこの場に実物投影機がなければ、聞き漏らしであったり、解き方のコツがわからないまま進んでしまったりということがあるかもしれません。実物投影機は、児童の理解をより一層深めるとともに、様々な課題の予防にも効果を果たしています。

しらせたいな 見せたいな
1年生の国語では「しらせたいな 見せたいな」を学習しています。第1校時のこの日のめあては「知らせたいものの絵と見つけたことをかこう」です。
知らせたいものとして、捕まえたドングリ虫を選んだ児童は、その姿をノートに大きくスケッチし、気づいた特徴を1~3文で記しました。「かみたろう」と名付け、愛着をもって観察する様子が印象的でした。
テントウムシを捕まえ「天ちゃん」と名付けた児童は「私は12個も特徴を見つけたよ!」と嬉しそうに話していました。ノートを覗くと、「背中がかたい」「体よりも頭が小さい」等、見つけた情報がビッシリ。学習に対する積極性が強く感じられました。
次回の学習では、今回見つけた情報を文章で表すことに挑戦します。句点や語と語の続き方等、基礎を押さえながら「文章を書くって楽しい!」という気持ちにつながればと思います。
すべての努力に意味がある
1年生では、教師と子どもたち全員が一緒になって、新学期の提出物の一つ一つを丁寧に確認しました。時間はかかりますが、そのことで、せっかく頑張ってきた宿題を提出し忘れたり、別のプリントに紛れてしまったりということを防ぐことができます。夏休みのワークや作品を、胸を張って提出し、「がんばりましたね」と担任から褒められる姿が印象的でした。
また、この学級では「気をつけ」等の姿勢について、意識的に指導を行っていました。「初めが大事です。初めの頑張りこそ、二学期すべてにつながります。まずはみんなでピシッと姿勢を整えてみましょう。」周りの友達の様子ではなく、自分自身の背中や指先に気をつけて、凛々しい表情で前を見つめる子どもたちの姿に、頼もしさを感じました。