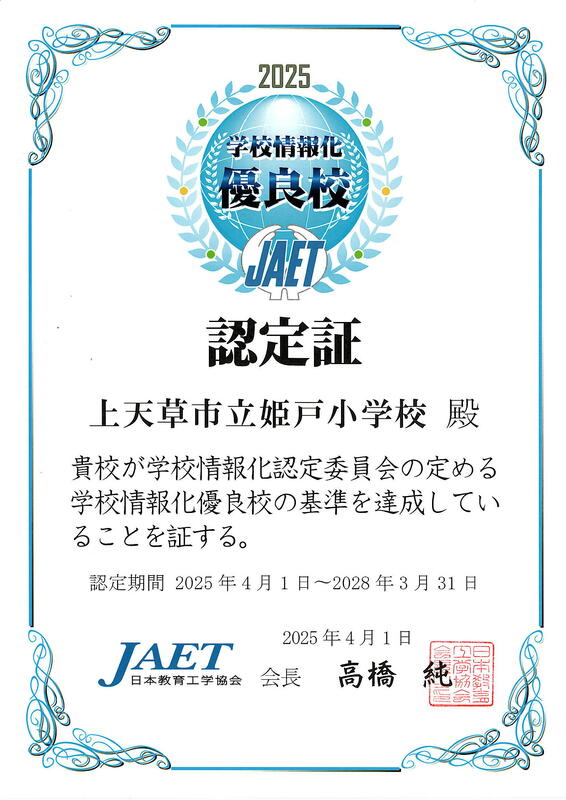学校だより
新緑、目に眩し
4月8日(金)快晴。
姫戸小学校が、令和4年度の新たな目標や夢に向かって、子どもたちも職員も、一斉にスタートをきりました。
「新緑、目に眩(まぶ)し」薫風香る皐月は、もうしばらく先ですが、桜が散った山々を望めば、モコモコと若葉が萌え初め、生き生きとした春の息吹を感じます。
始業式で対面した子どもたちの、新たな学年に向かうキラキラとした瞳に、その「新緑」のまばゆさを感じました。呼応して「この子どもたちのために我々も頑張るぞ」という気迫を、職員全員から感じとった次第です。
校長挨拶では、進級のお祝いと新学年における期待を述べるとともに、子どもたちに次のような話をしました。
①自分の命は、自分で守る。
絶対に飛び出さない。道路を渡る時は、手を挙げて、右よし、左よし、右よしと必ず確認する。
②人の話は「目と」「耳と」「心で」聞く。
しっかり聞いている人は、目が合います。うなずいています。その上で大事なのは、その話について自分の意見を持つこと。その意見を発表することです。
③学校では友だちの名前を「さん付け」で呼ぶ。
自分を、友だちを、大切に、大事にするために「さん付け」をします。先生たちは、みんな一人一人に、同じように、平等に、真剣に寄り添います。だから、男の子も、女の子も、みんな区別なく、「さん付け」をします。学校では「さん付け」。じゃぁ、日曜日に友だちと遊ぶ時は? 大事なのは「呼び捨て」や「ニックネーム」について何度もみんなで話し合うこと。そのときに必要なのは「嫌なことは、嫌」と言う勇気です。
なお、「さん付け」には賛否両論ありますが、公の場での振る舞いを身に付ける、教師と児童、児童同士の適正な距離を整える、性的マイノリティの尊重という観点で必要であると考えます。ご家庭や地域で話題にしていただければ幸いです。
歓迎遠足での、柊斗さんと池田先生と小野先生。碧い海と青い空。向こうに八代が見えますね。
ご卒業おめでとうございます
令和4年3月24日(木)、爽やかな青空から穏やかな陽の光が照らす「春うらら」。皆さまの御陰をもちまして、第63回卒業証書授与式を挙行することができました。
コロナウイルス感染症拡大防止のために、地域の方々をご招待できなかったことが唯一の心残りですが、18名の卒業生一人一人が立派に胸を張り、晴れやかな表情で巣立っていきましたことをご報告致します。校長式辞の一部をご紹介します。
(前略)
いま、一人一人に卒業証書を手渡しました。皆さんが手にしている卒業証書は、6年間の学びがすべて修了したという証です。あとでそっと開いて、見てください。その卒業証書には、友達と違うところが三カ所あります。
一つ目は、はじめに書かれている番号です。この番号は、あなただけの番号です。第一回卒業生から繋がっている番号です。そしてこの番号は、来年、再来年とずっと繋がっていきます。あなたは、この姫戸小学校の引き継がれた「伝統」の中に居るのです。
二つ目は、もちろん、あなたの名前です。おうちの方があなたへの限りない愛情と、成長していくあなたへの願いを込めた大切な名前です。その名前を、小学校生活で何度呼ばれてきたことでしょう。小学生として名前を呼ばれるのも、今日が最後です。
三つ目は、あなたの生年月日です。そこに書かれている日に、あなたの命が生まれ落ちたのです。家族やみんなが、どんなにあなたの誕生を待ちわび、喜ばれたことでしょう。あなたの命が生まれた日から、今日まで「四千数百日」。たくさんの方々があなたを見守ってくれました。心から愛し、大切に思いながら育ててこられたのです。あなたは 家族の 「宝物」 です。
たくさんのことが詰め込まれたこの卒業証書は、姫戸小学校と皆さんを、また、一緒に卒業する仲間たちを固く結びつけるものです。 生涯、大事にしてください。
この、よき門出に次の言葉を贈ります。
思考に気をつけなさい、それはいつか 「言葉」になるから。
言葉に気をつけなさい、それはいつか 「行動」になるから。
行動に気をつけなさい、それはいつか 「習慣」になるから。
習慣に気をつけなさい、それはいつか 「性格」になるから。
性格に気をつけなさい、それはいつか 「運命」になるから。
これはマザー・テレサの言葉です。人は、自分の口から発せられた言葉通りの人生を歩むことになる、という意味にも受け取れます。「できない」 「でも」 「だって」という負の感情を口にするよりも、何度失敗しても挫けず、「やれる!」 「大丈夫!」と果敢に立ち向かう意気込みを口にするべきである、ということです。身体は食べたもので作られますが、人間性は自分で言った言葉、人から言われた言葉で作られます。
家族や友だち、先生、地域の方々がいつも、あなたを応援しています。
希望の言葉を忘れず、堂々と前進してください。 (後略)
2016年(平成28年)4月14日及び16日に発生した熊本地震は、卒業生18名が小学校に入学した直後の出来事でした。二度にわたる大きな揺れは天草にも伝わり、各所で避難所が開設されるほどでした。テレビに映し出される土砂崩れ、崩落した阿蘇大橋、寸断され波打つ道路、倒壊した家、変わり果てた熊本城の様子など、幼心に自然災害の脅威を感じ、恐怖感で眠れない夜もあったことでしょう。昨年の修学旅行では卒業生18名と一緒に熊本城や阿蘇方面を訪ね、熊本地震における被害や復興の様子、人々の願いや想いを自分達の目と耳と心で確かめてきました。
また、この2年間はコロナウィルス感染症により活動の自粛を余儀なくされました。学校のリーダーとして活動したくても「3密」を避ける行動を強いられ、二ヶ月にも及ぶ休校、行事の中止や縮小も相次ぎ「頑張ろう」とする機会も奪われてしまいました。
でも、そんな中、登校班で元気に「おはようございます」と下級生に模範を示す姿、姫戸小を更に良い学校にしようと励む委員会活動、応援団とソーラン節で盛り上げた体育大会など、卒業生18名一人一人の意気込みと努力、誠実な人柄を大いに感じた一年間でした。「ありがとう。」という感謝の言葉しかありません。ちょくちょく遊びに来てくださいね。先生たちも、後輩たちも、みんなで待っています。
ゆずり葉
ゆずり葉 河井醉茗
子どもたちよ
これはゆずり葉の木です
このゆずり葉は
新しい葉ができると
入り代わって古い葉が落ちてしまうのです
こんなに厚い葉
こんなに大きい葉でも
新しい葉ができると無造作に落ちる
新しい葉にいのちをゆずって
子どもたちよ
お前たちは何をほしがらないでも
すべてのものがお前たちにゆずられるのです
太陽のめぐるかぎり
ゆずられるものは絶えません
かがやける大都会も
そっくりお前たちがゆずり受けるのです
読みきれないほどの書物も
幸福なる子供たちよ
お前たちの手はまだ小さいけれど
世のお父さん、お母さんたちは
何一つ持ってゆかない
みんなお前たちにゆずってゆくために
いのちあるもの、よいもの、美しいものを
一生懸命に造っています
今、お前たちは気が付かないけれど
ひとりでにいのちは延びる
鳥のようにうたい、花のように笑っている間に
気が付いてきます
そしたら子どもたちよ
もう一度ゆずり葉の木の下に立って
ゆずり葉を見るときが来るでしょう
河井醉茗(かわい すいめい)は、明治7年大阪府堺市に生まれ、昭和40年に90歳で長逝。明治、大正、昭和を生き抜いた日本の詩人です。「文庫」の記者として詩欄を担当し、伊良子清白、横瀬夜雨、島木赤彦、北原白秋、服部嘉香、川路柳虹など多くの詩人を育てました。また雑誌「女性時代」「詩人」を刊行するなどして口語自由詩を提唱しました。
ゆずり葉は暖かい地域の海岸近くに多く生息し、庭木としても知られます。実家の庭にも、私が生まれるずっと前から植えてあります(久玉では「つんのしば」と言います)。
冬の期間、寒さに耐えて枝に付いているのですが、春になると、ぽろっと葉が落ちてしまいます。その落ちた葉の後には、次に出てくる若い芽がしっかりと育ってきています。落ちた古い葉は、冬の寒さから若い芽を守っていたのです。その様子が自分の命を次の葉にゆずっていくということで「ゆずり葉」と名付けられたのが由来だそうです。
正月の鏡餅の飾りやしめ飾りに使われますが、新しい葉が出てくるまで古い葉が落ちないという特徴から、親から子へ受け継ぐこと、若い者が成長し年長者よりも先に亡くならず家系が代々永く続くことを願った縁起物として飾られます。
万葉集の中にも、弓削皇子が額田王に読んだ歌でゆずり葉が出てきます。枕草子では祝いの膳にゆずり葉を敷くことが書かれています。今から千年以上前からゆずり葉は存在しており、今でも縁起のいい葉として暮らしの中に溶け込んでいるのです。
この「ゆずり葉」というこの詩は、以前、国語の教科書(小学6年下巻)に載っていて、授業で習ったことを覚えています。「人ひとりの一生は儚(はかな)く、そして切ない。けれど、数珠繋ぎになることで命を繋ぎ、想いをつないでいるのだ」と授業で習いましたが、昨今の悲惨な国際紛争や貧困、不平等・格差、気候変動による影響など、人類が抱える問題を数えると、
「私たちは、どれだけのものを子どもに残していけるのだろう。」
「未来の子どもたちに、何を残していくことがいいことなのだろう。」
と、考えざるを得ません。
しない、させない、ゆるさない
水平社宣言(部分要約)
全国に散在する部落の人々よ、団結せよ。
ここに我々が人間を尊敬することによって、自らを解放しようとする運動を起こしたのは当然である。
我々は、心から人生の熱と光を求めるものである。
水平社はこうして生まれた。
人の世に熱あれ、人間に光あれ。
部落差別の根絶をめざし、当事者たちが立ち上がった全国水平社の創立から、今日2022年3月3日で100年を迎えました。この水平社宣言は日本初の人権宣言と言われ、社会のあらゆる人権問題の克服に向けた原点となってきました。
水平社は、差別された当事者が同情を乞うのではなく、自尊の精神を抱いて社会変革を訴えました。さらにその訴えを自分たちだけに閉ざさず、「人間を冒涜(ぼうとく)してはならぬ」とすべての人が、あらゆる差別を受けることなく、人間らしく暮らしていける社会の実現をめざしました。
しかし残念ながら、差別発言や差別待遇等のほか、現在も被差別部落をめぐっては結婚などの差別が残り、地名の一覧がネット上に掲載される事件や、差別を助長するような内容の書き込みがなされるなどの人権侵害事案が発生しています。差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
こうした状況の中、平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。この法律は「部落差別のない社会を実現すること」を目的としています。同和問題に対する誤った知識や思い込みは、解決を妨げます。
この100年を節目に、当時の人々の思いや願いを想像しながら、真に、人権が尊重される豊かな社会をつくるためにはどうしたらよいか、ぜひ一緒に考えていきましょう。
一人ひとりが同和問題を人権問題の重要な柱としてとらえ、水俣病をめぐる人権、ハンセン病回復者の人権など様々な差別について正しい知識をもち、差別を「しない」「させない」「許さない」という意識を持ち行動することで、差別のない社会を実現していきましょう。
ひな祭り
あかりをつけましょ(まちょ)
ぼんぼりに(ぼんぼいにぃ)
お花をあげましょ(ちょ)
桃の花(みょみょのはにゃ)
五人ばやしの(ばやちど)
笛太鼓(ぷえじゃいこ)
今日はたのしい(たのちい)
ひなまつり(まちゅり)
雛飾りの前で、おかっぱ髪の娘が嬉しそうに歌っているのを思い出しました。
3月3日はひな祭り。「桃の節句」「弥生の節句」ともいわれ、女の子の美しい成長と幸福を願うものです。この頃になると、雛人形や桜餅、雛あられを売る店先から、「うれしいひな祭り」が聞こえてきました。4番までぜんぶ歌えますか。私はうろ覚えで2番まででした。
【2番】
お内裏様(だいりさま)と おひな様
二人ならんで すまし顔
お嫁にいらした 姉様に
よく似た官女の 白い顔
【3番】
金のびょうぶに うつる灯(ひ)を
かすかにゆする 春の風
すこし白酒 めされたか
あかいお顔の 右大臣
【4番】
着物をきかえて 帯しめて
今日はわたしも はれ姿
春のやよいの このよき日
なによりうれしい ひなまつり
この歌の、優しくて些か切ない歌詞と美しい旋律は、やはり名曲です。
作詞者のサトウハチローさんは、詩人・童謡作家として「リンゴの唄」「ちいさい秋みつけた」など数々の名作を残しました。どの曲も世代を超えて歌い継がれています。
作曲者の河村光陽(かわむら こうよう)さんは、作曲家のかたわら音楽教師なども務め、「ほろほろ鳥」「かもめの水兵さん」「赤い帽子白い帽子」などの代表作があります。どれも覚えやすく、口ずさんで楽しい曲ばかりです。
孫娘が生まれたら(いつかな?)、倉庫に眠っている雛人形を引っ張り出して(倉庫の何処だっけ?)、飾ってやりたいと思います。
タブレット活用ルールについて
1、タブレットの持ち帰りルール(児童用)
2、ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)
3、タブレット五か条(児童用)
4、Wi-Fi接続の仕方
上記内容について、別添のとおり添付しています。正しくタブレットを活用できるよう、家族みなさんで確認してくだい。
〒866-0101
熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3
上天草市立姫戸小学校
TEL 0969-58-2068
FAX 0969-58-2147
E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp
URL http://es.higo.ed.jp/himedo/
*白嶽山頂からの眺望(碧い海の向こうに八代が見えます)

熊本県教育情報システム登録機関
管理責任者
校長 土屋 寛仁
運用担当者
教諭 濱﨑 伸太郞
栄養教諭 花田 千賀
学校情報化 優良校認定 (日本教育工学協会)