「やさしく・しっかり考え・たくましい南関三小っ子」が育つように学校と保護者、地域、南関町の教育行政のみなさんでウェルビーイングが循環する「地域とともにある学校」を目指しています。

「やさしく・しっかり考え・たくましい南関三小っ子」が育つように学校と保護者、地域、南関町の教育行政のみなさんでウェルビーイングが循環する「地域とともにある学校」を目指しています。
10月5日(木)に6年生はテレビ会議で,三小出身で元パラリンピックゴールボール日本代表の浦田理恵さんと交流しました。
きっかけは,総合的な学習の時間における調べ学習で,「浦田理恵さんのことをもっと知りたい!」という子どもたちの声でした。「浦田理恵さんに会って,直接お話を聞いたり質問をしたりしたい。」という子どもたちの気持ちに応えて,浦田さんが子どもたちとの交流を快く引き受けてくださいました。
テレビ会議を通しての交流となりましたが,浦田さんは子どもたちの様々な質問に丁寧に答えてくださいました。
交流会を通して,浦田さんの言葉からたくさんの学びがありました。勇気を出して,チャレンジすること,感謝の気持ちをもつこと,相手を知り,もっとなかよくなること・・・・・・子どもたちは,真剣なまなざしでいただいたメッセージを胸に刻んでいました。
6年生の算数では,「およその面積と体積」について学習を進めています。今回の授業では,身近にあるものの,およその面積や体積を求めました。
子どもたちは,教室にある学習用具や,廊下にある洗面台等,長さを測っておよその面積や体積を測定していました。友達と協力したり,意見を交わしたりしながら,わかったことをタブレット端末にまとめました。
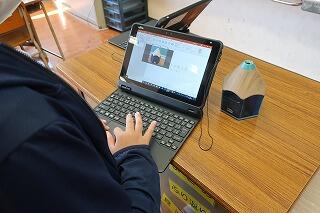
学習の中で,複雑な形は2つの立体に見立てて計算するといい,と考えついておよその体積を求めていました。学んだことを発揮するだけではなく,さらに学びを活かしてよりよい答えを導き出そうとする姿が見えました。
9月21日(木)は,6年生を対象にプログラミング教育の授業を実施しました。Springin’というアプリを使い,タブレット端末でくまモンを操作するゲームを作りました。

授業には,しくみデザイン(株)の方々や,熊本県知事公室のくまモングループの方々が,授業の準備,子どもたちへの指導やサポート等を進めてくださいました。

くまモンを動かして,障害物を避けてゴールへ進めるゲームを作成しました。子どもたちはイメージを広げながら,個性あふれるゲームをデザインしていました。ゲームがほぼ完成したとき,
なんと,くまモンが登場しました。
子どもたちが作ったゲームに挑戦するくまモン・・・なかなか難しく,悔しそうでした。ゲーム作りを通して,子どもたちはプログラミングの面白さに触れることができました。
6年生の算数の学習では,円の面積の公式を使って問題を解きました。
様々な形を組み合わせた図形の面積を,工夫して求めます。これまで算数で学んだことを活かして,考えをタブレット端末にまとめました。
子どもたちは,お互いに自分の考えを伝え合って交流することで,自分の考えをより深めていました。
電子黒板に考えを写して,発表しています。様々な考え方や解き方が出てきて,とてもおもしろい学習になりました。
5年生は米作りの学習の一環として,かかし作りをしました。

3グループに分かれ,それぞれどんなかかしを作るのか話し合い,デザインを決めました。みんなで協力し,役割分担をして作業を進めました。保護者の方々も応援に来てくださり,楽しいかかし作りの時間となりました。さて,どんなかかしができたでしょうか?
7月29日(土)に6年生は親子木工づくり体験活動を実施しました。永松建設の方々に協力していただいて,ベンチ,テーブル,うさぎの囲いを制作しました。
この体験活動は,「令和5年度 熊本県県民の未来につなぐ森づくり事業」の一環として実施されています。三小の学びの森から木材を調達し,学校に役立つものを制作しました。その仕上げとして,制作物に上記の事業名を記入しています。

てきぱき動く姿は,さすが6年生です。みんなで協力して制作を進めることができました。
7月29日(土)に6年生を対象に,親子木工づくり体験を実施しました。これは,「熊本県県民の未来につなぐ森作り事業」の一環として,本校の学校林の木を木材にして,永松建設の方々に加工していただきました。
今回作成したのは,ベンチ,テーブルとウサギの囲いです。永松建設の方々が加工してくださった木材を,子どもたちが組み立てたり塗装したりしました。


子どもたちはおうちの方と力を合わせて,テキパキと作業を進めていました。初めて体験することばかりで,とても楽しそうでした。
暑い中でしたが,とても楽しい体験活動でした。ご協力いただいた皆様,大変お世話になりました。ありがとうございました。
7月18日(火),6年生の子どもたちは家庭科の学習で,手洗いで洗濯をしました。どのように手洗いをするのか知り,実際にチャレンジしてみました。
バケツに水と洗濯石けんを入れ,体操服を洗濯しました。
しっかりしぼって水気を取ります。絞る作業がとても大変で,子どもたちは手洗い洗濯の大変さを実感するとともに,洗濯の仕組みについて知ることができました。
7月13日(木)は5年生の調理実習でした。今回のテーマは,「ゆでる」料理です。
今回は一人一実習で,オリジナルのゆで野菜サラダ作りをしました。
どのように野菜を切ればいいのか,どれくらいゆでればいいのか気をつけながら,とても楽しそうに活動していました。
できたサラダをみんなで「いただきます!」
栄養もバッチリ,味もバッチリで楽しい調理実習でした。
5,6年生の水泳の学習の様子です。現在,平泳ぎの練習をしています。

平泳ぎは,足の動かし方や息継ぎの仕方等,身につくまでなかなか難しい泳ぎ方です。子どもたちはお手本を見たり教え合ったりして練習を重ね,試行錯誤しながら平泳ぎの練習をがんばっています。
練習を繰り返しているうち,だんだんと上手になってきています。子どもたちの成長がすばらしいです。
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 村岡 英治
運用担当者
教諭 田川 昭太
〒861-0812
南関町立 南関第三小学校
TEL 0968-53-0101
FAX 0968-53-0140
E-mail nankan3-es@tsubaki.higo.ed.jp
URL https://es.higo.ed.jp/nankan3e/
※住所をクリックすると別ページで地図が開きます。