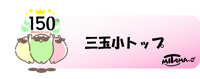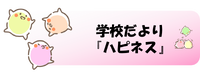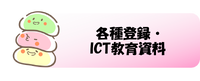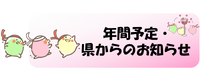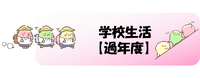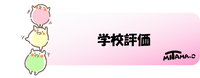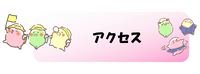給食
9月17日 水曜日
パインパン 牛乳 コンソメスープ タンドリーチキン ピーマンのじゃこ和え
タンドリーチキンは、ヨーグルトと香辛料に漬け込んだ鶏肉をタンドールと呼ばれる筒型の窯で焼くインド料理です。タンドールが変形してタンドリーチキンとなったようです。給食ではオーブンで焼いてあります。
9月16日 火曜日
麦ご飯 牛乳 豆乳味噌汁 牛肉のしぐれ煮 かりかり和え
「豆乳」は何から作られているか知っていますか?大豆から作られています。お味噌汁の「みそ」も大豆から作られています。お味噌汁に豆乳を入れるとまろやかな味になりますね。
9月12日 金曜日
丸パン 牛乳 コーンと卵のスープ 鶏肉のマスタード焼き イタリアンサラダ アセロラゼリー
給食で使っている鶏肉は、「もも」といわれる部分です。この「もも肉」の部分には貧血を予防してくれる鉄分が鶏肉の中で最も多く含まれています。まだまだ暑い日が続きそうです。しっかり栄養と睡眠をとって連休明けの火曜日も元気に登校しましょう!
9月11日 木曜日
麦ご飯 牛乳 肉じゃが 磯和え
「肉じゃが」は日本を代表する煮込み料理です。では、英語で話すとき、肉じゃがは何というか知っていますか?「Japanese beef and potato stew」などと言うことがあるようです。しかし、「tenpura」「sushi」のように「nikujyaga」でも通じるみたいです。
9月10日 水曜日
ミルクパン 牛乳 チキンビーンズ キビナゴフライ かぼちゃサラダ
かぼちゃは「カロテン」と言って体の中で「ビタミンA」にかわる栄養素を多く含んでいるので緑黄色野菜と言います。カロテンは免疫力アップや、目の健康にも効果があります。
9月9日 火曜日
麦ご飯 牛乳 鶏ごぼう汁 鯖ごま味噌煮 アーモンド和え
給食で汁物に入るごぼうは香りを出すために油で炒めています。そうすることによって、かつおや鶏肉のだしと一緒にごぼうの香りが出てさらに美味しくなります。
9月8日 月曜日
ハヤシライス 牛乳 フルーツヨーグルト
今日のハヤシライスは、玉ねぎをあめ色になるまでしっかり炒めていつもより長い時間煮込みました。毎日限られた時間の中で作っていますが、献立の組み合わせ次第ですが、時間をかけることができる時は時間をかけると美味しくできあがりますね!
9月5日 金曜日
栗ご飯 牛乳 すまし汁 鶏のさっぱり焼き もやしのごま和え
今月の「山鹿の日」の献立は栗ご飯です。
熊本県で有数の栗の産地である山鹿市。5~6月に白い小さな花が咲き、8月下旬から収穫の季節になりました。生産量が多いだけでなく、品質が良いと全国から高い評価もうけています。
今日の栗は、鹿本町の鹿子木農園さんの栗です。
9月4日 木曜日
麦ご飯 牛乳 夏野菜の味噌汁 魚の黄金焼き きゅうりとわかめの酢の物
魚の黄金焼きは クリームコーンとマヨネーズ、小麦粉を少し入れて混ぜてソースを作ります。ソースを魚にかけてオーブンで焼きます。オーブンで焼く前は、白いソースでしたがオーブンで焼くと黄金のような色になります。
9月3日 水曜日
ツナトースト 牛乳 肉団子と野菜の煮込み 豆腐サラダ
ツナトーストは、コーン・玉ねぎ・ツナをマヨネーズと混ぜて食パンの上にのせます。その上にチーズをのせてオーブンで焼きます。お家でもできそうですね!
9月2日 火曜日
麦ご飯 牛乳 汁ビーフン チンジャオロースー 春巻き シャインマスカット
今日は三玉校区にある社方園さんからシャインマスカットを頂きました。ビタミンCの栄養がとれ、とっても甘くて美味しかったです。三玉校区には色々な美味しい果物や野菜が作られています。地域の方に感謝していただきましょう。
9月1日 月曜日
親子どんぶり 牛乳 こんにゃくサラダ 黒糖大豆
お家でも良く食べられている親子丼ですが、この親子丼は、東京都の郷土料理です。東京にある料理屋さんで「とりすきやき」の残った汁の中に卵を入れてご飯と食べていたお客さんがいたことから考えられたそうです。
8月29日 金曜日
食パン 牛乳 五目うどん ツナサラダ みかんジャム
夏休みが終わっても まだ体調が整っていない人もいるようです。早起きをして朝の光を浴び、朝ご飯をしっかり食べる、夜は早く寝て十分な睡眠をとって生活のリズムを整えましょう。
8月28日 木曜日
麦ご飯 牛乳 豚肉のしょうが焼き 玉ねぎの味噌汁 野菜炒め
豚肉のしょうが焼きには、ビタミンやタンパク質の栄養が含まれいて、疲れを とってくれたり、貧血の予防、免疫力アップなどの色々な効果があります。
8月27日 水曜日
ナン 牛乳 キーマカレー ウィンナーと豆のスープ フレンチサラダ ぶどうゼリー
夏休みが終わりいよいよ2学期のスタートです。まだまだ暑い日が続いています。しっかり食事を摂って、元気に2学期の行事を頑張りましょう!
7月18日 金曜日
馬じゃこご飯 牛乳 豆腐のすまし汁 千草焼き れんこんサラダ
今月の「ふるさとくまさんデー」は、「熊本市」の味を紹介します。馬刺しで食べられている、馬肉を使った「馬じゃこ ご飯」、「からしれんこん」をイメージした「れんこんサラダ」です。
明日から、いよいよ夏休みですね!食生活のリズムを崩さないように規則正しい生活を心がけ、エネルギーをチャージして新学期に元気に登校できるようにしましょう!
7月17日 木曜日
セルフドッグ 牛乳 かぼちゃのポタージュ コールスローサラダ
かぼちゃは、βカロテンを多く含んでいます。βカロテンは体の中でビタミンAに変わり免疫力を高めてくれます。かぼちゃは、クリーミーなスープにすることで栄養をしっかり摂ることができます。
7月16日 水曜日
麦ご飯 牛乳 ビビンバ ナムル わかめスープ デザート
ビビンバは韓国でよく食べられている料理です。ごはんに ナムルと言って もやしや山菜をごま油で和えた物と 肉や卵をのせて、唐辛子の入った調味量などと よく混ぜて食べます。家庭では あり合わせの おかずに ご飯をのせて、醤油やキムチなどで自分の好みの味付けをして食べています。
7月15日 火曜日
丸パン 牛乳 八宝菜 しゅうまい あんこかし
あんこかしは、お盆にお備えするだんごです。ご先祖様の長旅をいたわり、疲れをいやしていただくという意味で、あんこやみたらしなどの甘い味付けのお団子をお供えします。
7月14日 月曜日
麦ご飯 牛乳 豚汁 じゃがたら ひじききくらげふりかけ
山鹿市は7月13日から15日までお盆になります。じゃがタラのタラは北海道などで獲れる魚で鮮度が落ちやすいため、身は干して棒鱈に、エラと内臓は鱈胃に加工され運ばれていました。昔は海の魚が手に入りにくく、たとえ干物であっても貴重品だったためお客が集まるお盆にごちそうとして出されていたのではないかと言われています。棒鱈は、骨が多いので気をつけて食べてください。
山鹿市立三玉小学校
〒861‐0522
熊本県山鹿市久原2935番地
TEL 0968-43-1177
FAX 0968-42-8410
E-mail y-mitamaes@leaf.ocn.ne.jp
URL https://es.higo.ed.jp/mitamaes/
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 北山 綾
運用担当者 塚原 聡