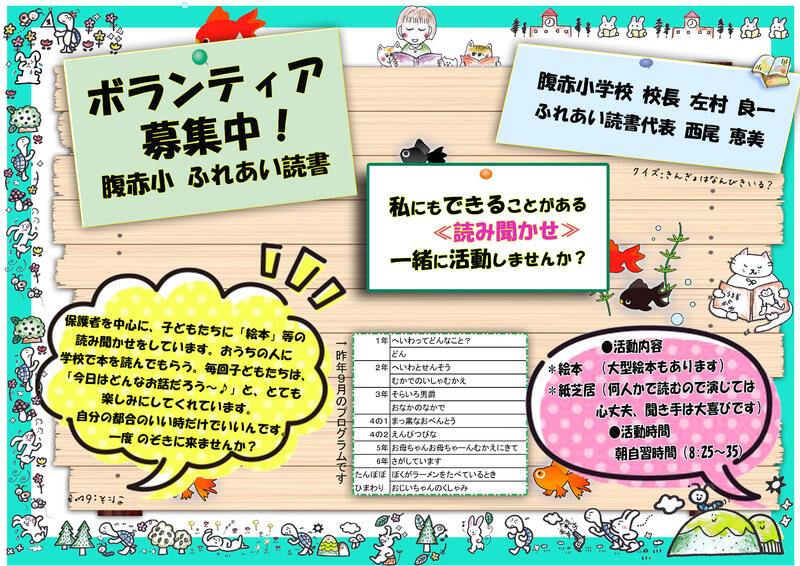季節のたより
梅雨入り
突然ですが「十薬」という名前をご存じですか?これは漢方薬の原料の一つです。江戸時代の医学者、貝原益軒の書物にも出てきます。
せっかくクイズ仕立てで書き始めましたので、ヒントを出しましょう。
ヒント1:日陰を好む植物である。
ヒント2:生命力が強く、抜いても抜いても生えてくる。
ヒント3:強烈な臭いで、手につくとなかなか消えない。
どうでしょう。1つめ、2つめのヒントでは、いくつも思い当たるものがあったでしょうが、3つ目のヒントで「あれか」と思われたかも知れません。
そうです、ドクダミです。建物の陰などのジメッとしたところで白い花を咲かせる植物です。
今回は,これからのシーズンの花とも言える「ドクダミ」について記してみたいと思います。
ドクダミは、様々な薬効成分を含んでいて、古くから民間薬としても重宝されている植物です。
しかし、「毒があるんですよね」とか「触るとかぶれるんですか」といったことを尋ねられたことがあるように、ドクダミの「ドク=毒」であまりよいイメージをもたれていないのも事実でしょう。
早速ですが、ドクダミの名の由来ですが、主なものとしては「毒溜め」「毒矯み」と漢字で書きます。
これは、それぞれ「毒を排出する」「毒を抑える」という意味から来ているそうです。
先に述べたように、十薬と呼ばれるだけあって、次のような様々な効能があると言われています。
◇化膿性の腫れ物:新鮮な葉を炙って患部に貼ると、膿を吸いだして腫れが引く。
◇擦り傷・靴擦れ:同上
◇利尿・便通・高血圧予防:ドクダミ茶にして飲む。
◇水虫:強い臭いの成分には抗菌性があるため、生の葉を患部にすり込む。
◇あせも:摘んだ葉を風呂に入れて薬浴する。
◇胃痛・十二指腸潰瘍:青汁にして飲む。
これらは、効き目の一部を紹介したものですが、あくまでも「そう言われている」ことですのでご了承ください。
また、効果には個人差があるでしょうし、ときには命にかかわることも起きかねないことについても申し添えておきます。
このドクダミの利用方法ですが、消臭剤として使うこともできます。
使い方は簡単です。ドクダミを摘んで室内につるしておくだけです。
気になるのは、あの強い臭いですが、乾燥するにつれて匂わなくなります。
私も実際にトイレにつるして試してみましたが、確かに消臭効果がありました。初日は独特の臭いがありましたが、徐々に薄れてその日の午後には気にならなくなりました。
これは、試してみる価値があります。
ドクダミに関することとして、気になるのは「食用にする」ことです。
ベトナムでは、ザウジエプカーと呼ばれるドクダミの仲間を香草として魚料理に使います。(ザウジエプカーとは、魚の野菜の葉という意味)何でも生の葉を使うそうですが、日本のものよりも香りは強くないと聞きました。
日本でも、加熱すると臭いが和らぐことから「てんぷら」に使ったり、茹でて「おひたし」にしたりする調理方法が伝えられています。まるで山菜のような扱われ方をするのですね。
降りしきる雨の中で、ドクダミの白い花は美しく見えます。梅雨の時期の風物として,しばらく楽しめそうです。
立夏
今日は「立夏」。季節はすっかり「夏の入り口」になりました。
臨時休業で、寂しい日々を送っています。早く子どもたちの元気な声が響き渡るように戻ることを祈るばかりです。
さて、腹赤小学校に来て4年を迎えましたが、今年はじめて理科室の軒下にツバメが巣作りをしています。
ツバメは、日本では古来から「益鳥」として大切にされてきた鳥です。その理由は,稲の害虫を食べ、米作りを助け守ってきたからです。
そのため、農村部ではツバメを傷つけたり,巣を壊したりすることを禁じて大切にしてきたようです。
また、人の出入りの多い場所を選んで巣をかけることから、商売繁盛の印にもなっています。
では、なぜツバメは,人の家の軒先などに巣をかけるのかということですが、一番の理由はツバメを襲う敵が近づきにくいためです。
彼らは面白い習性があって、オスが先に日本に渡ってきて、巣をかける場所を探すそうです。その後、メスが来て、オスの準備した巣が気に入ると、ペアができるそうです。
中には、早くにやって来たのに,いつまでも一羽で寂しそうにしているツバメがいますが、 それはオスで,メスに気に入られることのない巣を準備したせいだとのことです。
巣づくりについては、以前は「去年来たツバメが,今年も巣をかけた」といわれていましたが、必ずしもそうではなく、むしろ違うツバメがやって来ているという話も聞きました。
彼らは、スマートな体つきをしています。高速で飛行するのに適した構造になっています。ところが、「天は二物を与えず」と言われるように、ツバメの足はとても短いのです。
実際に地面に降りるのは,巣を作るときに材料である泥を求めるときだけです。(何と水を飲むときも,水面すれすれを飛んでいくのです。夏場、プールで見ることができます。)
実は、ツバメの鳴き声は「土食って虫食って口渋い」というふうに聞こえます。そのように鳴くようになった理由を紹介した民話があります。
昔、スズメとツバメは姉妹だった。彼らの親の死に目に際して、スズメはなりふり構わず駆けつけて間に合ったが、ツバメは身支度に時間をかけたため、間に合わなかった。
その様子を見ていた神様は、スズメには穀物でも何でも好きな物を食べることを許したが、ツバメには土と虫以外を食べてはならないとした。だから、今でもツバメは「土食って,虫食って口渋い」と鳴いているそうだ。
ところが、それだけ人とのかかわりが深かったツバメですが、激減しているといわれています。
その理由は、大きく3つあげられています。
①巣をかける家が減った
そもそも、ツバメが好むのは周囲でエサがたくさんとれ、巣材も豊富な里山の軒がある家屋です。ところが、近年の家はつるんとした壁が多くなり、巣をかけるのが難しいためだと言われています。
②天敵が巣を襲うようになった
一番の天敵はカラスです。カラスは,巣を襲いツバメの雛を奪っていきます。カラスをかばう気は全くありませんが、彼らも自分の子育てのためにツバメを奪うようです。何とも言えない悲しい話です。
近年、人間の生活圏でカラスが増えていますが、原因は人間の捨てるゴミを餌にしているためであるとも言われています。
③エサが減った
ツバメたちは、3000〜7000kmもの距離を,命がけで渡ってきます。それは、春から夏にかけての日本にはエサとなる昆虫が豊富で,子育てに適しているからです。
ところが、田畑の宅地化や河川の護岸化、農薬の使用、耕作放棄地の増加によって,エサとなる昆虫が減ってきています。
「日本野鳥の会」の調査によると、親鳥は1日に520回も雛にエサを運んだといいます。ということは、昆虫の減少は、死活問題になります。
先日は、理科園にジャガイモの種芋を植えました。6年生の理科の教材です。登校日には、子どもたちと種まきをしたいと思います。
ミツバチ
パンジーなど校内の花壇をはじめ、あちらこちらに美しい花が咲きみだれています。
次々と花が咲くこのころ、花を訪れるミツバチの姿が目につきます。足に花粉団子をつけて花をめぐる姿には「頑張っているなあ」と感嘆の声が出るほどです。
ハチというとどうしても、毒をもっていて危険だという先入観がありますが、ミツバチは穏やかで,よほどのことがなければ攻撃される(針で刺される)ことはありません。
日本にはミツバチが2種類います。1つは、もともと日本で暮らしていたニホンミツバチ。もう1つは,明治時代にヨーロッパから持ち込まれたセイヨウミツバチです。
ニホンミツバチは、1匹の女王蜂に対して、
働き蜂は、巣の外に出かけストローのような口と体中を覆う毛を使って上手に花の蜜や花粉を集め、巣に運びます。
ここで素晴らしいのは,彼らは花までの距離や方角をダンスで仲間に伝えるということです。円形ダンスと八の字ダンスがあり、餌場が近いときには円形ダンス、遠いときには八の字ダンスを踊って伝えるそうです。しかも踊りのスピードで,どれくらい離れているかということまで伝えるそうです。
働き蜂の仕事は、食料の調達だけではありません。巣を快適に保つことも重要な仕事です。
巣の出入り口で,羽を震わせて外の新鮮な空気を巣の中に送り込んだり、時には水を口に含んで巣の中に打ち水したりして巣内の温度を下げることまでするようです。
働き蜂の重要な働きは、もう一つあります。
それは、巣の防衛です。
ミツバチの天敵の一つが「スズメバチ」です。
スズメバチはミツバチを捕獲し、彼らの幼虫の餌にします。
さて、ニホンミツバチたちは、スズメバチが現れるとどのようにして防御するかというと、スズメバチに対して,瞬く間に数百匹もの働き蜂がおおいかぶさり、塊をつくります。
そして、羽を震わせながら熱をつくり出してスズメバチの体を作るタンパク質を崩壊させます。(つまり、熱で殺してしまうのです。我々の使っている体温計も42度までしか目盛りがありませんが、それはそれ以上を測る必要がないということなのです。)
このようにしてニホンミツバチは、集団で敵を撃退します。ではセイヨウミツバチはというと、どうも単独で立ち向かうため,次々にスズメバチにやられてしまうようです。
なぜ、同じミツバチで違いがあるのか?
それは、セイヨウミツバチの故郷であるヨーロッパにはスズメバチがいないため、撃退する術をもっていないのです。
ミツバチにも、長い年月をかけて培った文化(習性)があるのですね。
近年、ミツバチを使った地域活性化の取り組みがあります。
その名は「銀座ミツバチプロジェクト」というものです。何と東京のど真ん中である銀座で養蜂を行っているのです。
その趣旨は、「ミツバチによって自然と共生できる銀座の街に出合ったのです。自然を排除しない。自然と共生できる。素晴らしいものに出合った!自然を受けとめる。それによって街はもっとうるおいを持つ。生活は豊かになる。採れた蜂蜜を銀座の“技”で商品にする」(プロジェクト世話人の田中淳夫氏)というものです。ミツバチは環境指標生物。ミツバチの住める都市は安全な都市といえます。ハチ、イコール“安全”のシンボルというわけです。
この取り組みは平成18年3月28日(ミツバチの日)に始まり、日本全国にも拡大しているそうです。
花壇のチューリップ

色とりどりのチューリップの花が咲き誇っています。
冬の寒さをしっかり感じると、茎を伸ばして花をつけるそうです。
桜
3月の「季節のたより」では、熊本地方の桜は3月21日ごろ開花予定であると伝えられている旨をお知らせしましたが、実際には、それより遅れて花が開きました。
その後、暖かい日があったかと思うと冷え込みが戻ってきたせいで、花が長持ちしました。
花がいつ頃までもつかを判断するコツがあるそうです。さて、どんなコツでしょうか。
それは、花の色の変化を見るとよいそうです。実際に,咲き始めの花の色は「白」です。白は白でも輝くような白で、少しばかり強い風にさらされても散ることはありません。
ところが、日が経つにつれて,花の色が「ピンク」に変わってきます。
小さな花一つ一つの変化も、たくさん集まると大きな変化に見えます。
ですから、散りかけは、サクラの枝の色合いの変化で分かるというわけです。
さて、サクラと一口にいっても日本国内には10種類あります。ただし、これらは自生種といって「人の手によって育成されたものではない」種類です。有名なのは「ヤマザクラ」です。花が咲くのと同時に葉も開きます。山間部などでよく見ることができます。
園芸種は400種類を越えるとも言われます。ソメイヨシノはその一つです。
以前「ブラタモリ」という番組で、ソメイヨシノが取り上げられたことがあります。そのときの内容をまとめると次のようなものでした。
●江戸時代末から明治初期に,江戸染井村あたりの造園業者・植木職人によって育成された。
●江戸染井村は、現在の東京都豊島区駒込あたりである。
●エドヒガンとオオシマザクラの雑種である。
●そもそもは、「吉野桜」という名前をつけていた。
●これは、サクラの名所である奈良県の吉野山にちなんだものらしい。
●ところが、本家の吉野桜と種類が違うことが分かった。
●このまま「吉野桜」という名前をつけておくと、誤解が発生するため名称変更をすることにした。
●そこで染井村の名前をとって「ソメイヨシノ」と名付けた。
ソメイヨシノは、花が先に開き、華やかさがあることから人気があるサクラです。学校や公園などにもたくさん植えられています。
しかし、種が取れず,接ぎ木で育てるため、病気にかかりやすいとも言われています。
「ソメイヨシノ60年寿命説」という俗説が20年ほど前話題になったことがありました。その説の起こりは「ソメイヨシノの成長が早い分、老化も早い」とか「接ぎ木をした台木が腐りやすくなる」とか、これまた諸説がありました。
実際には、樹齢100年を越える老木も存在しているようなので、最近は話題に上がらなくなったようです。
さて、サクラの花が散り始めて「春たけなわ」になりました。
残念ながらコロナウイルス感染を防ぐために、休校になります。でも、たまには外に出て新鮮な空気と美しい春の景色を味わってほしいと思います。