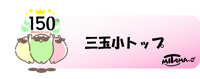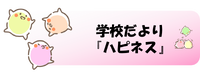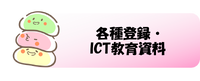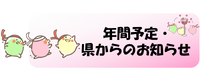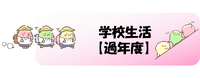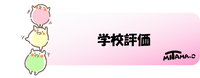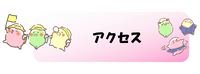給食
11月5日 水曜日
ミルクパン 牛乳 かぶのスープ 鶏肉のコーンフレーク焼き 豆とわかめのサラダ
今日は初めての鶏肉のコーンフレーク焼きです。鶏肉に塩・こしょうをしてマヨネーズで下味をつけておきます。少し崩したコーンフレークと粉チーズ・パン粉を衣にしてオーブンで焼きました。お家でもできそうですね!
11月4日 火曜日
ご飯 牛乳 高野豆腐の卵とじ コロッケ ごまみそ和え
高野豆腐は、豆腐を凍らせてから乾燥してあるため豆腐と同じようにたくさんの栄養を含んでいます。特に骨を丈夫にしてくれるカルシウムや貧血になりにくくしてくれる鉄、体の成長に必要な亜鉛 などの不足しがちなミネラルを多く含んでいます。
10月31日 金曜日
からいもご飯 牛乳 豆腐汁 梅かつお和え かぼちゃのカップケーキ
『ルルとララのカップケーキ』 あんびるやすこ/作
『ぐりとぐらとすみれちゃん』 なかがわりえこ/作
Trick or Treat!
今日はハロウィンです。ということで、かぼちゃを使ったメニュー「かぼちゃのカップケーキ」です。
ハロウィンは秋の収穫祭を祝い、悪霊を追い払うお祭りで、ジャック・オー・ランタンと呼ばれるかぼちゃのちょうちんを飾ったり、仮装を楽しんだりします。 みなさんも、かぼちゃのカップケーキでハロウィン気分を味わってくださいね。
みなさん、今年の物語とコラボしたスペシャルな給食はいかがでしたか?初めて食べるメニューもあって楽しかったですね。給食の先生たちにぜひ感想を聞かせてください。
おいしそうな料理が出てくる本は他にもたくさんあります。ぜひ読んでみてください。そして、自分で作ってみるのも楽しいかもしれませんね。
10月30日 木曜日
麦ご飯 牛乳 わかめスープ たこ焼きフライ もやしのナムル
『青空小学校いろいろ委員会 給食委員はアイドル』 小松原浩子/作
三玉小で大人気の『青空小学校いろいろ委員会』全10巻のシリーズの中から、読んだことがある人は気になってしょうがない「たこやきフライ」です。
小学生モデルとして活躍中のクールなアイドル、ルミがゆいいつ活動的になるのは給食の時間。食べるのが大好きなルミの愛してやまないのが、青空小学校でも人気ナンバーワンの「たこやきフライ」なのです。
さてさて、「たこやきフライ」とはどんなお味なのでしょうか?三玉小でも人気メニューナンバーワンになるのでしょうか?
10月29日 水曜日
ヨーグルトポムポム 牛乳 豚肉と野菜の煮込み コーンサラダ
『マドモアゼルいくこの秘密のケーキ作り』
この本は、三玉小にはありません。山鹿市の図書館にも、熊本県内にある大きな図書館にもありませんでした。そんな謎に包まれた本に書かれた、謎の「ヨーグルトポムポム」・・・。
「ポム」はフランス語で「りんご」という意味だそうです。ヨーグルトとリンゴを使った食べ物・・・スイーツでしょうか?ほとんどの人が初めて食べると思います。お楽しみに・・・
10月28日 火曜日
セルフおにぎり 牛乳 お野菜つみれ汁 照り焼きチキン 昆布和え
炊きたてのご飯に梅干しや昆布、塩さけなどの具材をいれ、三角や俵型ににぎった食べ物、そう今日はおにぎりです。日本人がお米を作りはじめたおよそ2000年前の弥生時代から作られ、食べられているおにぎり。日本各地色々なおにぎりがあり、今では世界中でもおにぎりが愛され、食べられています。ちなみに、コンビニで売られているおにぎり人気ナンバー1はツナマヨだそうですよ。
おにぎりが出てくるお話は『おむすびころりん』『パンどろぼうおにぎりぼうやのたびだち』などたくさんありますが、あなたのお気に入りの本はありますか?
今日は梅干しとのりのおにぎりです。しっかりにぎって食べてくださいね。
10月27日 月曜日
麦ご飯 牛乳 麩汁 鰯のおかか煮 ポテトチップスサラダ
今年の読書週間は10月27日から11月9日までとなっています。給食では今週 1週間 本にちなんだメニューを取り入れています。みんなが読んだことがある本はあるかな?本の紹介は図書の竹下先生が書いてくれています。
『せかいでさいしょのポテトチップス』 アン・ルノー/文
料理好きなクラムさんのいたずら心と、がんこでかわりもののお客さんから生まれたポテトチップス。アメリカで実際にあった、ポテトチップス誕生の物語です。残念ながらこの本は三玉小にはありませんが、じゃが芋をうすーくスライスしてパリパリに」揚げられたおいしいポテトチップスをサラダと一緒に味わってくださいね。
10月24日 金曜日
ミルクパン 牛乳 ジュリアンスープ チリコンカン フルーツ白玉
チリコンカンは、ひき肉や細かく切った玉ねぎや野菜などを炒めて豆やトマト、チリパウダーを加えて煮込んだ料理です。
メキシコ料理が由来とされていて、アメリカの郷土料理として古くから親しまれ「チリ・コン・カーニ」や「チリ・コン・カルネ」と呼ばれることもあります。
10月23日 木曜日
麦ご飯 牛乳 かきたま汁 ほきのみそマヨ焼き お浸し
お浸しは、野菜を浸す料理です。いつもの和え物やサラダと違って今日は茹でた野菜を水で冷やして かきたま汁のだし汁と醤油に、しばらく浸しています。
10月22日 水曜日
熊本県産とまとパン 牛乳 秋野菜のシチュー ビーンズサラダ オレンジゼリー
今日の熊本県産トマトパンは、熊本県の八代市で収穫されたはちべえトマトが使われています。熊本の食材を使って熊本県で開発されたパンです。
10月21日 火曜日
文楽めし 牛乳 いちょう葉汁 厚焼き卵 にらの酢味噌和え
今月の「ふるさとくまさんデー」は上益城地区です。
山都町の清和地区には人形劇である清和文楽が残っています。この文楽を観るときに食べていたのが山菜を入れた炊き込みご飯「文楽めし」です。
10月20日 月曜日
麦ご飯 牛乳 さつま汁 きのこソースハンバーグ ほうれん草の和え物
きのこは、1年中出回っていますが秋が旬と言われています。きのこは湿気と涼しい気候を好むため朝晩が冷え込み、空気中に適度な湿度がある10月が収穫するのに最適な環境なのです。
10月17日 金曜日
麦ご飯 牛乳 なめこの味噌汁 とんかつ 和風サラダ 青リンゴゼリー
いよいよ明日は運動会ですね!赤団も白団もカツを食べて勝つように練習の成果を発揮しましょう!
10月15日 水曜日
照り焼きチキントースト 牛乳 卵スープ ささみのごまだれサラダ みかん果汁
照り焼きチキントーストは、小さく切ってある鶏肉で照り焼きを作ります。それを食パンの上にのせ、その上にとろけるチーズ、きざみのり、マヨネーズをのせてオーブンで焼きます。いつもよりちょっと豪華なトーストになりますね!
10月14日 火曜日
麦ご飯 牛乳 豆腐の味噌汁 鮭の塩焼き ひじきサラダ
問題です!魚の卵でお寿司屋さんでも大人気!鮭の卵は何かな?
答えは・・・いくらです。
10月10日 金曜日
食パン 牛乳 きつねうどん ごぼうサラダ ブルーベリージャム
10月10日は目の愛護デーです。数字の10と10を横にすると目とまゆの形に見えることから制定された記念日です。私たちの生活は、知らず知らずのうちに目をたくさん使っています。しかし疲れ目をそのままにしていると、視力が低下したり、頭痛や肩こりといった症状が現れることがあります。姿勢や部屋の明るさに注意し、時間を決めて目を休めるようにしましょう。
目に良い食べ物は、ビタミンA・カロテンを多く含む人参・ほうれん草・うなぎ・レバーなど、アントシアニンを多く含むブルーベリー・ぶどう・なすなどです。これらの食べ物を上手に取り入れながらバランスのとれた食生活を心がけましょう。
10月9日 木曜日
麦ご飯 牛乳 チキンカレー 海藻サラダ 晩柑ゼリー みかん果汁
今日から運動会までの間、5回みかん果汁があります。みかん果汁は、運動会の練習で汗をかいた後の水分補給、日に焼けた肌の回復のためのビタミンCをとることができます。
10月8日 水曜日
揚げパン 牛乳 タイピーエン ツナマヨサラダ うまかってん
みんなが大好き揚げパン!揚げパンは、パン屋さんが届けてくれたコッペパンを給食室のフライヤーで揚げます。きな粉と黒砂糖を混ぜ合わせた物を油で揚げたコッペパンにまぶしてできあがり。給食室で揚げてあるので、揚げたてを食べることができるのでふわふわですね!
10月7日 火曜日
麦ご飯 牛乳 大豆の磯煮 いわしの梅の香揚げ かつお和え
こいわしは、骨ごと食べることができるのでカルシウムをたくさん摂ることができます。運動をして骨に刺激を与え、カルシウムを摂り、太陽の光を浴びることで丈夫な骨を作ることができます。
10月6日 月曜日
麦ご飯 牛乳 里芋の味噌汁 さんまの生姜煮 ゆかり和え
十五夜は「いも名月」や「中秋の名月」と呼ばれます。だんごやススキを飾り、月を愛でる行事です。だんごが供えられるようになったのは江戸時代の後半頃だと言われていて、それまではさといもを供えていたと言います。十五夜は秋の収穫を祝う行事でもあり、柿や栗なども供えています。
10月3日 金曜日
麦ご飯 牛乳 けんちん汁 魚のにんにくソースがけ 昆布のさっぱり和え
魚のニンニクソースがけは、ホキという魚に米粉と小麦粉を混ぜた粉をつけて油で揚げます。その上にねぎがたっぷり入ったニンニクソースがかけてあります。魚料理の中では人気のメニューです。
10月2日 木曜日
麦ご飯 牛乳 豆腐のすまし汁 鶏肉のナッツ焼き 竹輪のごま和え
鶏肉のナッツ焼きは、鶏肉を赤みそ・砂糖・しょうゆ・お酒・みりん・生姜に漬け込んでおきます。焼く前に、ナッツをころものようにしてつけてオーブンで焼きます。ナッツの香ばしさを感じることができ、油を使っていないのでヘルシーな料理になります。
10月1日 水曜日
コッペパン 牛乳 きのこスパゲッティ コールスローサラダ
気持ちのよい秋空が広がる季節になりました。秋は「芸術の秋」、「スポーツの秋」と言われるように色々なことにじっくり取り組むことができる季節でもあります。
そして「味覚の秋」と言われるように、さつまいも、栗、きのこ類など今が旬の食べ物がたくさんあります。実りの秋に感謝しながら美味しい秋の味覚を楽しみましょう。
9月30日 火曜日
麦ご飯 牛乳 みそバター汁 ホキと豆の揚げがらめ
今日はいつもの味噌汁にバターを加えてあります。みそとバターのコクが溶け込み風味が豊かになります。
9月29日 月曜日
麦ご飯 牛乳 キムチスープ プルコギ
プルコギは、お肉とたくさんの野菜を甘辛味で炒め煮にした韓国料理です。日本の焼き肉と言うより、すき焼きに似ている料理です。韓国ではプルは「火」、コギは「肉」という意味です。
9月26日 金曜日
チーズパン 牛乳 コーンクリームスープ 魚のレモン煮 かみかみ大豆サラダ
レモンにはたくさんのビタミンCが含まれています。ビタミンCはお肌の調子を整え、風邪の予防にも効果があります。レモンの酸っぱいクエン酸には疲れた体を回復する働きがあります。
土曜日・日曜日はしっかり休んで、月曜日には元気に登校しましょう!
9月25日 木曜日
ガパオライス 牛乳 春雨スープ 桃のタルト
ガパオライスはタイ料理の「パッガパオガイ」という料理をもとに、日本人が食べやすいようにアレンジした料理です。発祥はタイですが、ガパオライスは日本特有の料理名です。「ガパオ」とはバジルというハーブの種類のホーリーバジルのことを言います。ガパオライスは日本語で「バジルご飯」という意味になります。給食では乾燥バジルを使用しています。
9月24日 水曜日
ミルクパン 牛乳 ラビオリスープ スパニッシュオムレツ 梨
今日の梨は荒尾市で収穫された梨です。梨は、多くの水分が含まれています。その中に天然の甘みが加わって、甘くてジューシーな果物です。食物繊維も多く含まれているのでおなかの調子を整えてくれます。
9月22日 月曜日
麦ご飯 牛乳 鶏肉のごま味噌煮 ししゃもの香焼き 南関揚げの酢の物
ししゃもには、骨や歯を丈夫にしてくれるカルシウムがたくさん含まれています。骨まで食べることができるのでカルシウムを体に取り入れるには最適な食べ物です。
9月19日 金曜日
麦ご飯 牛乳 つぼん汁 鯖のカレー揚げ 梨サラダ
今月の「ふるさとくまサンデー」は「人吉・球磨」地域の紹介です。「つぼん汁」は毎年10月に行われる おくんち祭りなどの お祝いのときに食べています。「つぼ」と呼ばれる深いお椀に入れて食べられていた「つぼの汁」がやがて「つぼん汁」と呼ばれるようになりました。
9月18日 木曜日
ひじきキムチチャーハン 牛乳 じゃが芋の煮物 即席漬け
ひじきキムチチャーハンに入っている「ひじき」には、貧血を予防してくれる鉄分、骨を丈夫にするカルシウム、おなかの調子を整えてくれる食物繊維がたくさん含まれています。
9月17日 水曜日
パインパン 牛乳 コンソメスープ タンドリーチキン ピーマンのじゃこ和え
タンドリーチキンは、ヨーグルトと香辛料に漬け込んだ鶏肉をタンドールと呼ばれる筒型の窯で焼くインド料理です。タンドールが変形してタンドリーチキンとなったようです。給食ではオーブンで焼いてあります。
9月16日 火曜日
麦ご飯 牛乳 豆乳味噌汁 牛肉のしぐれ煮 かりかり和え
「豆乳」は何から作られているか知っていますか?大豆から作られています。お味噌汁の「みそ」も大豆から作られています。お味噌汁に豆乳を入れるとまろやかな味になりますね。
9月12日 金曜日
丸パン 牛乳 コーンと卵のスープ 鶏肉のマスタード焼き イタリアンサラダ アセロラゼリー
給食で使っている鶏肉は、「もも」といわれる部分です。この「もも肉」の部分には貧血を予防してくれる鉄分が鶏肉の中で最も多く含まれています。まだまだ暑い日が続きそうです。しっかり栄養と睡眠をとって連休明けの火曜日も元気に登校しましょう!
9月11日 木曜日
麦ご飯 牛乳 肉じゃが 磯和え
「肉じゃが」は日本を代表する煮込み料理です。では、英語で話すとき、肉じゃがは何というか知っていますか?「Japanese beef and potato stew」などと言うことがあるようです。しかし、「tenpura」「sushi」のように「nikujyaga」でも通じるみたいです。
9月10日 水曜日
ミルクパン 牛乳 チキンビーンズ キビナゴフライ かぼちゃサラダ
かぼちゃは「カロテン」と言って体の中で「ビタミンA」にかわる栄養素を多く含んでいるので緑黄色野菜と言います。カロテンは免疫力アップや、目の健康にも効果があります。
9月9日 火曜日
麦ご飯 牛乳 鶏ごぼう汁 鯖ごま味噌煮 アーモンド和え
給食で汁物に入るごぼうは香りを出すために油で炒めています。そうすることによって、かつおや鶏肉のだしと一緒にごぼうの香りが出てさらに美味しくなります。
9月8日 月曜日
ハヤシライス 牛乳 フルーツヨーグルト
今日のハヤシライスは、玉ねぎをあめ色になるまでしっかり炒めていつもより長い時間煮込みました。毎日限られた時間の中で作っていますが、献立の組み合わせ次第ですが、時間をかけることができる時は時間をかけると美味しくできあがりますね!
9月5日 金曜日
栗ご飯 牛乳 すまし汁 鶏のさっぱり焼き もやしのごま和え
今月の「山鹿の日」の献立は栗ご飯です。
熊本県で有数の栗の産地である山鹿市。5~6月に白い小さな花が咲き、8月下旬から収穫の季節になりました。生産量が多いだけでなく、品質が良いと全国から高い評価もうけています。
今日の栗は、鹿本町の鹿子木農園さんの栗です。
9月4日 木曜日
麦ご飯 牛乳 夏野菜の味噌汁 魚の黄金焼き きゅうりとわかめの酢の物
魚の黄金焼きは クリームコーンとマヨネーズ、小麦粉を少し入れて混ぜてソースを作ります。ソースを魚にかけてオーブンで焼きます。オーブンで焼く前は、白いソースでしたがオーブンで焼くと黄金のような色になります。
9月3日 水曜日
ツナトースト 牛乳 肉団子と野菜の煮込み 豆腐サラダ
ツナトーストは、コーン・玉ねぎ・ツナをマヨネーズと混ぜて食パンの上にのせます。その上にチーズをのせてオーブンで焼きます。お家でもできそうですね!
9月2日 火曜日
麦ご飯 牛乳 汁ビーフン チンジャオロースー 春巻き シャインマスカット
今日は三玉校区にある社方園さんからシャインマスカットを頂きました。ビタミンCの栄養がとれ、とっても甘くて美味しかったです。三玉校区には色々な美味しい果物や野菜が作られています。地域の方に感謝していただきましょう。
9月1日 月曜日
親子どんぶり 牛乳 こんにゃくサラダ 黒糖大豆
お家でも良く食べられている親子丼ですが、この親子丼は、東京都の郷土料理です。東京にある料理屋さんで「とりすきやき」の残った汁の中に卵を入れてご飯と食べていたお客さんがいたことから考えられたそうです。
8月29日 金曜日
食パン 牛乳 五目うどん ツナサラダ みかんジャム
夏休みが終わっても まだ体調が整っていない人もいるようです。早起きをして朝の光を浴び、朝ご飯をしっかり食べる、夜は早く寝て十分な睡眠をとって生活のリズムを整えましょう。
8月28日 木曜日
麦ご飯 牛乳 豚肉のしょうが焼き 玉ねぎの味噌汁 野菜炒め
豚肉のしょうが焼きには、ビタミンやタンパク質の栄養が含まれいて、疲れを とってくれたり、貧血の予防、免疫力アップなどの色々な効果があります。
8月27日 水曜日
ナン 牛乳 キーマカレー ウィンナーと豆のスープ フレンチサラダ ぶどうゼリー
夏休みが終わりいよいよ2学期のスタートです。まだまだ暑い日が続いています。しっかり食事を摂って、元気に2学期の行事を頑張りましょう!
7月18日 金曜日
馬じゃこご飯 牛乳 豆腐のすまし汁 千草焼き れんこんサラダ
今月の「ふるさとくまさんデー」は、「熊本市」の味を紹介します。馬刺しで食べられている、馬肉を使った「馬じゃこ ご飯」、「からしれんこん」をイメージした「れんこんサラダ」です。
明日から、いよいよ夏休みですね!食生活のリズムを崩さないように規則正しい生活を心がけ、エネルギーをチャージして新学期に元気に登校できるようにしましょう!
7月17日 木曜日
セルフドッグ 牛乳 かぼちゃのポタージュ コールスローサラダ
かぼちゃは、βカロテンを多く含んでいます。βカロテンは体の中でビタミンAに変わり免疫力を高めてくれます。かぼちゃは、クリーミーなスープにすることで栄養をしっかり摂ることができます。
7月16日 水曜日
麦ご飯 牛乳 ビビンバ ナムル わかめスープ デザート
ビビンバは韓国でよく食べられている料理です。ごはんに ナムルと言って もやしや山菜をごま油で和えた物と 肉や卵をのせて、唐辛子の入った調味量などと よく混ぜて食べます。家庭では あり合わせの おかずに ご飯をのせて、醤油やキムチなどで自分の好みの味付けをして食べています。
7月15日 火曜日
丸パン 牛乳 八宝菜 しゅうまい あんこかし
あんこかしは、お盆にお備えするだんごです。ご先祖様の長旅をいたわり、疲れをいやしていただくという意味で、あんこやみたらしなどの甘い味付けのお団子をお供えします。
山鹿市立三玉小学校
〒861‐0522
熊本県山鹿市久原2935番地
TEL 0968-43-1177
FAX 0968-42-8410
E-mail y-mitamaes@leaf.ocn.ne.jp
URL https://es.higo.ed.jp/mitamaes/
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 北山 綾
運用担当者 塚原 聡