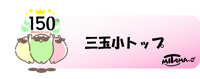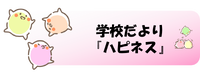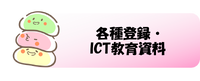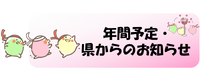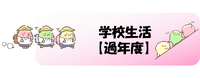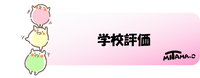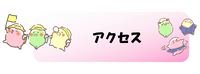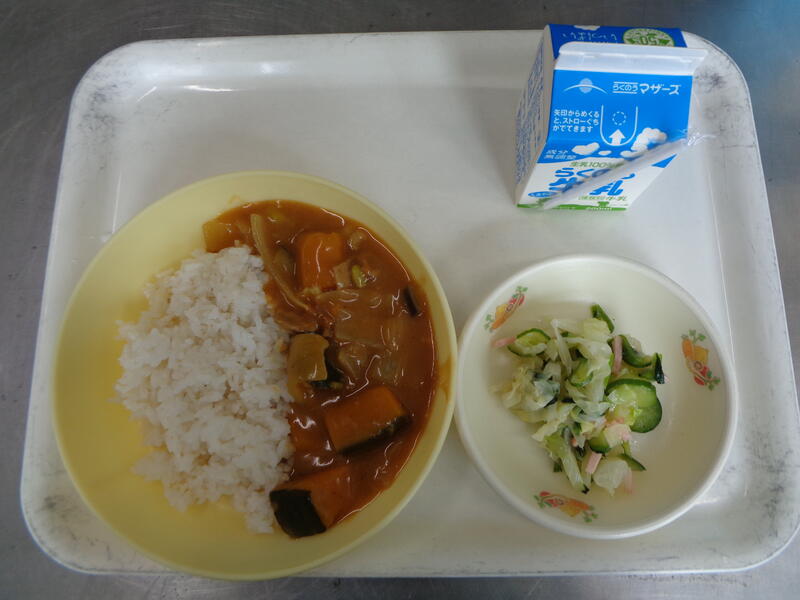給食
10月30日 水曜日
コッペパン 牛乳 ひじきスパゲッティ ごぼうとナッツのサラダ
和食料理によく使われているひじきを、スパゲッティと組み合わせると醤油で味をつけているので和風スパゲッティみたいになりますね。給食で使用しているひじきは、「芽ひじき」と言ってひじきの葉っぱにあたる部分です。「姫ひじき」とも呼ばれています。細く小さいため料理がしやすい種類です。
10月29日 火曜日
麦ご飯 牛乳 筑前煮 きゃべつのごま和え
筑前煮は福岡県の郷土料理です。鶏肉とごぼう・れんこん・人参・こんにゃくなどを油で炒め、醤油・みりんなどで甘辛く煮こみます。福岡県では「がめ煮」と呼ばれお正月やお祭り、結婚式などのお祝いごとの時によく作られます。
10月28日 月曜日
麦ご飯 牛乳 さつま汁 鯖のごま味噌煮 野菜の甘酢和え
さつま汁は、鹿児島県の郷土料理で鶏肉の入った具だくさんのみそ汁です。鹿児島県は昔、鶏の雄を戦わせる競技が盛んでした。その戦いに負けた鶏をその場でしめ、野菜と一緒に煮込んで食べたのがはじまりと言われています。
10月24日 木曜日
麦ご飯 牛乳 かぼちゃのみそ汁 鯖のソース煮 五色和え
かぼちゃは、βカロテンやビタミンC、食物繊維などがたくさん含まれていて栄養価が高い食べ物です。特にβカロテンは、体の中でビタミンAに変わり視力の維持や免疫力を高める働きをしてくれます。
10月23日 水曜日
甘酒とお芋の蒸しパン 牛乳 肉団子と春雨のスープ
甘酒とお芋の蒸しパンは、小麦粉とケーキミックス・ベーキングパウダー・砂糖・甘酒を混ぜてちょうどいい固さになるまで水を加えます。その中に切ったさつまいもを加えカップに入れて蒸し器で蒸します。給食では約200個の蒸しパンを作りました。甘酒が入っているので生地がもっちりして、甘さがひかえめなのでさつまいもの甘みが感じられますね!
10月18日 金曜日
文楽めし 牛乳 いちょう葉汁 和風サラダ
今月の「ふるさとくまさんデー」は「上益城地区」の献立です。山都町の清和地区には人形劇である清和文楽が残っています。この文楽を観るときに食べていた山菜を入れた炊き込みご飯が「文楽めし」です。
10月17日 木曜日
麦ご飯 牛乳 家常豆腐 中華和え
チャーチャン豆腐と麻婆豆腐の違いは揚げた豆腐、厚揚げが使われているというとこです。どちらも中華料理ですがチャーチャン豆腐は漢字で「家・常・豆腐」と書きます。いつも家で食べられているメニューでそれぞれの家で違ったレシピを持っているそうです。豆腐を揚げた厚揚げと、お野菜を一緒に炒めた料理なので栄養バランスがいいですね!
10月16日 水曜日
コッペパン 牛乳 高野豆腐のスープ チリコンカン ごまドレサラダ
今日から3日間、みかんジュースがあります。みかんジュースにはたくさんのビタミンCが含まれています。ビタミンCには、体を動かすエネルギーを作る役割や、日焼けした肌を整えようとするはたらきがあります。
運動会本番まであと少しです。
「かがやけ 笑顔 頑張れ 三玉 150」 運動会が楽しみですね!
10月15日 月曜日
菜めし 牛乳 かきたま汁 小イワシの梅の香揚げ きゅうりとわかめの酢の物
小イワシフライのように小魚を頭からしっぽまで食べるとカルシウムがとれます。運動して骨を刺激し、カルシウムをとることで丈夫な骨を作ることができます。
10月11日 金曜日
麦ご飯 牛乳 麻婆豆腐 棒々鶏サラダ
棒々鶏サラダは、鶏肉をやわらかくするために棒で叩いたためこの名前があるそうです。給食では鶏のささみに醤油とお酒を入れて加熱しながら叩いてほぐしています。
10月10日 木曜日
人参ごはん 牛乳 五目汁 卵焼き おかか和え
目に良いビタミンAがたくさん含まれている人参ごはんです。ご飯を炊くときに切った人参を加えて炊きます。炊き上がったら、塩昆布と茹でておいた枝豆と一緒に混ぜて出来上がりです。人参が苦手でも食べられるようになるかもしれませんね!
10月9日 水曜日
ミルクパン 牛乳 ちゃんこうどん コーンサラダ ブルーベリージャム
10月10日「目の愛護デー」は数字を横にすると目とまゆの形に見えることから制定された記念日です。私たちの生活は、テレビ・パソコン・携帯電話など、知らず知らずのうちに目をたくさん使っています。しかし、疲れ目をそのままにしていると、視力が低下したり、頭痛や肩こりといった症状が現れることがあります。姿勢や部屋の明るさに注意し、時間を決めて目を休めるようにしましょう。目に良い食べ物はビタミンA・カロテンを多く含む 人参・ほうれん草・うなぎ・レバーなど、アントシアニンを多く含むブルーベリー・ぶどう・なすなどです。これらの食べ物をうまく取り入れながら毎日バランスのとれた食生活を心がけていきましょう。
10月8日 火曜日
麦ご飯 牛乳 がんもと野菜のうま煮 山吹和え シャインマスカット
今日のぶどうは三玉校区の社方ぶどう園さんから、「三玉小学校のみなさんにどうぞ!」とプレゼントしていただきました。このぶどうは、シャインマスカットという種類のぶどうで「皮ごと食べられる」「種がほとんどない」「粒が大きい」「とても甘い」という特徴を持つ、「ぶどうの女王」と呼ばれているそうです。
地域の方々から三玉小学校のみんなが応援していただいていることに感謝して、美味しく頂きましょう!
10月7日 月曜日
麦ご飯 牛乳 秋野菜のみそ汁 ほきの南蛮漬け ミニとまと
今日のお味噌汁の中にはこれからが旬の野菜やきのこが入っています。おみそ汁の具、全部わかりますか?しめじ・なめこ・にんじん・さといも・はくさい・ねぎ・・・
10月4日 金曜日
揚げパン 牛乳 八宝菜 こんにゃくサラダ
揚げパンは、パン屋さんから来たコッペパンを給食室のフライヤーであげています。焼きたてみたいにふわふわして、きな粉と砂糖が甘くて美味しいですね!
10月3日 木曜日
麦ご飯 牛乳 根菜汁 鰯の梅煮 卯の花炒り
おからは豆腐の絞りかすからできる栄養たっぷりの食材です。「卯の花いり」の「卯の花」は、おからの別名です。卯の花の小さな花が集まる様子がおからと似ていることからおからは「卯の花」とも言われるようになりました。
10月2日 水曜日
丸パン 牛乳 コーンと卵のスープ タンドリーチキン マカロニサラダ
タンドリーチキンは、ヨーグルトと香辛料に漬け込んだ鶏肉をタンドールとよばれる筒型の窯で焼くインド料理です。タンドールが変形してタンドリーチキンとなったようです。給食では、オーブンで焼きました。
10月1日 火曜日
麦ご飯 牛乳 ワンタンスープ チンジャオロースー
気持ちの良い秋空が広がる季節になりました。秋は「芸術の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」といわれるように、色々なことにじっくり取り組むことができる季節でもあります。そして、『味覚の秋』といわれるように、今が旬のさつまいも、栗、きのこ類など食べ物がたくさんあります。実りの秋に感謝しながら美味しい秋の味覚を楽しみましょう。
9月30日 月曜日
麦ご飯 牛乳 はんぺんすまし汁 鶏肉のさっぱり煮 もやしのごま和え
鶏肉のさっぱり煮は、照り焼きと同じ調味量に酢を足して煮込んであります。酢を加えることでさっぱりとした味になりますね!酢には食欲が出る効果や疲れを回復する効果、カルシウムの吸収をよくしてくれる効果があります。
9月27日 金曜日
丸パン 牛乳 コーンクリームスープ ハンバーグ イタリアンサラダ
今日のクリームスープは、バターでコクを出して米粉を牛乳で溶いてとろみをつけています。ホワイトルーよりも手間をかけずに作ることができますね!
9月26日 木曜日
麦ご飯 牛乳 肉じゃが 酢味噌和え
問題です!日本で一番多くじゃが芋を作っているのはどこでしょう?
①長崎県 ②北海道 ③千葉県
答えは・・・②北海道です。北海道はじゃが芋の収穫量が日本一で日本で生産される約80%が北海道産です。今日の給食の肉じゃがのじゃが芋も北海道産です。
じゃが芋は、炭水化物やビタミンCたくさん含まれています。
9月25日 水曜日
コッペパン 牛乳 焼きそば 豆腐サラダ
今日の給食は、焼きそばに6玉のきゃべつ、サラダに5玉のきゃべつをつかっています。きゃべつは生で食べるとビタミンCが効果的に摂ることができます。
9月24日 火曜日
麦ご飯 牛乳 具だくさんみそ汁 鮭の塩焼き 野菜の甘酢和え
朝晩、涼しくなってきて食欲も出てくると思います。しっかり食事をとって昼間の暑さを乗り切りましょう!
9月20日 金曜日
麦ご飯 牛乳 ドライカレー コールスローサラダ ぶどうゼリー
今日のドライカレーには、秋が旬のなすが入っています。ドライカレーはカレーライスと違って野菜の水分だけで作ります。玉ねぎやトマト、なすの美味しさがぎゅっとつまっていますね!
9月19日 木曜日
栗ご飯 牛乳 つぼん汁 ほき天玉揚げ 梨サラダ
今月の「ふるさとくまさんデー」は人吉・球磨のあじです。人吉・球磨地方は熊本県の南部に位置する山間部を含む広い地域です。熊本県の栗の生産高は全国2位です。それを支えているのが、山鹿市や人吉・球磨地方の栗だと言われています。今日の栗は菊鹿町の鹿子木農園さんで収穫された栗です。また、人吉・球磨地方では梨の生産も盛んです。サラダの梨は、三玉校区で収穫された梨です。つぼん汁は、人吉・球磨地方の郷土食です。秋祭りの時に食べられていた料理です。
9月18日 水曜日
コッペパン 牛乳 スタミナスパゲッティ 海藻サラダ
まだまだ暑い日が続いています。にんにくたっぷりのスパゲッティを食べて運動会の練習がんばりましょう!
9月17日 火曜日
麦ご飯 牛乳 里芋のうま煮 即席漬け お月見団子
今日は、十五夜です。お月見でおなじみの十五夜は、中秋の名月といわれ、旧暦の8月15日をさします。中秋とは秋の真ん中という意味で、昔は7~9月が秋にあたるため、秋の真ん中である8月15日の十五夜を「中秋の名月」と呼んでいました。お月見をするようになったのは、月の満ち欠けが暮らしや農作業に関わったとして、収穫したものには「おかげさまで今年も無事に収穫ができました」、これから収穫する物は「どうぞ豊作でありますように」そして「私たちの命が今あるのは、ご先祖様のおかげです」と月に感謝し、祈りを捧げるようになったのです。
9月13日 金曜日
ミルクパン 牛乳 冷やしうどん きびなごフライ ぶどう
今日のぶどうは、三玉校区の今田地区で収穫されたぶどうの王様「巨峰」です。今年は暑くて栽培がとても大変だったそうです。巨峰は糖度が高くポリフェノールや食物繊維がたくさん含まれています。また、素早く体の中で必要なエネルギーに変わります。そのため夏バテや疲労回復にとても効果があります。
9月12日 木曜日
麦ご飯 牛乳 肉豆腐 磯和え
肉豆腐とすき焼きの違いは、肉豆腐は皿料理ですが、すき焼きは鍋料理にになります。肉豆腐は豆腐がメインなので他の材料がシンプルです。すき焼きは具材を多くして豆腐以外の具材も味わいます。味付けも肉豆腐の方がすき焼きよりも味がさっぱりしています。
毎日「宇宙一美味しい給食」「世界一美味しい給食」と言ってくれる2年生が、今日は「レストランよりおいしかったです!」と言ってくれました(*^▽^*)
9月11日 水曜日
ミルクパン 牛乳 レタスと卵のスープ 酢豚 フルーツゼリー
給食の酢豚には、じゃが芋が入っているのが特徴です。下味をつけたお肉を油で揚げる前にじゃが芋を油で揚げておきます。酢豚の量が増えて、じゃが芋に味が絡んで食べやすくなりますね!
9月10日 火曜日
麦ご飯 牛乳 春雨スープ プルコギ
給食のプルコギはしょうゆ・甜麺醤・お酒・ごま・砂糖・こしょう・ごま油・にんにく・はちみつをまぜあわせてお肉をつけ込みます。朝9時にお肉が配達されてきてすぐにつけ込み冷蔵庫に入れておきます。11時位から炒め始めます。味のついたお肉を炒めその後に野菜を炒めていきます。お家に調味料がそろっていれば好みの味つけができます。「給食のプルコギはお店のより美味しい!」とよく言われます。
9月9日 月曜日
ほきの黄金焼きは、塩・こしょうをしたほきにクリームコーンとマヨネーズを混ぜあわてのせます。それをオーブンで焼きます。オーブンで焼くとクリームコーンが黄金に見えるような気がしますね!
9月6日 金曜日
親子丼 牛乳 鶏ささみの中華サラダ
親子丼は、だし汁と調味量で鶏肉を煮て卵でとじ、ご飯の上にのせて食べます。さて、なぜ親子丼かわかりますか?卵と鶏肉が使われているからなんですね!では、いとこ丼は何と何が使われているでしょう?答えは鴨肉と卵です。鴨肉が鶏に似ているからだそうです。
9月5日 木曜日
ひじきキムチチャーハン 牛乳 ワカメスープ 三色ナムル
ひじきキムチチャーハンは、いつものキムチチャーハンに鉄分・カルシウム・食物繊維がたくさん含まれているひじきを加えて作ってみました。
9月4日 水曜日
ツナコーンパン 牛乳 野菜のスープ煮 フルーツヨーグルト
ツナコーンパンは、ツナ・コーン・玉ねぎ・マヨネーズを混ぜて食パンにのせ、さらにチーズをのせてオーブンで焼きます。お家でもできそうですね!
9月3日 火曜日
麦ご飯 牛乳 かぼちゃのみそ汁 チキン南蛮 かりかり和え
チキン南蛮は、宮崎県のご当地グルメとして有名です。今日は給食室でチャレンジしてみました。塩・こしょうをした鶏肉に小麦粉をまぶし、溶き卵にくぐらせて油で揚げます。その後、甘酢に漬け込んでタルタルソースをかけて出来上がりです。
9月2日 月曜日
麦ご飯 牛乳 さんまのみぞれ煮 豆腐汁 アーモンド和え
秋の魚といえば、さんまですね!さんまのあぶら部分には、記憶力がよくなるEPA(エイコサペンタエン酸)・DHA(ドコサヘキサエン酸)がたくさん含まれています。また、貧血予防によいビタミンB群、カルシウムの吸収を助けるビタミンDも多く含まれています。
8月28日 水曜日
麦ご飯 牛乳 根菜入り肉信田 コーンと卵のスープ グリーンサラダ
夏休みが終わりましたが、まだまだ暑い日が続いています。生活リズムが乱れていると体調をくずしてしまうこともあります。
「早寝・早起き・朝ごはん」で、しっかりと生活を整えて元気に残暑をのりきりましょう。
7月19日 金曜日
ミルクパン 牛乳 冷やし中華 シュウマイ
今日は1学期最後の給食です。2学期も元気に登校できるように、睡眠をしっかりとって、バランスの良い食事をきちんと食べて、元気に遊んで、生活リズムを崩さないように夏休みを過ごしましょう!宿題も忘れずに!!!

7月18日 木曜日
生姜チャーハン 牛乳 い草そうめん汁 とまとサラダ
今月のふるさとくまさんデーは八代市です。八代市は熊本県の南に位置しています。江戸時代には城下町として栄え、2005年に八代市・鏡町・千丁町・泉村・坂本村・東陽村が合併し新しい八代市となりました。特産品には「しょうが」や「い草」、「はちべえとまと」があります。
7月17日 水曜日
シュガートースト 牛乳 野菜のスープ煮 小魚とチーズのサラダ
チーズと小魚にはカルシウムがたくさん含まれています。カルシウムはどんどん成長しているみんなには、骨が成長するために必要な栄養です。骨が成長するときにカルシウムが摂れていないと弱い骨になって骨折しやすくなります。カルシウムが多く含まれる食べ物は他にどんな食べ物があるか気にかけてみてください。
7月16日 火曜日
麦ご飯 牛乳 カレー肉じゃが 冬瓜サラダ
カレー肉じゃがは、いつもの肉じゃがにカレー粉が入っています。暑い屋外や冷房の効いた屋内を行ったり来たりしていると体が温度変化についていけなくなり、体の調子が悪くなってきます。カレーには血液の流れをよくして体を温める効果があり、体の調子を整えてくれます。
7月12日 金曜日
麦ご飯 牛乳 夏野菜カレー グリーンサラダ
夏野菜カレーには、かぼちゃ・なす・玉ねぎ・枝豆が入っています。お肉もビタミンBが多く含まれている豚肉を使っています。苦手な野菜もカレーに入っていると食べやすいですね!
7月11日 木曜日
キムたくチャーハン 牛乳 スーミータン きゅうりとわかめの酢の物
キムたくチャーハンは、ごま油でキムチと千切りに切ったたくあんを炒め醤油とみりんで少し味をつけておきます。から煎りしたちりめんと茹でておいたピーマンを一緒にご飯に入れて混ぜ合わせます。
7月10日 水曜日
食パン 牛乳 八宝菜 中華和え あんこかし
山鹿市は、13日からお盆になります。お盆の入りにお供えする団子を お迎え団子といいます。ご先祖様の長旅をいたわり、疲れをいやしていただくという意味で、あんこやみたらしなどの甘い味付けのお団子をお供えします。給食室では小豆を炊いてあんこを作り、白玉餅を1つ1つ丸めました。手作りの団子はとてもおいしかったです。
7月9日 火曜日
麦ご飯 牛乳 夏のっぺ いわしのみぞれ煮 おかか和え
夏のっぺには、冬瓜・おくら・なすなど夏にたくさん収穫される野菜が入っています。夏野菜には強い紫外線や熱中症、夏バテから体を守ってくれるビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素がたくさん含まれています。夏野菜を食べて暑い時期を元気に過ごしましょう!
7月8日 月曜日
タコライス 牛乳 あおさ汁 ヨーグルト
「タコライス」はメキシコ料理の「タコス」がヒントになって誕生した沖縄オリジナルの料理です。「タコス」は、スパイシーに炒めたひき肉と玉ねぎ、レタス、とまと、チーズをとうもろこしで作ったうすい生地(トルティーヤ)の上にのせてくるめています。その上からサルサ(スペイン語で「ソース」)をかけて食べるメキシコの伝統料理です。その「タコス」で使う具材とサルサをお皿に盛ったご飯の上にのせて食べるのが「タコライス」で、タコス+ライスで「タコライス」と名付けられました。
7月5日 金曜日
丸パン 牛乳 コーンスープ 星形コロッケ 枝豆サラダ
7月7日は「七夕」ですね!給食では少し早いですが「七夕」メニューです。みんなが、短冊に込めた願い事が叶うといいですね!今年は天の川を見ることができるでしょうか?織り姫と彦星が会えるといいですね!
7月4日 木曜日
干ぴょうご飯 牛乳 はんぺん汁 千草焼き 昆布和え
干ぴょうご飯は、甘辛く炊いた干ぴょうと椎茸を「酢飯」に混ぜています。「酢」には体の中の働きをよくしたり、食べたものを効率よくエネルギーに変えて疲れをとってくれたり、スタミナアップをしてくれます。
7月3日 水曜日
コッペパン 牛乳 ポークビーンズ 甘夏サラダ
甘夏サラダの甘夏みかんは缶詰に加工されたものを使用しています。甘夏は甘酸っぱく果肉が大きいのでプチプチとした食感がありますね。甘夏にもビタミンBが多く含まれています。
山鹿市立三玉小学校
〒861‐0522
熊本県山鹿市久原2935番地
TEL 0968-43-1177
FAX 0968-42-8410
E-mail y-mitamaes@leaf.ocn.ne.jp
URL https://es.higo.ed.jp/mitamaes/
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 北山 綾
運用担当者 塚原 聡