2017年11月の記事一覧
校内研修
11月28日(火)
国語 5年天気を予想する 6年『鳥獣戯画』を読む
国語 5年天気を予想する 6年『鳥獣戯画』を読む
5年生。これまで、段落の構成をつかんできたことをふりかえり、今日のめあてをつかむ質問「今日は、その文にどんな資料が入るのか。」から。
自分で考える→グループで考える→資料の効果について考えるという流れでした。
それぞれもらった写真カード。

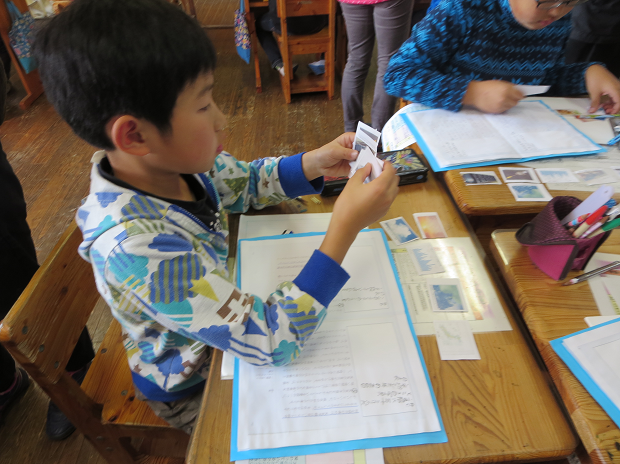
「この資料カード、この言葉があるからここ!」
「あれ?この資料は必要なのかな?」
読み込みながら、カードを置き換えたり、これは使わないんじゃないかな?と先生の ひっかけ に気付いたり。
頭をひねって、じっくり考えるの「か」です。
かかる時間には当然、個人差が。

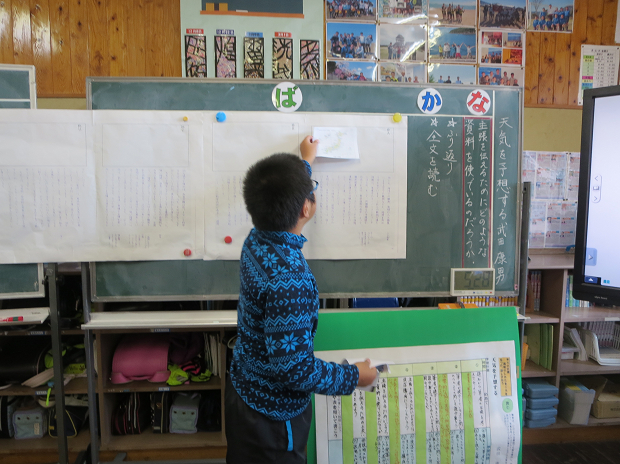
先生だけでなく、クラスメイトも個人差につきあい、普通に補い合う様子に、参観の先生から授業研究会で、「グループ学習の時、学習リーダーやみんなが、時間が必要なメンバーにもフォローするのがとてもすばらしかった。」と。
登校や縦割り班、部活、朝ラン、遠足、運動会、ぎんなん祭・・・・・日々の5,6年生の下の学年へのかっこよくて、だれにも優しい姿は、教室の中も同じです。
6年生。
少し前に、阿蘇小学校の研究授業に参加した先生が、「導入で、前時までの学習の振り返りを、電子黒板でスライドショーみたいにしてあったよ。とってもわかりやすかった。やってみたいな。」と話していました。


なるほど。きっとこんなふうにされていたんだな・・・。
自分で考える→グループで考える→資料の効果について考えるという流れでした。
それぞれもらった写真カード。

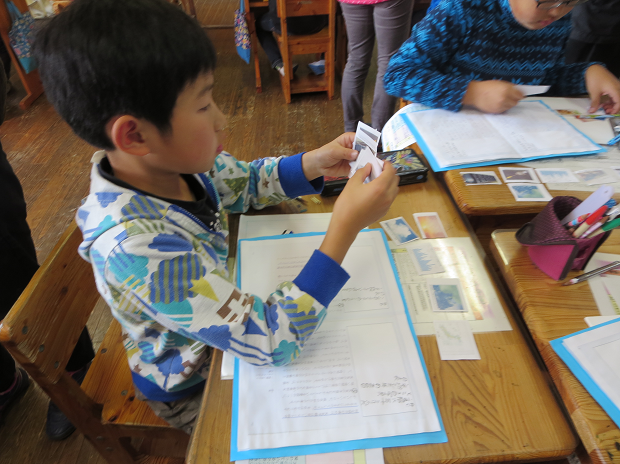
「この資料カード、この言葉があるからここ!」
「あれ?この資料は必要なのかな?」
読み込みながら、カードを置き換えたり、これは使わないんじゃないかな?と先生の ひっかけ に気付いたり。
頭をひねって、じっくり考えるの「か」です。
かかる時間には当然、個人差が。

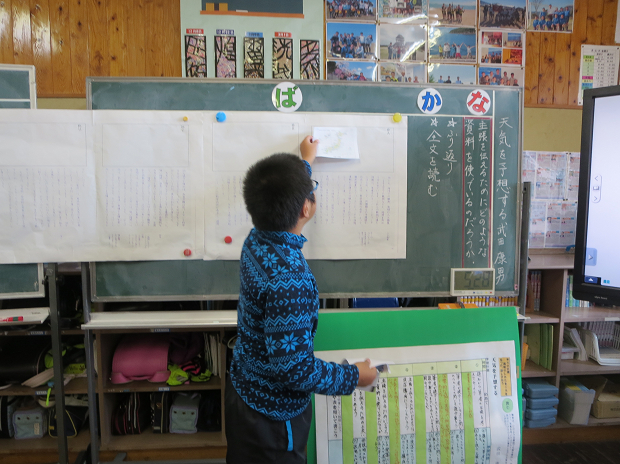
先生だけでなく、クラスメイトも個人差につきあい、普通に補い合う様子に、参観の先生から授業研究会で、「グループ学習の時、学習リーダーやみんなが、時間が必要なメンバーにもフォローするのがとてもすばらしかった。」と。
登校や縦割り班、部活、朝ラン、遠足、運動会、ぎんなん祭・・・・・日々の5,6年生の下の学年へのかっこよくて、だれにも優しい姿は、教室の中も同じです。
6年生。
少し前に、阿蘇小学校の研究授業に参加した先生が、「導入で、前時までの学習の振り返りを、電子黒板でスライドショーみたいにしてあったよ。とってもわかりやすかった。やってみたいな。」と話していました。


なるほど。きっとこんなふうにされていたんだな・・・。
事実と評価の色分けした書き込みと、段落構成の振り返りをして、今日は「おもしろさ」の謎解きです。
おもしろいと思ったことを個人で書き出す→グループで伝え合う→すばらしいところをまとめて発表する と言う流れでした。
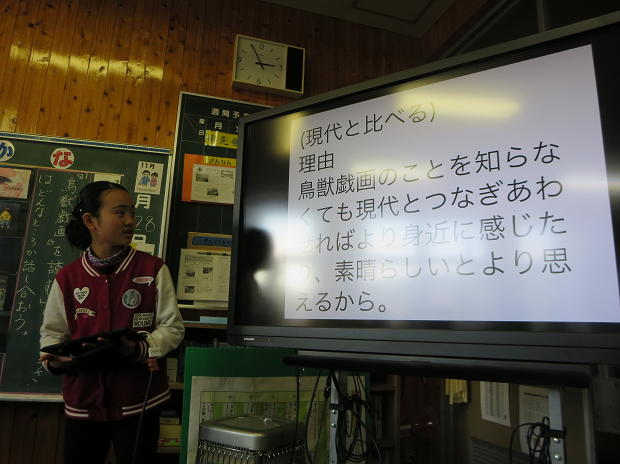

授業研究会で校長先生からの、「ホワイトボードやタブレットを使い、あえて少しずつ変えながら発表をしたのはなぜ?」
という質問は、「実は・・・」と、今日は国語の研究授業ですが、めあてに迫る工夫にICTがたくさん活用できますよ!と職員に知らせる「&ICT研修 #ロイロノート」の気持ちも含まれていましたという担任の思いを引き出しました。
おもしろいと思ったことを個人で書き出す→グループで伝え合う→すばらしいところをまとめて発表する と言う流れでした。
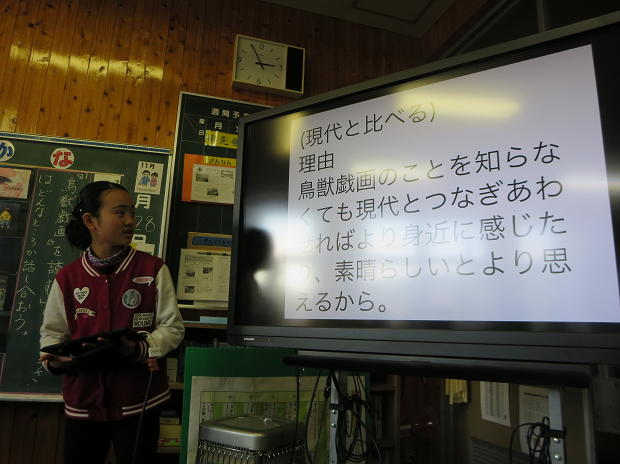

授業研究会で校長先生からの、「ホワイトボードやタブレットを使い、あえて少しずつ変えながら発表をしたのはなぜ?」
という質問は、「実は・・・」と、今日は国語の研究授業ですが、めあてに迫る工夫にICTがたくさん活用できますよ!と職員に知らせる「&ICT研修 #ロイロノート」の気持ちも含まれていましたという担任の思いを引き出しました。
授業は1時間でしたが、前の1年生の研究授業のときに続く、日常の授業や生活の積み重ねを感じる、たっぷりの1時間でした。

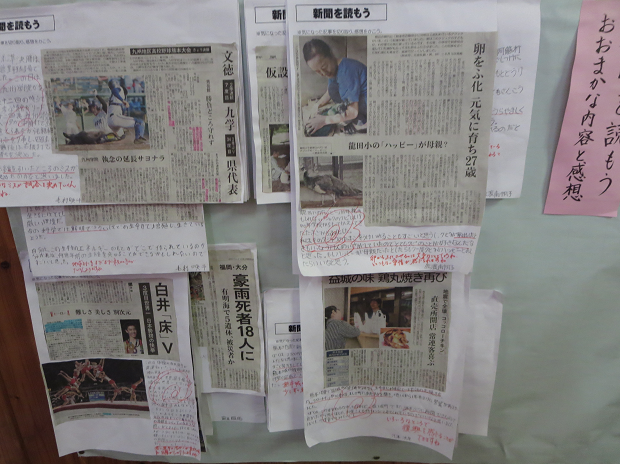
職員室に戻りながら、日々の複式のたいへんさを理解する教頭先生から担任へ、「複式だからこそ!」のプラスの応援(複式の教育効果)のお話が続いていました。

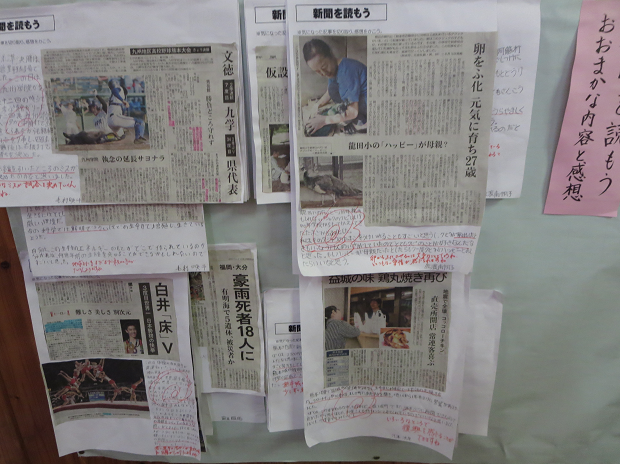
職員室に戻りながら、日々の複式のたいへんさを理解する教頭先生から担任へ、「複式だからこそ!」のプラスの応援(複式の教育効果)のお話が続いていました。
