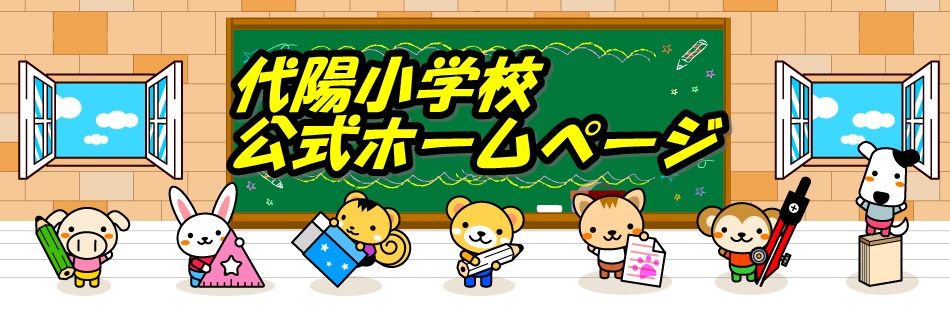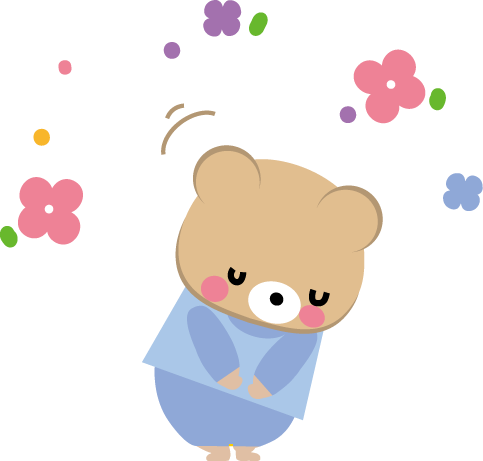令和7年度 校内研修計画
1 研究主題
共に学ぶよさを実感できる環境づくり
~学級・学年経営と授業実践を通して~
2 研究主題設定の理由
子どもたちは授業のみならず、学校生活のあらゆる場面で学んでいます。学校教育は子ども・教師が共に学び合うことを通して、子どもの人格形成に資することが最たる目的です。しかし、学校で子どもたちが一番長い時間を過ごす授業がなかなか成立しないという状況が近年の学校現場の課題です。これは本校にも当てはまります。授業改善の視点から様々な学習意欲を高める手立てを講じても、学ぶ意義を見出すことが難しい子どもには、あまり効果がありません。その背景として、個性の重視や個別最適化といった美化されたことばが一人歩きし、わたしたち教師の役割とは何か、その指導がブレているのではないかと考えることがあります。ゆえに、子どもの内面から集団への帰属意識(居心地のよさ)を高めていくことを第一に取り組みたいと考えました。特に子どもたちが学校生活を送る基本集団である「学級」や「学年」に焦点をあてます。わたしたち教師が行う学級・学年経営の充実なくして、授業改善はなし得ないと思います。そこで、研究主題を学校の本来の意味やわたしたちの指導について問い直すために、「共に学ぶよさを実感できる環境づくり」と広く設定しました。
「共に学ぶよさ」とは、わかるようになったうれしさや喜び、学び合うことで考えが変わったり深まったりすることの充実感、学ぶ楽しさなど、様々な意味を内包しています。強調したいのは、学びの主体は子ども・教師の双方であり、子どもも教師も「学ぶよさ」を実感できるようにすること、子どもと教師が協働して居心地のよい環境づくりに関わることを願って設定しています。
「環境づくり」と広く設定したのは、学校生活のあらゆる場面を射程に入れたかったからです。授業の場面だけでなく、登校から下校まで子どもたちがどのように過ごすか、共に学ぶよさを感じることができる教室とは、学級とは、学年とはを1年間問い続けていきたいと思います。
副題には、主題に迫るための二つの視点を入れています。学級・学年経営と授業実践(改善)について、研修を深めることで、子どもたちが共に学ぶよさを感じることができる手立てを全員で考えていきたい。
〇視点1【学級・学年経営の充実について】
<手立て>
①学びの土台となる学習規律をそろえ、徹底する
・「代陽っ子 学習の約束10か条」(特に、チャイム前着席・黙想) ・返事 ・「筆箱の中身」 など
②学びの土台となる集団意識を高める共通実践事項と学級経営におけるアイデアの共有
・学年集会 ・教科担任制の実施と成果・課題の共有 ・給食指導
・掃除指導 ・係活動 ・朝の会 ・帰りの会
・掲示 ・学級経営・授業実践座談会の実施 など
〇視点2【授業実践について】
<手立て>
①学び合うよさを実感できる授業デザインの工夫
・学習課題 ・問い(発問)・振り返り ・評価 ・学習態度
・発表の仕 ・聞き方・対話 ・ICT・単元構成 ・ノート指導 など
②学びをつなげる家庭学習の充実
・宿題の内容・チェックや見取りの工夫・自主学習のすすめ
・一人一台端末の活用(金曜4時間や学力保障のために)
・学習習慣の形成