
熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

ブログ
2014年10月の記事一覧
 2年生は給食センター見学に行きました。
2年生は給食センター見学に行きました。
先週の金曜日(17日)に2年生は生活科の学習で給食センターに行きました。
「まちたんけん・まちはっけん」の学習では、自分たちの住む地域の人々と触れ合う中で、自分たちの地域に愛着を持ち、人々と積極席に接していこうとする気持ちを持たせることをねらいとしています。
今回は、毎日食べている給食がどこから来るのかを中部給食センターに見学に行って学びました。
中部給食センターは、校区内の島田町にあります。センターでは、担当の田中先生に給食センターのお仕事についてお話を聞いたり、給食センターの中を案内していただいたりしました。
そのあと、考えてきた質問をしました。
毎日当たり前のように食べている給食が、たくさんの人々の力で作られているのだということがよくわかりました。

「まちたんけん・まちはっけん」の学習では、自分たちの住む地域の人々と触れ合う中で、自分たちの地域に愛着を持ち、人々と積極席に接していこうとする気持ちを持たせることをねらいとしています。
今回は、毎日食べている給食がどこから来るのかを中部給食センターに見学に行って学びました。
中部給食センターは、校区内の島田町にあります。センターでは、担当の田中先生に給食センターのお仕事についてお話を聞いたり、給食センターの中を案内していただいたりしました。
そのあと、考えてきた質問をしました。
毎日当たり前のように食べている給食が、たくさんの人々の力で作られているのだということがよくわかりました。

 花火見物は大人の人と一緒に
花火見物は大人の人と一緒に
 今日(10/18)は、全国花火大会です。担任の先生からも言われていると思いますが、子どもだけで花火を見に行くのは禁止です。
今日(10/18)は、全国花火大会です。担任の先生からも言われていると思いますが、子どもだけで花火を見に行くのは禁止です。大人の人と一緒に行きましょう。
※大人というのは成人した人です。小中高校生のお兄さんお姉さんのことではありません。
きまりはみんなを守るため
 上のメニューの「きまり」のページにも書いてありますが、学校の下校は午後4時30分です。
上のメニューの「きまり」のページにも書いてありますが、学校の下校は午後4時30分です。「おそくとも4時30分までには、学校の門から出ます。」という意味なのです。
私は、午後5時ころ児童玄関のとじまりをしますが、その時間にまだ遊具で遊んでいる人がいます。(あれっ、この時間は部活動の人しかいないはずなのに…。)
上の写真にもあるすべり台やブランコで何人かの人が遊んでいます。
そのたびに「下校時刻は過ぎています。帰りなさい。」と言っています。
どうやら子どもたちの中には、下校時刻というのは「4時30分までに教室を出ること」とかん違いしている人がいるようです。
担任の先生からも指導していただいていますが、下校時刻は交通事故や不審な人からみんなを守るために決めてあります。
時々学校に「まだうちの子どもが帰っていないんですがもう学校は出たのでしょうか。」というお問い合わせがあります。6時過ぎた時間です。
下校時刻を守らないとおうちの人にも大変な心配をかけます。
下校時刻は、学年によっても違い、毎週担任の先生から1週間の計画も出ていると思います。おうちの人を心配させないためにも下校時刻を守りましょう。また、おうちの人と下校についてもお話しておきましょう。
事故が起きてからでは遅いのです。
 栄光を目指して
栄光を目指して
陸上記録会の練習が熱を帯びてきました。六年生は、朝と昼休みに熱心に自分の種目に取り組んでいます。


教材研究!(外国語活動)
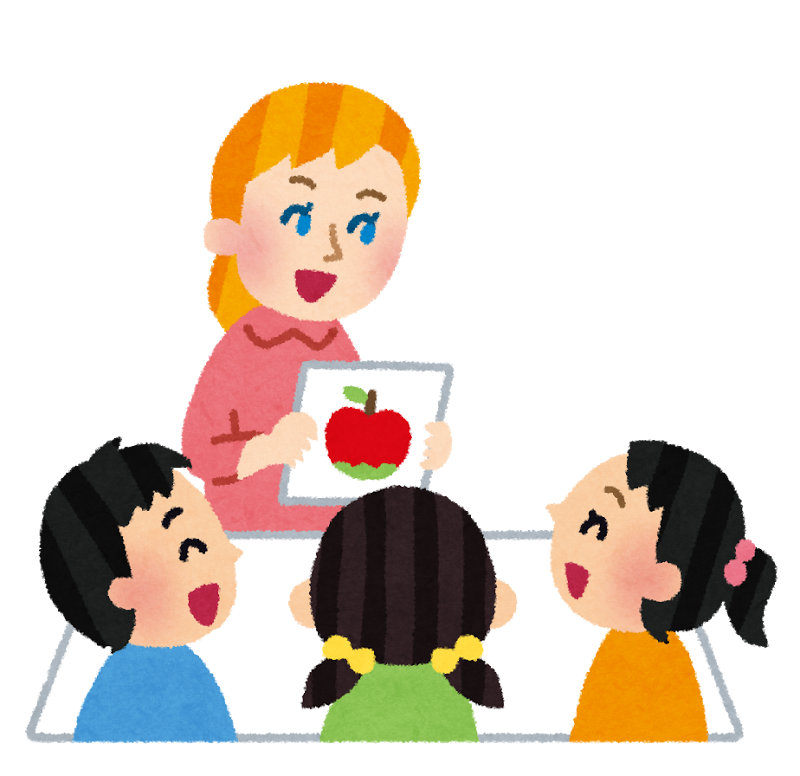 平成23年度より小学校において「外国語活動」が必修化されました。
平成23年度より小学校において「外国語活動」が必修化されました。これは、小学校の子どもたちにも英語を身近なものに感じさせ、慣れ親しませることを第一の目的にしています。
年間35時間で、5年生と6年生が取り組んでいます。
もちろん、総合的な学習の時間で、4年生以下もケビン先生と一緒に英語で楽しく遊ぶ時間を設けていますが、5年生と6年生は「外国語活動」として年間計画に位置付けられています。(学習指導要領に位置付けがあります。)
外国語活動という名前ですが、実際にはその多くが『英語』に親しむ時間です。では、外国語活動の時間は、英語を話すことのできる外国人の先生(本校ならケビン先生)が主になって授業が進められるのでしょうか。

いえ、文部科学省は、あくまで、担任の先生が授業の主になり進めてくださいと言っています。
したがって、英語が得意とか苦手とか言ってはいられません。小学校の先生たちもみんな英語に取り組んでいます。
もちろん、流ちょうに話すということではなく、「英語は楽しいんだよ、外国ってどんなところかな」そんな風に子どもたちに興味を持たせ、一緒に英語を楽しもうという姿勢で授業を組み立てています。
さて、上の写真は6年生の担任の先生です。明日の外国語活動の時間のために「教材研究」をされています。
 教材研究というのは私たちが授業をどのように組み立て、すすめていくかといった授業を準備すること全部をいいます。
教材研究というのは私たちが授業をどのように組み立て、すすめていくかといった授業を準備すること全部をいいます。先生は、どんな授業をされるのでしょう。明日の授業が楽しみですね。
情報教育に関するお知らせ
本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。
情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。
ぜひご覧下さい。
02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx
03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx
04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx
05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx
06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx
07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx
☎ 連絡先
熊本県八代市日置町
445番地
八代市立 太田郷小学校
TEL 0965-32-6143
FAX 0965-32-6144
 es-otago@yatsushiro.jp
es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。
http://es.higo.ed.jp/otago/
リンク
アクセスカウンター
2
2
3
3
5
8
下記正式登録HPです
熊本県教育情報システム
登録機関(CMS)
管理責任者
校長 大住 和行
運用担当者
教諭 鶴山 典子
災害対応・心のケア等について
ダウンロードしてご確認ください。
〈熊本県電話相談窓口一覧〉
〈性暴力に関するパンフレット〉
⑤性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用).pdf
〈防災関係〉
災害発生時の対応について.pdf
震災後の心のケアについて.pdf
震災後の心のケアについて2.pdf
◇ 大切なお願い ◇
①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)
➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。
➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。
④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。


