

それほど頑張らずに、「習慣化」
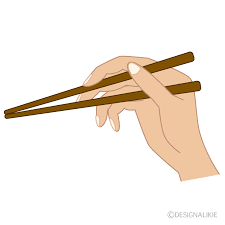
習慣化の特徴は、「その行動をするのが、当たり前に感じる」「その行動をしない方が気持ち悪いと、違和感を覚えることもある」「意志の力はあまり必要なく、無意識のうちに行っていることが多い」「頑張らずにずっと継続できる。むしろやめようと思っても、やめられない」‥等という点にあります。
これらの習慣化の特徴を活かして、「やり続けたいこと」を意図的に習慣化すると、自分の行動をコントロールしやすくなります。
(慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 前野隆司教授 参照)
◎豊かな食生活につながる「歯の健康」
◎健康な身体を創る「バランスのよい食事」
◎夢の選択を拡げる「確かな学力」
◎他者と心地よく繋がる「社会形成能力」
さて、姫戸小で取り組んでいる上記(↑)の育成4項目についても、この「習慣化」の特徴を活かして、お箸を持つようにスムーズに、そんなに頑張らせずに「やり続けさせる」ことができないものかと頭をひねっているところです。
昨年度から取り組んでいる「音韻トレーニング」は、自立支援相談員の辻川先生にご指導をいただき、本校の特別支援コーディネーターである小野先生の快活な号令と周到な準備の下、子ども達に「何故このトレーニングが必要なのか」「これを頑張れば何ができるようになるのか」をしっかり理解させたうえで、全学級で足並みを揃えて行っています(令和4年度学校だより第15号参照)。
次のプリント、その次のプリントと、自分から求めてトレーニングを進める者も増え、先日は「100枚達成!賞」の賞状を手渡しました。その効果は顕著で、「聞く力」を高め「言葉のまとまりを捉える力」の向上に大変役立っています。
多くの子ども達にとって朝自習や宿題等で行う「音韻トレーニング」は、それほど頑張らなくても継続できる「習慣化」された取組になりつつあります。
考えるに‥、「習慣化」のポイントは、次の4点にありそうです。
☆そもそも何故、日常の習慣にするくらい身に付けなければならないかを、子ども達に肚落ちさせる(なるほど、納得! やってみようかな!)
☆やってみての成果が「すぐ表れる」→「誉められる」→「楽しいと思える」→「続けてみよう」と思う
☆それを行う時間や機会を、ちゃんと設定する
☆「自分で進んでやってる感」を持たせる
※子ども、保護者、職員の「肚落ち」が、まず必要。
〒866-0101
熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3
上天草市立姫戸小学校
TEL 0969-58-2068
FAX 0969-58-2147
E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp
URL http://es.higo.ed.jp/himedo/
*白嶽山頂からの眺望 *碧い海の向こうに八代が見えます *近々、隣の峰までジップラインが設置されるそうです(楽しみ(*^_^*)
熊本県教育情報システム登録機関
管理責任者
校長 土屋 寛仁
運用担当者
教諭 濱﨑 伸太郞
栄養教諭 花田 千賀
歯・口 キャラクター「ハミーちゃん」


