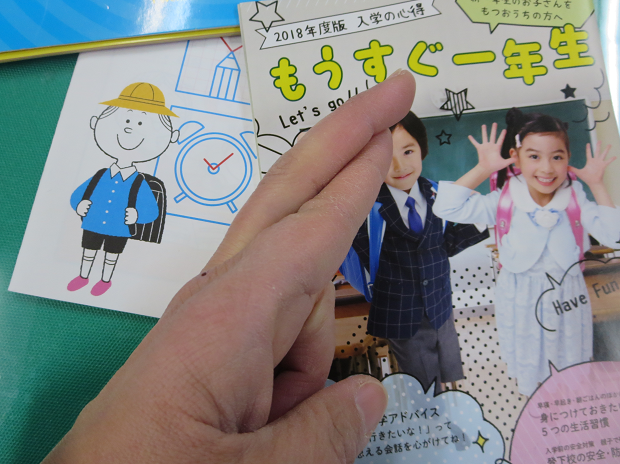「ら」
「ら」い(来)年一年生をむかえる会の準備
2月8日 5時間目の全校学活は、5年生(新6年生)の、本物の話し合い活動デビューでした。
少し前から、教室で話し合われていました。
当日、業間前にはすでに会場作りがバッチリ完了。
正面の黒板に
「ぎだい」(1年生をむかえる会(2月19日)の計画をたてよう。)
「ていあんりゆう」(春から1年生が登校するために、1年生を迎える会をします。その会のために、今日の会をします。)
が、大きなていねいな字で書いてありました。
司会が活動の流れを説明。
毎月の全校集会などとはちがう空気を感じて、みんなキリリと前に立つ人を見ています。各班の話し合いでも、5年生が話をすすめます。
することだけを決めるのではなく、「誰が何をする」とか、「これを作っておこう」とかまで、先を見ての段取りをしてくれていました。
6年生は、班の全員がたくさん発表できるように、下の学年の子の横について、まわりを見て、合わせて動いていました。
今日の議題は『自分の考えをもって!』話し合うという点はうすかったのですが、こうしたスタイルの会を、全学年が知って(経験して)おくことは、楽しい、豊かな学校(学級)をつくるためにとっても大事な場です。
5年生の「率先」した行動に拍手でした。(そして、スーパーサポート6年生、ありがとう。)
会が終わってからの片付けを、4年生がお手伝いしました。
実は数日前(2月5日)すでに、1年生が「話し合い活動 初級」をしていました。
1年生が、新1年生を招待してなにをするか計画について話し合いです。
毎日毎日している朝・帰りの会の司会や、授業中の学習リーダーはどんどん上手になってきています。
が、この話し合いでは司会が自分の発表もしたくなったり、黒板書記がうまくまとめて書くなどはむずかしくて。
先生にひとつずつアドバイスしてもらいながらでした。
それでも、自分の役割をきちんとやりきって、小さいけど「ひとつの達成感」を感じたようでした。
人数が少なくても、低学年でも、こうした場を持つことにこだわります。
「みんなで話し合って決める」経験を重ねて、数年後は学校のリーダーさんに。